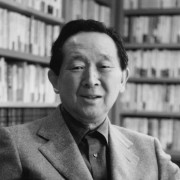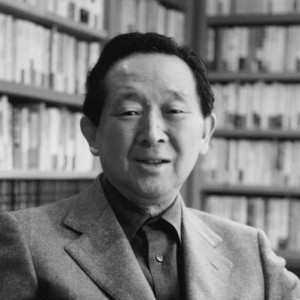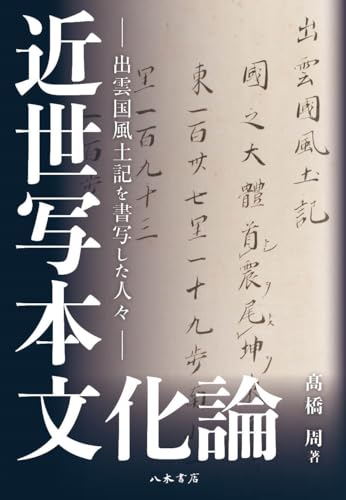書評
『土から生まれた―津軽の画家 常田健が遺したもの』(平凡社)
常田健は主に農民の生活と労働を描いた。青春の一時期を除いて青森に住み自分も農民として生きた。この無名であった画家の巡回展は五十五日間で一万三五〇〇人を集めたという。ここ数年、美術館への入場者が、特別の企画展でもない限り、最盛時の半分以下になってしまったと伝えられている時、この数字は何を物語っているのだろう。その理由を解き明かしてくれているのが本書である。
この『土から生まれた』(平凡社)は、常田健の書いた詩と断章を「二つの巨像」「木と草のごとく」「申し分のない暮らし」の三章にまとめてある。ここには絵画論、農民を描いたブリューゲルと絵巻物の比較論があり、人生哲学があり、詩があり、体制批判がある。ないのは理論への拘泥であり時流におもねようとするいじましさである。
この特徴は彼の絵画作品そのままと言えよう。彼の絵をはじめて見た時、私はメキシコが植民地の状態から脱却し、国の独立のための革命的な戦いのなかで生まれた一九一〇年代のメキシコ社会派と呼ばれた作品群を思い出した。オロスコ、リベラ、シケイメロスらを指導者とする新しい絵画運動は、壁画をひとつの有力な表現の手法として民衆の運動に働きかけていった。その時期、公共の場の壁面は民衆の意志表示の場であった。わが国では現在、公共の場とは政府が所有し管理している、民衆とは無縁の空間なのだが。
常田健は、屈折した表現ではあるが、
と書いている。確かに彼の素朴な絵画作品は、そのような明日へと繋(つなが)る、生きる力を表現しているのである。
この『土から生まれた』(平凡社)は、常田健の書いた詩と断章を「二つの巨像」「木と草のごとく」「申し分のない暮らし」の三章にまとめてある。ここには絵画論、農民を描いたブリューゲルと絵巻物の比較論があり、人生哲学があり、詩があり、体制批判がある。ないのは理論への拘泥であり時流におもねようとするいじましさである。
この特徴は彼の絵画作品そのままと言えよう。彼の絵をはじめて見た時、私はメキシコが植民地の状態から脱却し、国の独立のための革命的な戦いのなかで生まれた一九一〇年代のメキシコ社会派と呼ばれた作品群を思い出した。オロスコ、リベラ、シケイメロスらを指導者とする新しい絵画運動は、壁画をひとつの有力な表現の手法として民衆の運動に働きかけていった。その時期、公共の場の壁面は民衆の意志表示の場であった。わが国では現在、公共の場とは政府が所有し管理している、民衆とは無縁の空間なのだが。
常田健は、屈折した表現ではあるが、
あのような盛り上る民衆の息吹が、生き生きとした、ある直(ちょく)截(せつ)な感動を投げかけないとは言われぬ。僕ら何を描いても、このような感動を百パーセント身内に漲(みなぎ)らせるべきだと思う。(中略)けっしてそれは強引な主観でなく、僕は少なくとも人間に対して、これだけの信頼は持ちたい。
と書いている。確かに彼の素朴な絵画作品は、そのような明日へと繋(つなが)る、生きる力を表現しているのである。
初出メディア
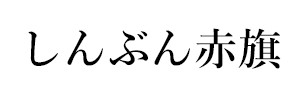
しんぶん赤旗 2002年5月27日
ALL REVIEWSをフォローする