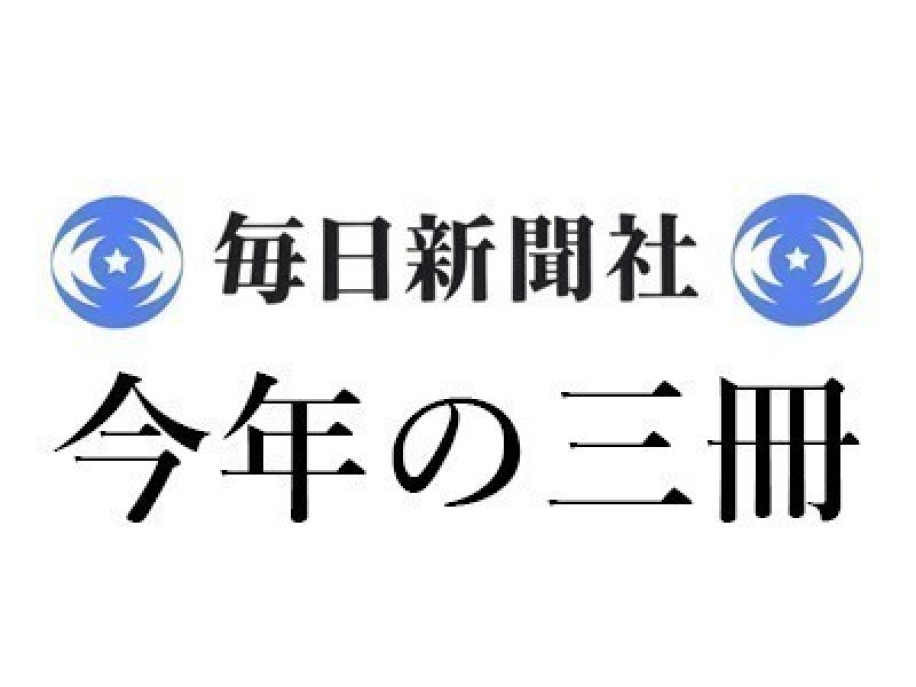書評
『馬と人の江戸時代』(吉川弘文館)
いななきが聞こえる
テレビや映画の時代劇に、馬はごくふつうに出てくる。では、江戸時代の馬はいったいどこで生まれ育ち、どのように役目を与えられ、どんなふうに死んでいったのだろう。ほとんど気に留められることもなかったその一生、生産や流通の実態、人間とのかかわりなどを、史料を丹念に集めて浮き彫りにしていく。時代劇の道具から、歴史の重要なキャストへと、馬をうまく引っぱり上げた。
信長や秀吉といった権力者と馬との関係史から、語りは起こされる。乗用や贈答・下賜品として用いるために東北の良馬を調達するシステムは、家康以来、幕府の中につくられていく。生類を憐(あわ)れんだ五代綱吉がそれに制約をかけたり、偉丈夫だった八代吉宗が馬も大きくしようと西洋馬を輸入したり、将軍の個性や施策によってシステムが刻々変わるようすは興味を引く。
男(牡馬〈ぼば〉)に生まれるか女(牝馬〈ひんば〉)に生まれるか、幕府や藩の牧で育つか村で育つか、見ばえや能力などのスペックが優れているかどうか。馬の一生もほぼそれで決まった。力を出せずエリートから「転落」する馬もいた。人がつくる厳しい社会に、江戸時代の馬たちは完全に組み込まれ、歴史の一役を担った。
船の転覆事故や火事で命を落とした馬、牧場で狼(おおかみ)に襲われる馬、飢饉(ききん)と馬肉食のはじまり、馬の供養やまつりなど、馬と人とが織りなした悲喜こもごものエピソードも豊富だ。行間から馬のいななきが聞こえ、臭いがただよってくるかのよう。筋道だった論理をふりかざすことだけではない。そこに置き去られた過去の音や臭いまで感じ取ろうとする謙虚な敏感さが歴史を語る上で大切なのだと気づかせてくれる。
著者は、良馬を産した盛岡の人で、東北で歴史を学び、研究を積み重ねてきた。あとがきにも触れられている震災との遭遇が、そんな過去への敏感さの原点になっているように思える。東北発の新しい日本史の一著だ。
[書き手] 松木 武彦(まつぎ たけひこ・国立歴史民俗博物館教授)
ALL REVIEWSをフォローする