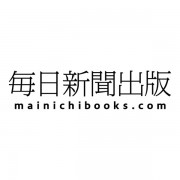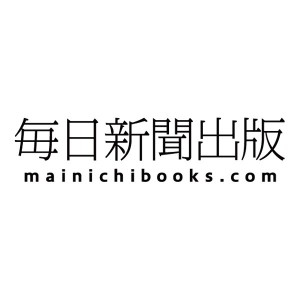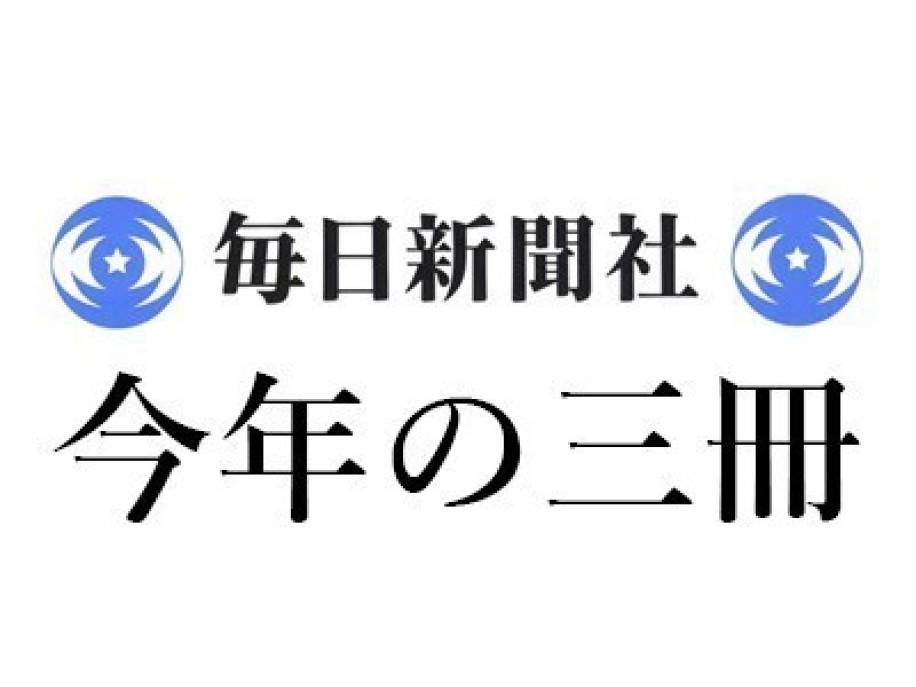前書き
『ウクライナ侵攻までの3000日 モスクワ特派員が見たロシア』(毎日新聞出版)
2022年2月にロシアがウクライナに侵攻してから、24日で1年が経過した。その影響は世界中に広がり、いまだ戦争には終わりが見えない。戦争を始めたプーチン大統領の本心とは何か? 現地からロシア、ウクライナの状況を伝え続ける毎日新聞モスクワ支局長・大前仁氏。『ウクライナ侵攻までの3000日 モスクワ特派員が見たロシア』(毎日新聞出版)は、最前線で取材を続ける記者のルポルタージュだ。ロシアがクリミア半島を併合した2014年から2022年までの3000日の間に、ウクライナ国内では何が起こり、どのようにして戦争につながっていったのか。本書の「序章」を特別公開する。
ドネツク州にあるマイオルスク村は、臨時の州都が置かれたクラマトルスクから南東の方角へ車で1時間と少しの距離にある。耳を澄ませば鳥のさえずりも聞こえてきそうで、のどかな光景が目の間に広がっている。
だが、この村はウクライナ軍がロシアの後ろ盾を得た武装勢力と対峙する最前線に置かれている。
ウクライナ軍の許可を得て、村内を歩くと、痛々しい傷痕が目に入ってきた。レンガ造りの家屋の屋根と壁は砲弾に直撃されて、大きく破損していた。半分以上の窓ガラスが割れて、ビニールで塞がれている。立派な作りの建物なのに、住人が去ってから久しいことが伝わってくる。
私はアパートの前に据えられたベンチに腰を下ろし、世間話に興じていた3人の女性と出会った。話を聞くと、全員が60代だという。旧ソ連の国では珍しくないことだが、彼女たちは総じておしゃべりであり、警戒心が弱かった。
ところが、この女性たちと会話を続けていくうちに、奇妙なことに気がついた。
彼女たちは頻繁にウクライナの政府や政治家をけなしたり、批判したりしている。女性の1人のアパートにあげてもらい、大きく破損した内部を見せてもらったときのことだ。テレビをつけると、2016年まで首相を務めたアルセニー・ヤツェニュクが映し出された。
「久しぶりにこいつをみたよ」
この部屋の持ち主の女性は罵倒に近い思いを吐き出していた。
ところが、この女性たちは自分たちに砲弾を浴びせてくる親露派の武装勢力や後ろ盾になるロシアの話になると、口調が変わるのだ。自国の首相を務めたヤツェニュクをバカにしたような態度から一変してしまう。
「ロシアのプーチン大統領についてどう思いますか」
まさに、この村に砲弾を浴びせている張本人について、私が尋ねると、女性のうちの1人は淡々と答えた。
「彼には関係がないわ。それは別の国の話だから」
この場に同席していた別の女性も似たような答えを返してきた。
「彼は自分の国で善政を敷いてきたと思うわ。私たちは自分の国の大統領にも同じように期待したいのよ」
私はすっかり、キツネにつままれたような気持ちになってしまった。ここは曲がりなりにも、ウクライナ政府が統治を続けている土地である。しかも、この女性たちは毎日のように、武装組織が放つ砲弾に脅かされている。それなのに武装勢力やロシアへの怒りや非難を口にすることはなかったのだ。
マイオルスク村の住民の発言を聞いていると、理論的な結論を導くのが難しく思えてしまう。この時点でウクライナ出張は通算10回目を数えていたが、私はこの国を理解できずに、むしろ困惑を深めるばかりだった。
それでも一つだけ、はっきりと言えることがある。
このマイオルスク村も私が取材した「2019年のウクライナ」の現実の一つということだ。
そうなのだ。「2019年のウクライナ」は幾つもの違う顔を持っており、何度も私を驚かせた。
時には軍事介入してきたロシアに虐げられ、悲しい顔をしていた。また別の時には、長年のロシアのくびきから逃れて、新たな道を歩もうとしていた。ここで紹介したマイオルスク村のように、ロシアから砲弾を浴びせられながら、親露感情を抱き続ける場所もあった。
誤解を恐れずに言えば、「2019年のウクライナ」は、日本神話に出てくる八岐大蛇のようである。胴体こそウクライナという一つの国であるが、違う場所に行き、違う人たちに会うと、それぞれの頭をのぞかせていた。
なぜ今になって「2019年のウクライナ」を取り上げるのか。
ロシアが2014年3月にウクライナ南部クリミアを併合してから、2022年2月の全面侵攻まで、おおよそ3000日の月日を要している。私がウクライナに足しげく通った2019年は、中間地点を過ぎて後半に差し掛かっていたが、全面侵攻につながる多くの兆候が見られたからだ。
この時点でロシアに仕掛けられた戦争は5年も続き、傷ついている人たちが少なくなかった。一方で実質的にロシアの支配下に収められると、諦念の気持ちに心が占められてしまう人たちも多く見た。
2019年は単なる点にはならず、一つの線となり、3000日という過去と現在をつなげていた。本書ではこのことを検証していきたい。
[書き手]大前仁
最前線の村を訪れて
2019年7月半ばのウクライナ東部の空には雲一つかかっていなかった。この時期の日本のように蒸し暑くはない。ドネツク州にあるマイオルスク村は、臨時の州都が置かれたクラマトルスクから南東の方角へ車で1時間と少しの距離にある。耳を澄ませば鳥のさえずりも聞こえてきそうで、のどかな光景が目の間に広がっている。
だが、この村はウクライナ軍がロシアの後ろ盾を得た武装勢力と対峙する最前線に置かれている。
ウクライナ軍の許可を得て、村内を歩くと、痛々しい傷痕が目に入ってきた。レンガ造りの家屋の屋根と壁は砲弾に直撃されて、大きく破損していた。半分以上の窓ガラスが割れて、ビニールで塞がれている。立派な作りの建物なのに、住人が去ってから久しいことが伝わってくる。
私はアパートの前に据えられたベンチに腰を下ろし、世間話に興じていた3人の女性と出会った。話を聞くと、全員が60代だという。旧ソ連の国では珍しくないことだが、彼女たちは総じておしゃべりであり、警戒心が弱かった。
ところが、この女性たちと会話を続けていくうちに、奇妙なことに気がついた。
彼女たちは頻繁にウクライナの政府や政治家をけなしたり、批判したりしている。女性の1人のアパートにあげてもらい、大きく破損した内部を見せてもらったときのことだ。テレビをつけると、2016年まで首相を務めたアルセニー・ヤツェニュクが映し出された。
「久しぶりにこいつをみたよ」
この部屋の持ち主の女性は罵倒に近い思いを吐き出していた。
ところが、この女性たちは自分たちに砲弾を浴びせてくる親露派の武装勢力や後ろ盾になるロシアの話になると、口調が変わるのだ。自国の首相を務めたヤツェニュクをバカにしたような態度から一変してしまう。
「ロシアのプーチン大統領についてどう思いますか」
まさに、この村に砲弾を浴びせている張本人について、私が尋ねると、女性のうちの1人は淡々と答えた。
「彼には関係がないわ。それは別の国の話だから」
この場に同席していた別の女性も似たような答えを返してきた。
「彼は自分の国で善政を敷いてきたと思うわ。私たちは自分の国の大統領にも同じように期待したいのよ」
私はすっかり、キツネにつままれたような気持ちになってしまった。ここは曲がりなりにも、ウクライナ政府が統治を続けている土地である。しかも、この女性たちは毎日のように、武装組織が放つ砲弾に脅かされている。それなのに武装勢力やロシアへの怒りや非難を口にすることはなかったのだ。
マイオルスク村の住民の発言を聞いていると、理論的な結論を導くのが難しく思えてしまう。この時点でウクライナ出張は通算10回目を数えていたが、私はこの国を理解できずに、むしろ困惑を深めるばかりだった。
それでも一つだけ、はっきりと言えることがある。
このマイオルスク村も私が取材した「2019年のウクライナ」の現実の一つということだ。
そうなのだ。「2019年のウクライナ」は幾つもの違う顔を持っており、何度も私を驚かせた。
時には軍事介入してきたロシアに虐げられ、悲しい顔をしていた。また別の時には、長年のロシアのくびきから逃れて、新たな道を歩もうとしていた。ここで紹介したマイオルスク村のように、ロシアから砲弾を浴びせられながら、親露感情を抱き続ける場所もあった。
誤解を恐れずに言えば、「2019年のウクライナ」は、日本神話に出てくる八岐大蛇のようである。胴体こそウクライナという一つの国であるが、違う場所に行き、違う人たちに会うと、それぞれの頭をのぞかせていた。
なぜ今になって「2019年のウクライナ」を取り上げるのか。
ロシアが2014年3月にウクライナ南部クリミアを併合してから、2022年2月の全面侵攻まで、おおよそ3000日の月日を要している。私がウクライナに足しげく通った2019年は、中間地点を過ぎて後半に差し掛かっていたが、全面侵攻につながる多くの兆候が見られたからだ。
この時点でロシアに仕掛けられた戦争は5年も続き、傷ついている人たちが少なくなかった。一方で実質的にロシアの支配下に収められると、諦念の気持ちに心が占められてしまう人たちも多く見た。
2019年は単なる点にはならず、一つの線となり、3000日という過去と現在をつなげていた。本書ではこのことを検証していきたい。
[書き手]大前仁
ALL REVIEWSをフォローする