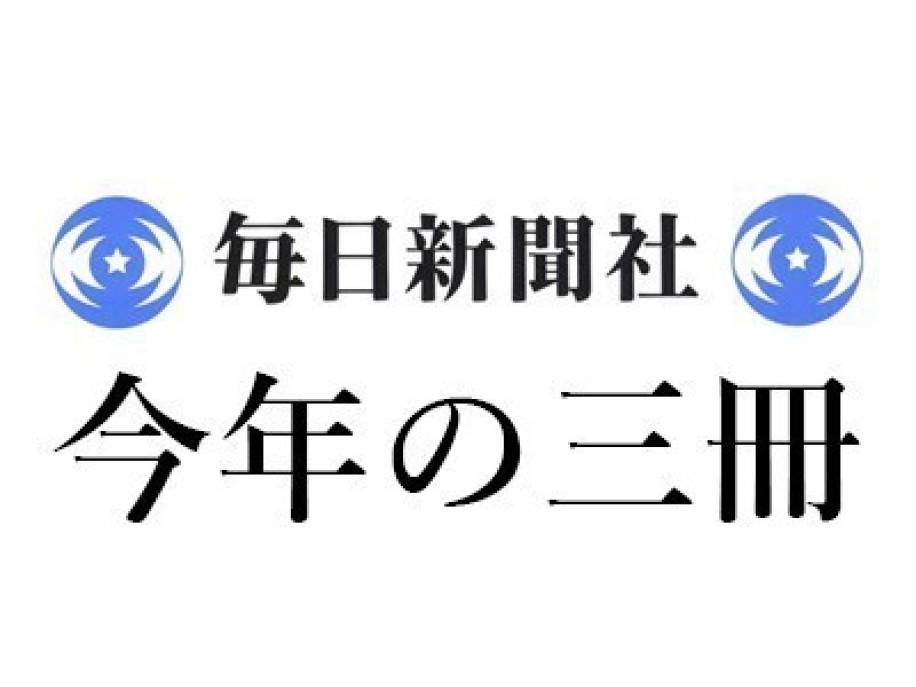書評
『火山の下』(白水社)
フローベールの『ボヴァリー夫人』やナボコフの『ロリータ』なんかが例としてわかりやすいと思うんですが、文学史上に残る傑作とされている作品の多くは、ストーリーの骨格だけ取り出してみると、単なる通俗小説にすぎなかったりいたします。で、そうした名作を映画化した場合、監督が小説のことがよくわかっていない朴念仁だったりすると、骨格だけに振り回され、まんまメロドラマにしてしまい、そのことからも小説が言語からなる芸術だということが、よお―くわかるという次第です。つまり、どう″語る″かが小説を小説たらしめる要諦であり、物語など二の次だということ。それは文学だけでなく実はジャンル小説も同じなのだけれど、この紙幅で理由を説明するのは無理なので、とりあえず、たとえばトマス・H ・クックの『沼地の記憶』あたりを読んでいただき、各自でお考えいただくとして、話は先頃ついに新訳復刊あいなったマルカム・ラウリーの『火山の下』に続いていくのでした(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は2010年頃)。
ふたつの火山が眺望できるメキシコの町を舞台に描かれる、酒浸りの元英国領事ジェフリーと、一年前に彼の元を去るも舞い戻った妻イヴォンヌのたった一日の出来事。そこに、ジェフリーの友人ラリュエルと、ジェフリーの腹違いの弟ヒューという、かつてイヴォンヌと関係を持ったことのある男二人が絡んだ、これは物語の大筋だけからみれば、『真珠夫人』などの昼ドラを制作した東海テレビが翻案しかねないベタなメロドラマです。この小説を、ジョン・ヒューストン監督の映画のほうでご存じの方もおられましょうが、わたしが読んだ感想からいえば、映像化は至難のはず。なぜか。読めば、わかります。
この物語は全十二章になっていて、最初の一章だけを一九三九年十一月二日(死者の日)に設定。第二章からは、ちょうど一年前の死者の日に起きた出来事が、視点人物を変えながら描かれていくんです。①たった一日の出来事を描いて長篇小説にするという、ジョイスの『ユリシーズ』ばりの野心。② 「意識の流れ」という語りのテクニックを活かし、視点人物の心理を繊細に描写。③死者の日(生者の祈りによって、煉獄にある死者の魂の浄めの期間が短くなるという教えから生まれた祭日)や火山、登場人物たちの前に幾度も現れる尻に焼き印が入れられた馬など、さまざまなものを象徴として効果的に投入。④ひとつの出来事を場所と視点を変えて描くことでエピソードを立体化。⑤情報を小出しにすることで、読者の心中に「?」をどんどん膨らませていき、それを一気に解消することで生まれるドラマチックな演出。②の語りのテクニックにより注目すれば、同じくたった一日を描いた『ユリシーズ』が、新聞記事や女性向けの通俗小説などさまざまなテキストを取り込む文体見本市になっていたのと比べれば穏健派とはいえ、『ボヴァリー夫人』第二部の八章、農作物や畜産物の品評が行われる共進会の場面における、ふたつの異なる声が共鳴しあって進行するポリフォニーのテクニックを効果的に使う場面があったりと、ラウリーもかなり積極果敢に攻めています。
で、こうした特徴をすべて映像化するのは無理なんであり、言語芸術の小説だからこそできる技法によって、メロドラマの大筋を文学へと昇華したのが、この『火山の下』という小説なのです。だから、読むのはたやすくありません。でも、最終章がもたらす衝撃を120%堪能できるのは、そこまで丁寧に味読した人だけ。これほど読み甲斐のある小説は、決して多くありません。読者冥利に尽きる、復刊を待った甲斐のある傑作なのです。
【旧版】
【この書評が収録されている書籍】
ふたつの火山が眺望できるメキシコの町を舞台に描かれる、酒浸りの元英国領事ジェフリーと、一年前に彼の元を去るも舞い戻った妻イヴォンヌのたった一日の出来事。そこに、ジェフリーの友人ラリュエルと、ジェフリーの腹違いの弟ヒューという、かつてイヴォンヌと関係を持ったことのある男二人が絡んだ、これは物語の大筋だけからみれば、『真珠夫人』などの昼ドラを制作した東海テレビが翻案しかねないベタなメロドラマです。この小説を、ジョン・ヒューストン監督の映画のほうでご存じの方もおられましょうが、わたしが読んだ感想からいえば、映像化は至難のはず。なぜか。読めば、わかります。
この物語は全十二章になっていて、最初の一章だけを一九三九年十一月二日(死者の日)に設定。第二章からは、ちょうど一年前の死者の日に起きた出来事が、視点人物を変えながら描かれていくんです。①たった一日の出来事を描いて長篇小説にするという、ジョイスの『ユリシーズ』ばりの野心。② 「意識の流れ」という語りのテクニックを活かし、視点人物の心理を繊細に描写。③死者の日(生者の祈りによって、煉獄にある死者の魂の浄めの期間が短くなるという教えから生まれた祭日)や火山、登場人物たちの前に幾度も現れる尻に焼き印が入れられた馬など、さまざまなものを象徴として効果的に投入。④ひとつの出来事を場所と視点を変えて描くことでエピソードを立体化。⑤情報を小出しにすることで、読者の心中に「?」をどんどん膨らませていき、それを一気に解消することで生まれるドラマチックな演出。②の語りのテクニックにより注目すれば、同じくたった一日を描いた『ユリシーズ』が、新聞記事や女性向けの通俗小説などさまざまなテキストを取り込む文体見本市になっていたのと比べれば穏健派とはいえ、『ボヴァリー夫人』第二部の八章、農作物や畜産物の品評が行われる共進会の場面における、ふたつの異なる声が共鳴しあって進行するポリフォニーのテクニックを効果的に使う場面があったりと、ラウリーもかなり積極果敢に攻めています。
で、こうした特徴をすべて映像化するのは無理なんであり、言語芸術の小説だからこそできる技法によって、メロドラマの大筋を文学へと昇華したのが、この『火山の下』という小説なのです。だから、読むのはたやすくありません。でも、最終章がもたらす衝撃を120%堪能できるのは、そこまで丁寧に味読した人だけ。これほど読み甲斐のある小説は、決して多くありません。読者冥利に尽きる、復刊を待った甲斐のある傑作なのです。
【旧版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする