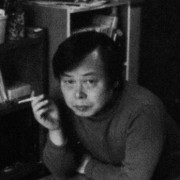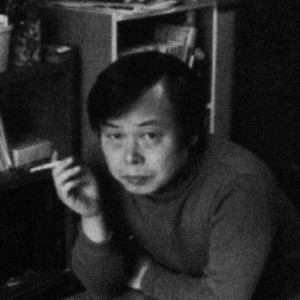書評
『ライレッセの大絵画本と近世日本洋風画家』(雄山閣)
読めなかった絵画論
ニューヨークのメトロポリタン美術館に、モデルが久しく不明だったレンブラント作の肖像画がある。モデルがレンブラントの周辺にいたアムステルダムの画家、ヘラルド・ドゥ・ライレッセ(一六四〇ー一七〇九年)と判明したのは、一九一三年のことだった。一方、天明七年に戯作者森島中良が編んだ『紅毛雑話』に、「『シキルデルブック』に載る一二図を模写して、好事の人の看に呈す」とあって、一連の模写図が描かれている。「シキルデルブック」とは、右のヘラルド・ドゥ・ライレッセが全盲となった晩年の一七〇七年に、若き日イタリア遊学中に親しんだチェーザレ・リーパの『イコノロギア』(一五九三年、ローマ)を範として、オランダに美術アカデミーを創設すべく編んだ、寓意象徴表現の集大成である。
このいわゆる「ライレッセの大絵画本」が、長崎出島を通じて天明の洋風画家、平賀源内、佐竹曙山、小田野直武、司馬江漢、森島中良等に伝わった。これら江戸洋風画家がそこから何を得、何を逸したかを、じかに『大絵画本』の原典について分析したのが本書である。
ライレッセの『大絵画本』は、チェーザレ・リーパの『イコノロギア』の寓意表現をオランダ・アカデミーのために再体系化せんとしたものだが、一方、写実的陰影法の摂取に余念のなかった江戸の洋風画家には、語学の未熟のためもあって、原典の意図が理解されなかった。洋風画家たちは寓意表現の体系である『大絵画本』をもっぱら画法書として受け取ったために、決定的な誤読が生じ、そのため「ライレッセが『大絵画本』で唱えた西洋美術の美や理想の問題を知るには森鴎外を待たねばならなかった」。『解体新書』の翻訳の場合と同様、サイレントだった『大絵画本』は、天明の画家たちに翻訳不能の△印を付されたのである。これ以後寛政の異学の禁から明治まで、著者によれば洋画研究は大空位時代に入る。
しかし、目と手は語学力の壁を越えて隠されたイデアを読み解くことがある。たとえば化政期の北斎漫画では、海波の図像は形象言語としてより正確に読み解かれたのではないか。ライレッセの新興ブルジョア的風貌や、森島中良がその一員であった桂川家周辺の学風についての叙述は、東西文化の創造現場のいきいきとした臨場感を伝えて読みごたえがある。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1983年5月16日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする