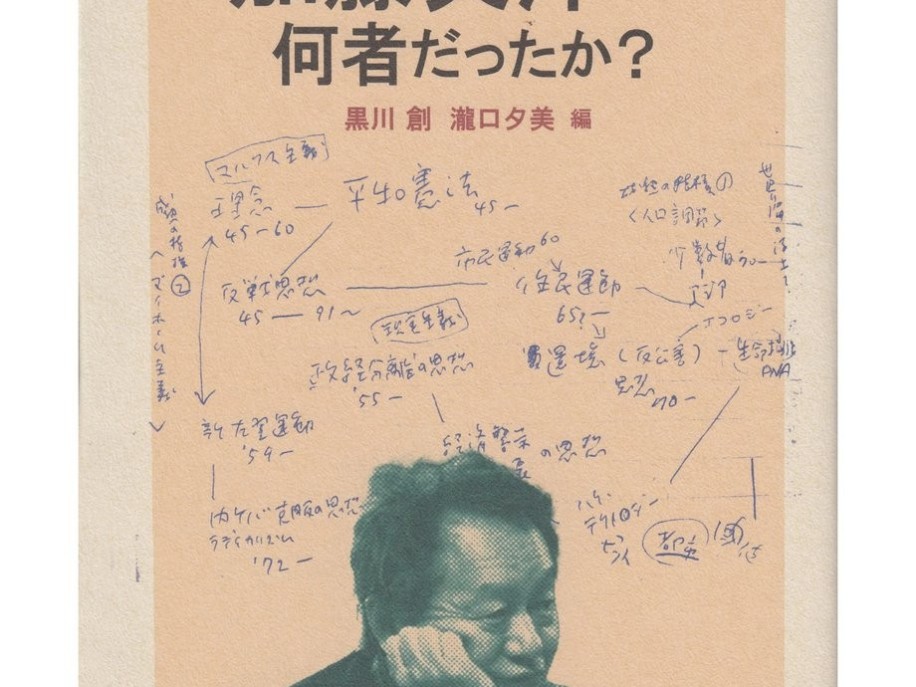書評
『言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか』(中央公論新社)
本書を書店で見かけ、パッと手に取り、グイグイ読んだら、いくつもハッとして、読み終えてポカーンとしている。
こんな感想を読んで、この本を前向きに読んだらしいと伝わるのはなぜなのか。「発見がたくさんあった」などと書くより、先の感想のほうが思いが届くのはなぜなのか。
『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(今井むつみ、秋田喜美著・中公新書・1056円)で主に議論されているのがオノマトペの存在。子どもは車を見て、「ブーブー」と言う。「プープー」だとオナラだ。では、それを「ブーブー」だと捉えた理由はどこにあるのか。「プープー」では間違いなのか。
「少なくとも最初のことばの一群は身体に『接地』していなければならない」とする記号接地問題を入り口に、言語の本質を探りにいく。曲線的な図形と、尖った線が重なった図形を並べ、どちらが「マルマ」で「タケテ」かと問うと、多くの話者が「マルマ=曲線」「タケテ=尖った線」だと判断するという。「完全に万国共通な音と意味のつながりというのは、今日に至るまで報告がない」というのに。
オノマトペでは、「否定や分配法則、抽象概念」などの論理的関係を表すことはできない。「具体的に知覚できるもの」は表現できても、たとえば「友情」や「正義」などの抽象概念は難しい。私と友人にある友情を言い表したいとする。君と話していると、ほくほくする。違う。らんらんする。違う。見当たらない。
「進化の過程でなぜ言語はオノマトペから離れなければならなかったのか、どのように離れていったのか」との問いへ進んでいく。言葉を習得しながら、私たちは知識を膨らませてきた。仮説を形成し、極めて複雑なものを捉え、伝えていくことを覚える。
なぜ人間だけが言語を持つのかという問いは、解決するどころか膨らんでいく。残念ながら、「ブーブー」を「車」と呼ぶように切り替えた瞬間を覚えていない。その時、自分に何があったのか。本書は、自分を遡る旅にもなる。
こんな感想を読んで、この本を前向きに読んだらしいと伝わるのはなぜなのか。「発見がたくさんあった」などと書くより、先の感想のほうが思いが届くのはなぜなのか。
『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(今井むつみ、秋田喜美著・中公新書・1056円)で主に議論されているのがオノマトペの存在。子どもは車を見て、「ブーブー」と言う。「プープー」だとオナラだ。では、それを「ブーブー」だと捉えた理由はどこにあるのか。「プープー」では間違いなのか。
「少なくとも最初のことばの一群は身体に『接地』していなければならない」とする記号接地問題を入り口に、言語の本質を探りにいく。曲線的な図形と、尖った線が重なった図形を並べ、どちらが「マルマ」で「タケテ」かと問うと、多くの話者が「マルマ=曲線」「タケテ=尖った線」だと判断するという。「完全に万国共通な音と意味のつながりというのは、今日に至るまで報告がない」というのに。
オノマトペでは、「否定や分配法則、抽象概念」などの論理的関係を表すことはできない。「具体的に知覚できるもの」は表現できても、たとえば「友情」や「正義」などの抽象概念は難しい。私と友人にある友情を言い表したいとする。君と話していると、ほくほくする。違う。らんらんする。違う。見当たらない。
「進化の過程でなぜ言語はオノマトペから離れなければならなかったのか、どのように離れていったのか」との問いへ進んでいく。言葉を習得しながら、私たちは知識を膨らませてきた。仮説を形成し、極めて複雑なものを捉え、伝えていくことを覚える。
なぜ人間だけが言語を持つのかという問いは、解決するどころか膨らんでいく。残念ながら、「ブーブー」を「車」と呼ぶように切り替えた瞬間を覚えていない。その時、自分に何があったのか。本書は、自分を遡る旅にもなる。
ALL REVIEWSをフォローする