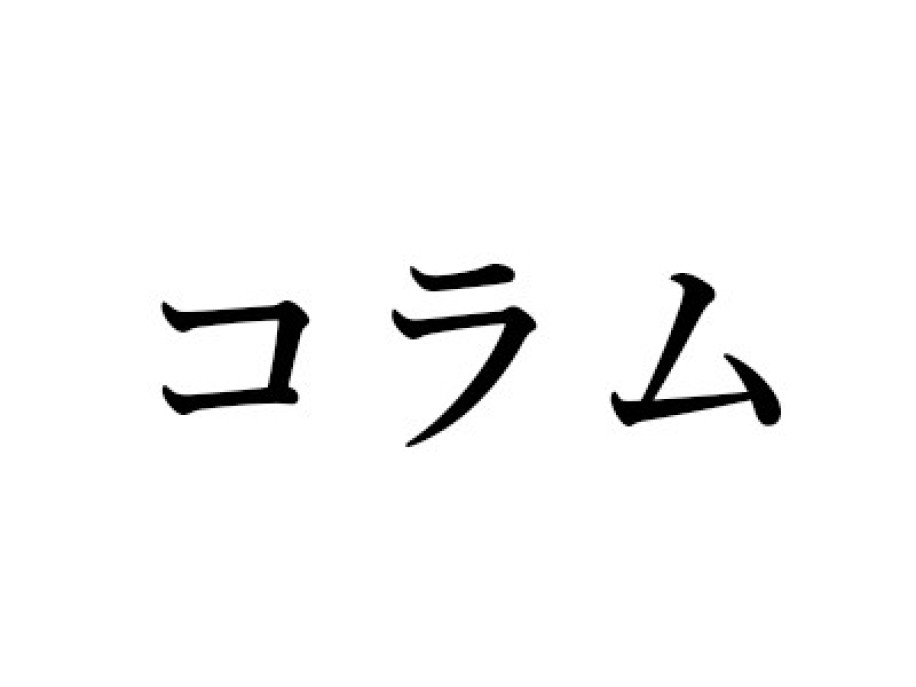書評
『西洋書物史への扉』(岩波書店)
粘土板からパピルスや羊皮紙を経て紙へ、手書きから印刷へと、西洋の書物は変化してきた。ただし、その道筋は必ずしも一直線でなかったことを本書は教えてくれる。
たとえば、巻子本(巻きもの)から冊子本(綴じた本)へという形態の変化。冊子本が登場しても、ユダヤ教ではしばらく巻子本を使いつづけたという。一方、ユダヤ教から分かれて発達したキリスト教は冊子本を用いた。冊子本は新しさの象徴だったのかもしれない。
15世紀にグーテンベルクが活版印刷術を発明するまで、書物は職人が手で書き写すものだった。印刷本がたちまち書写本を駆逐する……かと思いきや、なんと印刷本そっくりに手書きした本もあるという。初期の印刷本は書写本を再現しようとしていたのだから、ことは複雑だ。
グーテンベルクの聖書は、現代になってとてつもない値段がついた(1987年に丸善がオークションで落札したときは約7億8千万円)。著者のはたらきもあって慶應義塾図書館が所蔵することになったその本は、デジタル化され、誰でも自宅の端末で見ることができる。これは本の未来を示唆しているのだろうか。
たとえば、巻子本(巻きもの)から冊子本(綴じた本)へという形態の変化。冊子本が登場しても、ユダヤ教ではしばらく巻子本を使いつづけたという。一方、ユダヤ教から分かれて発達したキリスト教は冊子本を用いた。冊子本は新しさの象徴だったのかもしれない。
15世紀にグーテンベルクが活版印刷術を発明するまで、書物は職人が手で書き写すものだった。印刷本がたちまち書写本を駆逐する……かと思いきや、なんと印刷本そっくりに手書きした本もあるという。初期の印刷本は書写本を再現しようとしていたのだから、ことは複雑だ。
グーテンベルクの聖書は、現代になってとてつもない値段がついた(1987年に丸善がオークションで落札したときは約7億8千万円)。著者のはたらきもあって慶應義塾図書館が所蔵することになったその本は、デジタル化され、誰でも自宅の端末で見ることができる。これは本の未来を示唆しているのだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする