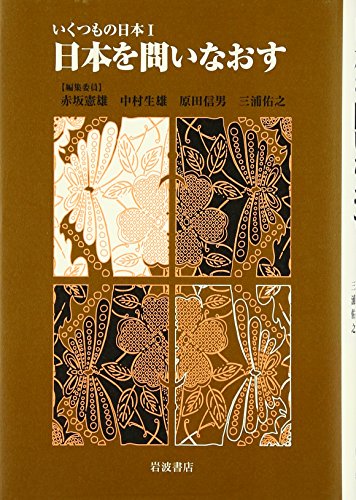書評
『中国の歴史7 中国思想と宗教の奔流 宋朝』(講談社)
「文弱」の先入観覆した歴史家の内省
中国の宋王朝は、秦・漢帝国や唐王朝と比較してあまり馴染みがないかもしれない。華麗な古代文明を開いた王朝として記憶されている後者に対し、前者については、日本の古代律令国家に比較して日本の中世社会への馴染みが薄いように、関心は大きくない。しかしこの宋の社会が中国社会にあたえた影響は、思想・文化・技術、政治制度から社会習慣に至るまで、すこぶる大きなものがあった。なかでも思想と宗教とは多大な影響をあたえた。
本書は、その宋の歴史三百年を叙述した歴史書であり、タイトルに「中国思想と宗教の奔流」とあるごとく、思想・宗教の側面を重視し描いている。
そこからは政治や経済の叙述を中心とした、これまでのものとは違った新鮮さがうかがえる。とはいえ宋王朝は五代の乱離を受けて成立した王朝であり、また北方の遼・金の圧迫を受け、ついに南遷し、最後にはモンゴルにより滅ぼされた王朝であれば、それに触れずしては済まされない。
しかも王朝の政治では、科挙制度に基づいて、官僚となった士大夫が皇帝を奉戴して行う文治政治が行われ、その士大夫の手によって儒教の再興と土着化が進められたのであれば、政治と宗教・思想とは分かちがたい関係にあった。
したがって本書は最初に宋朝誕生の経緯を述べ、第二章から第四章までを政治の動きにあてた後に、第五・六・七章で宗教・思想を扱い、最後に残された文化や社会の動きに触れている。十章からなり、それぞれ五節からなるという、易の筮竹(ぜいちく)の数五十本に因む構成をとっているのである。
読むうちに、思い知らされたのは、宋代の人々の徹底した思考である。「水も漏らさぬ緻密な制度設計」からなる王安石の改革に始まり、万物の成立と存在を理と気の二元論で説明し、そこから修養して自己の人格を高め、その成果を政治の場にまで及ぼそうとした朱子の儒学、さらには天文地理や医学・料理、印刷技術などの科学技術全般にわたって、宋代人は徹底して追究してゆく。
確かにそれは日本の江戸時代に比せられる近世社会の到来を物語っているかもしれない。江戸時代には朱子学が広く受け入れられ、様々な科学技術を育んでいる。
しかし他方で、「宗教の奔流」という面、禅宗や様々な祭祀が広まり、宗族のような、日本の家と似た社会制度の広がりなどを考えると、それは同じ時代の、日本の中世社会とも似通っている。宋代が中世なのか近世なのかは、どこを見るかによって違ってくるようだ。
それはさておき、さらに驚嘆させられたのが、激しい党派争いである。科挙により官僚層が形成されるなかで、王安石が出て改革を断行するとともに新法派が形成され、それに対抗する旧法派との間に争いが始まって、以後、党派争いは激化し、大きな混乱を常に招くことになった。
それがまた様々な副産物を生む。旧法党の中心人物司馬光が、洛陽に引退させられていた間に歴史書『資治通鑑』を著しているなどはその一つであった。
しかしこのように歴史書が党派争いの産物であれば、その著作の評価には少なからぬ問題が生じてくる。『資治通鑑』にはまだ抑制された筆致があったが、以後の歴史書を探る際には、著者の党派性をいかにはぎ取って事実に迫るかが重要となる。
著者が行ったのはまさにそうした作業である。朱子学者たちによって語られてきた宋代のイメージ、しかしそれとは裏返しの、中国蔑視につながる「文弱な士大夫たちの精神文化が中国の発展を妨げてきた」といった評価を、覆そうと試みている。
そのために、宋の歴史をその時代の文脈でいかに語るのか、という試みを徹底して行っている。しかしそれだけで終わるのではなく、身近な例や様々な例との比較を通じながら理解するようにも試みている。
たとえば、「朱子学の普及は印刷技術無しに考えられない。“グーテンベルク無くして宗教改革無し”をもじれば、“木版印刷無くして朱子学無し”なのである」といった評価や理解である。
その理解には多少とも違和感をもつ部分はあるが、著者の「中国思想の専門家」としてのスタンスが随所に見えてきて、面白い。
歴史を探ってゆくと、今、当然のように語られていることが、実は瓢箪から駒のような形で始まっていることや、相手の党派への対抗上から探し出されてきたようなものが実に多くあることが、本書によって改めて実感させられた。
だから歴史は面白いのだが、それだけに怖い。著者は最後に「実像を探ると称しながら、その虚像をまた一つ描き出したにすぎないことを恐れる」と語っているが、こうした内省こそが歴史家には求められている。優れた歴史書たる由縁である。
ALL REVIEWSをフォローする