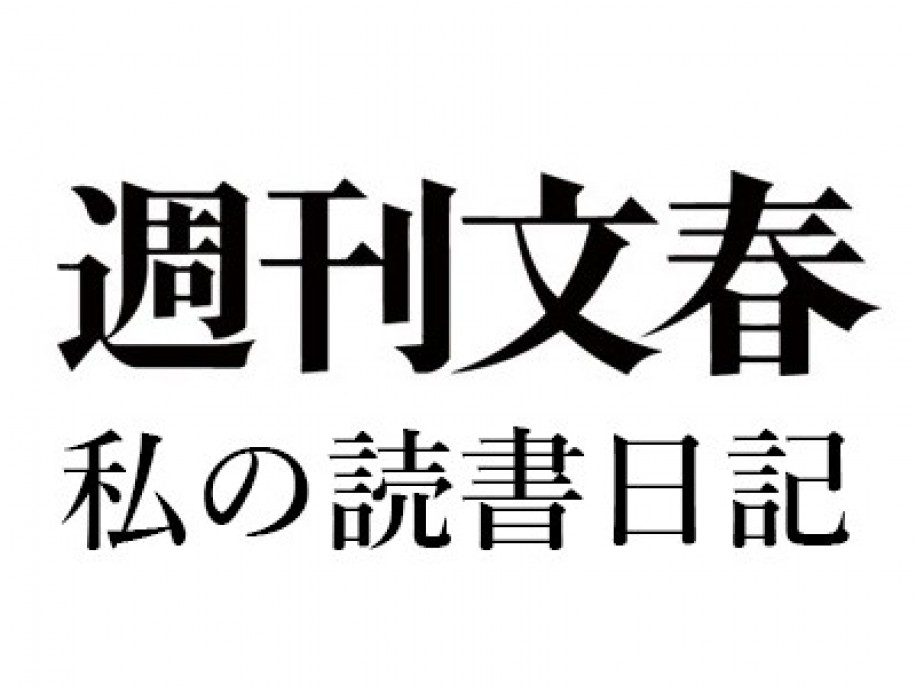書評
『力と交換様式』(岩波書店)
資本制の彼方に「交換様式D」構想
わが国の思想界を牽引する柄谷行人氏の新著『力と交換様式』。二○一○年の『世界史の構造』を発展させた決定版の登場だ。マルクス主義は、原始共産制/古代奴隷制/中世封建制/近代資本制、に歴史を区分した。生産様式に基づく区分だ。だが交換様式に注目すると見え方が変わる。
交換様式とは、人びとが財や服従/保護を交換すること。交換様式Aは、共同体での互酬的な財の交換。Bは税など垂直的な収奪と保護。Cは市場での水平の交換。歴史はAを壊しBやCを発展させた。その到達点が資本主義だ。
でもその先に、交換様式Dがある。資本主義(B+C)が行き詰まると、≪Aの高次元での回復≫が起こるに違いないという。
さて、力とは何か。力は霊のような強力な働きのこと。モースは『贈与論』で、マオリ族は≪物に付着した霊≫が≪贈与交換を強いている≫と信じているとした。これは交換様式Aの場合だが、Bでは王が神聖視され、Cでは貨幣が物神となる。どんなに意識してもその力を逃れるのは不可能だ。
マルクス主義は生産様式が、奴隷制/封建制/資本制、の段階を踏むとした。交換様式はA/B/Cが入り混じる。こうして読み解く世界史はユニークで興味深い。たとえば古代文明の中心地では専制的官僚制(交換様式B)が発達した。それを外れたユダヤ民族にはA~Cが入り混じった神ヤハウェが生まれた。海を隔てた周辺のギリシャは氏族制(A)を残し、民主制や哲学が育った。ゲルマンも部族制(A)を残し封建制で商業(C)が発展し、国家は未発達だった。いっぽうビザンチンは専制的(B)で、それがロシアに伝わった。交換様式はA↓B↓Cの順に進むと限らず、遅れた地域がかえって発展したりする。だから中心の中国はBの官僚制でも、周辺の日本(Aが残る)は幕藩制だったのか、と理解が深まる。
柄谷氏は交換様式を『資本論』から着想した。その第一章は商品が貨幣(物神)に変わる分析だ。物神=力だ。『資本論』は資本が物神として経済を支配する話。だがマルクスは第一巻で筆を止め、モーガンの『古代社会』を読みふけった。資本主義の彼方に、原初の交換様式Aが高次元で復帰するさまを思い描こうとした。その路線を継承したカウツキーは、議会で多数をえて資本制を改造する社会民主主義を採用した。だがロシア革命を成功させたレーニンやスターリンは専制的官僚制の党を築き、正統マルクス主義を称した。共産党独裁がやがて国家を死滅させるか。そんなはずはない。交換様式の「力」は、人間の意志や理性には従わないのだから。
本書の主題は交換様式D。それは、A~Cの絡まりを追う本書の全体に予感されている。交換様式BやCの中にAが潜り込み、多様な社会形態が生み出されるさま。それはDの可能性でもある。≪Dは、Aとは違って、人間が願望し…実現される…ものではない。…いわば“向こうから”来る≫。意図して≪国家や資本…BやCを揚棄することはできな≫くても、資本制が永続するわけではない。資本制の空虚の先に、人間らしい交流を実現する新しい世界が必ずやって来る。それを交換様式から読み解いて確信し、希望をもって生きよう。厳しい覚悟の書である。
ALL REVIEWSをフォローする