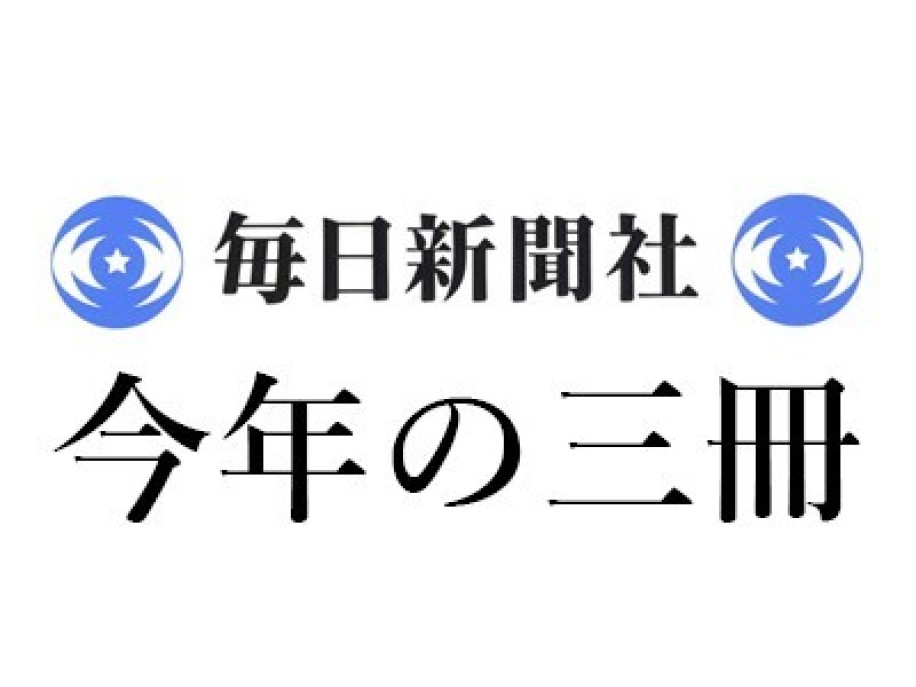書評
『殉教の日本―近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック―』(名古屋大学出版会)
聖人化先駆け、西欧で受容の背景
本書の題名から連想するのは、遠藤周作の小説『沈黙』やM・スコセッシ監督の映画ではないだろうか。イエズス会の宣教師が信者の迫害に直面し、一方では命を落とし殉教者になり、他方では棄教者の道を歩む場合があった。一神教文明の世界で育った人々は論理には絶対といえるほど自信をもっているという。だが、この作品では長崎奉行の説得力が勝っており、欧米人は愕然とするらしい。ところで、「かくれキリシタン」として名高い戦国末期・江戸初期のキリスト教信者をめぐって、世界はどう見ていたのだろうか。近世の日本は「殉教」の聖地であるとともに暴虐の国として理解されていたという。
もちろん、近世における殉教の記述は日本に限られるわけではない。北米・中南米をはじめ布教活動がなされた地でも報告されている。ところが、日本の殉教のみが、文書・図像・演劇などを通して広く伝えられ、ついには「大きな物語」として成立したという。そうであれば、布教政策や禁令活動の通史ではなく、教会関係者の記録を「逆なでに」読み、「起こったこと」が歴史化された文脈を解き明かすことが本書の焦点となる。
日本では男女とも読み書き能力があることに感銘したF・ザビエルの方針で、活版印刷機が導入され、『信仰の象徴入門』の日本語版が出された。だが、原著の意図は大幅に改訂され、殉教のテーマを強調した聖人(サントス)の伝記であった。日本への宣教がなされた十六世紀には、ヨーロッパでは宗教戦争のせいで「殉教」の意味内容が揺らぎつづけていた。そのために、列福・列聖の判断が変容しがちであった。
そこで西欧における日本の殉教言説に決定的な影響をおよぼした長崎二十六殉教者の列福の過程が、裁判文書を用いてたどられる。古代以来の聖人崇拝を権威づけるために列福・列聖制度が発展し、一六〇〇年前後に教皇庁は改革に着手し、制度が整うなかで日本の殉教者が初めて列福されたという。その意味でも、本書は『日本の殉教』ではなく『殉教の日本』なのである。
日本で処刑されたキリスト教徒が他に先駆けて聖人化されるとともに、それを迫害する側の権力も探究される。例えば豊臣秀吉は「タイコーサマ」なる呼称で暴君の象徴と見なされたのだ。
地球規模の宣教活動がくりひろげられるなかで、殉教者が公式に輩出すれば、その聖性が特定の地域と結びつく。そこで、聖遺物が希求され、それ自体が殉教者の聖性を示唆する物的証拠として重要な役割を担った。日本の殉教者のモノとして信仰される物語などの記憶がなければならないのだ。殉教者の図像があればなおさらであり、壮大な物語として紡がれる。長崎二十六殉教者のうち二十三人の十字架刑(磔刑)図はその白眉であり、日本の殉教の図像化は、残酷な劇場であるかのように、受容されやすかったという。
さらに、日本の殉教はヨーロッパ各地で演劇化され、その「見る」行為により、宗教的なカタルシスを得られる教化手段にもなったのだ。
このようにして、多様な殉教伝・磔刑図像・残酷劇を通じて、きわめて独特な日本像が創出された。そのプロセスを解明しつつ、キリスト教史における宣教のレトリックを問い直す作業は、東西の歴史をつなぐ試みとして、ことさら注目されてよいだろう。
ALL REVIEWSをフォローする