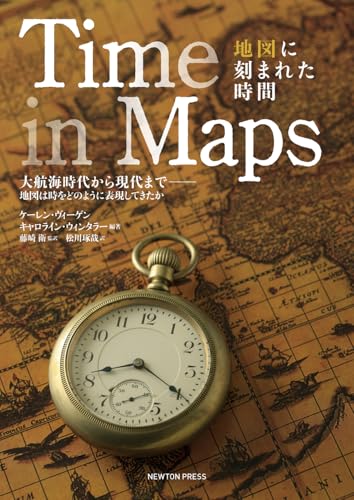書評
『スパルタを夢見た第三帝国 二〇世紀ドイツの人文主義』(講談社)
国家と学問の関係を問い直す
アテネから西南方面にバスで3時間半ほど行くとスパルタに着く。ひなびた町であり、これがあの古代ギリシアの二大強国の一つかと目を疑いたくなる。文化活動を軽んじ、ひたすら軍事訓練に心したスパルタだったが、その栄光は同時代の人々でなければ感じられないものだったのだろうか。オリーブ畑に囲まれたスパルタ遺跡に向かう途中で大きなレオニダス王の立像を仰ぎ見る。紀元前四八〇年、ペルシア軍との戦いで三〇〇人の兵士を率いて玉砕したスパルタ王を記念したもの。いくども映画化され、印象深い。
ところで、一九四三年のナチスの国際宣伝雑誌『シグナル』の冒頭には、この立像の原像とおぼしき写真が「ヨーロッパを守る盾」として載せられている。ドイツ兵を鼓舞するためにスパルタ兵の奮戦を想起させようとしたのだろう。
第一次大戦後、民主主義にもとづくヴァイマル共和国が成立した。しかし、多額の賠償金、大インフレ、貧富差の増大、中産階級の貧困化、小党分立による安定政権の欠如、政治的テロなどがうずまき、共和国への不満と戦勝国への雪辱感が強まるばかりだった。
このような経済的停滞と政治的混乱とともに爛熟した文化が見られ、民主主義・資本主義を装う内外の敵には、アテナイ民主主義が投影されていた。そもそも、18世紀後期以降のドイツ人は古代ギリシアに大きな愛着を寄せてきた。しかも、このような古典主義への関心は、主にドイツとアテナイとが親縁にして類似しているという意識にもとづくものだった。
しかしながら、ヴァイマル期の混乱と停滞は社会や国家を改造する機運を創り出し、ナチスが登場する。その改造の梃子となるのがスパルタを規範とする施策であった。この時期に生まれた作家は、第三帝国下の学校での経験を回顧する。「私は我々に紹介された理想、つまり古代のスパルタ・における子供の教育のことを、はっきりと覚えている。この理想は、国粋主義を奉じる教師によって感激と共に我々の眼前に繰り広げられた。例は巧みに選ばれた。つまり一方で小さいスパルタは、経済的には強力だが根本において腐敗している(アテナイなど)民主主義(国家)に囲まれ、軍事教育を受けた自らの若者の力だけを頼りにした。他方で(第一次世界大戦での)敗北の屈辱に苦しみ敵に囲まれた戦後のドイツは、(スパルタ市民と)似た、死を軽蔑する若者を教育した場合のみ、この恥辱を雪(すす)ぐことができた」
これと同時に、古典古代の教養を軸としてきた人文主義は、岐路に立たされた。それまで「人間と文化を介してドイツとアテナイの親縁性」が強調されてきたのに、第三帝国のスパルタ受容をきっかけに「人種を介したゲルマン人とスパルタ人の親縁性」が重んじられるようになったのだ。ナチ政権の理想に人文主義者たちはどう対峙すべきか、決断を迫られた。
研究に没頭して傍観したW・イェーガー、人文主義保護のためにナチスに協調したR・ハルダー、学問と大学の自由のために抵抗したK・V・フリッツ。本書の大半は、これらの人文主義研究者の見解を整理しながら、国家と学問の関係を問い直すことに割かれている。このような意欲ある議論がなされる背景に、なによりも社会の底流に浮沈する人々の夢があったことは今さらながら驚きである。
ALL REVIEWSをフォローする