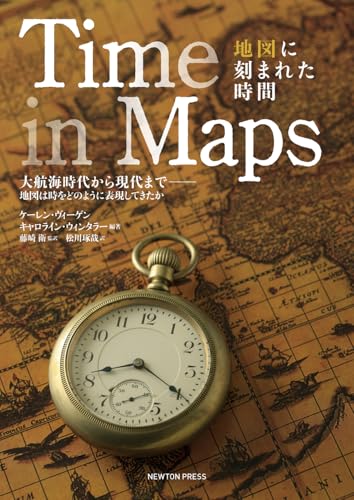書評
『パピルスのなかの永遠: 書物の歴史の物語』(作品社)
書き 伝え 写し 残す 人間の執念をたどる
個人として歴史にその名を刻みたいなら、自分で多くを書き残すか、他人が記録したくなるような事績を行うことだ、とはしばしば言われる。そもそも人間がおしゃべりをして噂話に興じるようになってから認知能力が高まったというが、せいぜい数万年前にすぎない。文字が開発されて記録されるようになってから、文明が生まれたが、それも六〇〇〇年前のこと。さらに、数多くの文字数がある楔形文字やヒエログリフから、三〇足らずの文字で書けるアルファベットが生まれて三〇〇〇年が経ったにすぎない。世界最古の古典ともいえる『イリアス』『オデュッセイア』の吟遊詩人ホメロスは文字などまったく知らなかった。やがて、声の世界が捨てられ、流れ、しなやかさ、即興の自由なども失われる。それでも、自分の教えが書きとめられることを嫌がったソクラテスと同様に、ピュタゴラス、ディオゲネス、さらに仏陀、イエスも声を好んだ。だが、彼らの弟子たちが師の文言を記録したおかげで、偉人の足跡が残ることになり、そこでは書物が決定的な媒介物となった。
アレクサンドロス大王の死後数十年も経たない時代に、馬に乗った怪しげな男たちが地中海沿岸の街道を進んでいた。道中にはびこる追いはぎや山賊の襲撃を恐れながら、エジプトのファラオから莫大な金額を委ねられて、獲物を追跡するのだった。驚くべきことに、彼らの探す獲物とはパピルスに記された書物であり、世の最高権力者が命をかけても世界中のすべての書物をアレクサンドリア大図書館に集めようとしていたのだ。
ことあるごとにファラオは、軍隊の行進を眺めるかのように、蔵書の巻物を眺めにやって来た。図書館長からすでに二十数万巻があり、「目下私は五〇万を満たすため邁進しております」と答えられると誇らし気だったという。
フェニキア人の開発したアルファベットは子音のみから成り立っていたが、ギリシア人が母音を加味することによって、曖昧さがなくなった。そのためにヨーロッパ中に広まり、読むことが身近になったという。
さかのぼれば、前四世紀のアリストテレスは「知られる限り初めて、書物を収集した者」であり、途方もない金額で他の哲学者の蔵書を買いあげたらしい。それは、ヨーロッパが書物への熱狂に飲み込まれる発端であった。
ところで、ウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』はショーン・コネリー主演の映画にもなって広く親しまれている。このなかで修道院の写字室の場面があり、そこで写されていたテキストの一つがアリストテレスの『詩学』の失われた(?)第二部「喜劇論」であったと想定される。連続殺人の真犯人である修道僧は、古代最大の哲学者に「喜劇論」などあってはならず、笑いに関する論考は一冊残らず消滅させるのが修道院の務めだというのが真犯人らの意図するところであった。もちろん、この部分は作家エーコの創作であるが、パピルス文書が羊皮紙に写し書き記されていく場合に起こりえることだっただろう。
それはともかく、忘却、排他主義、言語の壁は世の常である。しかし、アレクサンドリア大図書館のおかげで、紙の祖国をもつ人間は奇妙な生物に変貌したのだ。
後に大帝国になるローマは、起源をたどれば、評判の悪い都市だった。犯罪者や逃亡者のならず者集団であり、あげくの果てに集団婦女暴行までしてしまう。しかし、イタリアの征服者となり、西地中海に覇を唱えるカルタゴを斥(しりぞ)けた前三世紀末には、ローマもいっぱしの文化をおびた社会になっていた。
ローマ人の社会では書物に親しむには縁故が必要だった。なによりも誰を知っているかが問題であり、いつも友情と複写できる人とのつながりが大切であった。友人に借りて、自分の奴隷や書字生に複写させるのである。
ローマ社会では、書き方を教えたり、写しを作成したり、文芸作品の製造のあらゆる面に、奴隷が参加していた。しかし、ポンペイの数多くの落書きから推測されるように、ローマ人の読み書き能力は高かったという。文芸を楽しむ豊かな精神生活と報酬をもたらす教育とは別ものとされており、建築家、医者、教師のような職業は下層民の仕事として軽蔑されていた。
そのせいか、学識のあるギリシア人奴隷の多さに比べて、後世の文明における強いられた非識字化はあまりにも対照的である。たとえば、南北戦争の敗北まで、アメリカ南部の諸州では、奴隷が読み書きを学ぶことは、奴隷制を危うくするものとして違法であったという。
ともかく、ローマ世界はグローバル化されており、帝国の街道を伝って、大量の書物が流通した。富裕な読書人の家庭では、書物をどこに置けばいいかが悩みの種だったという。それが古代末期には大量絶滅のごとく消滅してしまう。異邦人の侵略という数世紀の激震が永遠と信じられたものの脆さを晒したのだ。
ALL REVIEWSをフォローする