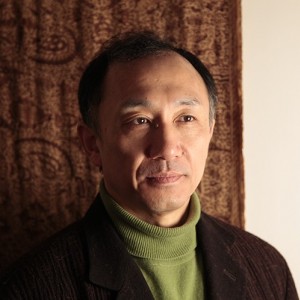書評
『昭和の東京郊外 住宅開発秘史』(光文社)
戦後スプロール、夢の跡を探訪
2021年2月、市井の郊外研究者である著者のもとに都市・建築に特化した古書店からカタログが届く。著者の目に止まったのが140枚ほどの「郊外住宅地の売り出しチラシ」。昭和30年代、神奈川県、横浜・川崎・鎌倉のものだ。終戦直後の住宅不足は甚だしく、昭和30年代になっても284万戸が未充足だった。高度成長期、東京周辺の各県ではホタルやヤマユリが溢れた山林や畑が急速に住宅地に変わり、「東京の郊外」として通勤圏に組み込まれた。土地成金が大量発生、取引には夢と悪が混乱のうちに大発生したはずだ。
チラシの主は同潤会系でも公営でも電鉄系でもない、純粋民間中小住宅分譲会社だった。「雑草がはびこる」が原義である「スプロール」の全体像に迫るチャンス、と埼玉、千葉、三多摩などのチラシも購入、別荘地である鎌倉は除いて著者は実際に足を運んだ。上大岡、旭区、瀬谷区、保土ケ谷区から日吉、新百合ケ丘、多摩美、岡上、大宮・浦和といった各地区で、巻末にチラシ内容一覧がある。ラフなデータだけに、凸凹具合が想像力を刺激する。本書は庶民が土地を持った戦後スプロールの夢の跡を、足で辿(たど)った探訪記である。
売買されたのは土地そのもので、現地には万国旗がたなびきスピーカーの大音量で流行歌が流れた。「松濤台、五島遊園台、静風台」等、販促用に架空の地名が掲げられ、大半は所在地も記載されない。詐欺まがいも多く、「東武地下鉄越谷駅前繁華街商住地、徒歩5分」と謳う物件は、客が自動車で連れて行かれたのは18キロ先、徒歩なら3時間45分はかかった。昭和41年にはついに旧建設省や公正取引委員会が「宅地分譲抜き打ち調査」に乗り出す騒ぎとなっている。
すべての土地が誇大広告で取引されたわけではない。非電鉄系最大の分譲会社「大島土地」は「土地の銀行」を謳い、1000坪以上の土地を預かり「1区画18坪」などに分割、小口分譲を行う技術を誇った。相模原市や国立市、大和市の中央林間で活動、社長は首都機能の移転までぶち上げている。
たんに土地を細分化しただけではない。「個」の集合体である分譲地を愛着の持てる「まち」として成立させるため、住環境がデザインされている。軒を低くし竹垣と植栽の高さも抑えて、歩いて親しみを持てるヒューマンスケールの街並みが残されている。プレハブ住宅を容積率一杯に並べ、隣との連携なく孤立させてしまっている現在の住宅産業とは一線を画す。
さらに著者が発見したのが、同潤会を受け継ぎ、軍需工場で働く労働者に住宅を大量供給すべく昭和16年から21年まで全国の工場の多い都市で活動した「住宅営団」物件と、横浜・川崎・千葉のチラシ物件では、立地がかなりかぶることである。用地が戦後に売り出され、不動産業者が購入したのではないかと推測し、資料が長く個人蔵だったため「幻」と呼ばれたこの組織を特段に紹介している。
1年がかりの探訪を終え、著者は改めて「庭付き木造平屋住宅」の魅力を語る。設計時点で「型」があっても、住民には必要に応じて増築、改築できる可変性・柔軟性があった。それに庶民の手が届いた昭和30~40年代は、詐欺と隣り合わせで夢が叶えられた時代でもあったのだ。
ALL REVIEWSをフォローする