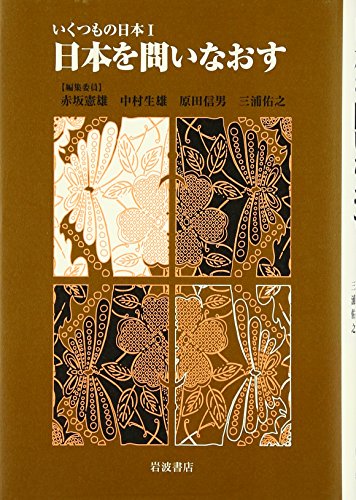書評
『白河法皇 中世をひらいた帝王』(角川学芸出版)
時代を切り開くか時代に殉じるか
最近の政治家の発言を聞いていると、その根底にある思想の浅さが目立ってしかたがない。滑稽にさえ思えてくる。日頃から抱いている浅薄な鬱憤(うっぷん)が、事件にかこつけてほとばしり出るのであろう。浅さを「庶民感覚」だと勘違いしているから困ってしまう。では一体、時代を遡って日本の政治家はどうだったのか。たとえば院政を始めたとされる白河法皇はどうか。美川は近作でこの白河法皇について語っている。
政治勢力が激しく競合する中世社会のなかで、天皇の権威を守り、天皇制と朝廷とを存続させるべく、王家の家父長権を確立し、院政という専制体制を生み出した、というのが、白河の政治への評価である。
具体的には、白河の専制君主への道を跡付け、院政の政治の方式を明らかにし、その院政を支えた院近臣や実務官僚、さらに武士の存在を探り、他方で寺院の大衆が強訴する時代相に触れ、最後に王権の基盤としての京と白河・鳥羽の都市環境を考察している。
美川のこれまでの院政の政治研究を前提に、白河法皇の政治的な行動に絞って、その特質に迫った力作であり、総じて、白河法皇は、時代を強い意思をもって創り出した人物ではなく、時代の大きなうねりのなか、その意思とは別の形で時代を前へと進めてゆく作用を果たした、と結論づけている。
たしかに日本の政治家にはそう評されるタイプが多い。時代の流れに沿って動いただけであるといった政治家が多く、野心的な政治家は不遇のうちに滅ぼされている。信西や信長などはその典型であろう。だが白河の場合、そのどちらでもないのではないか。
本書を読んだ限りでも、相当に強い意思をもっていたことがわかる。父後三条の遺言を無視して我が子に皇位を継承させた点をはじめ、白河と鳥羽の地を開発し、出家の身ながら政治の実権を握るなど、これは単に時の流れに応じてというものではなかろう。
その目で見てゆくと、意外と本書は白河の個人としての動きへの言及が乏しい。それはこの時代の文化についてほとんど触れていないこととも関連があろう。たとえば白河には自分を「文王」であると語った逸話がある。皆がその発言に耳を疑ったところ、続けて自分が文に優れているからいうのではない、文に優れた人物を登用したからであるとも語った、という。
この『古事談』の説話からうかがえるような、白河と文化との関わりにもっと触れて欲しかったと思う。そうすると白河の意思と政治のかかわりももっと違った面が浮かびあがってきたであろう。
ALL REVIEWSをフォローする