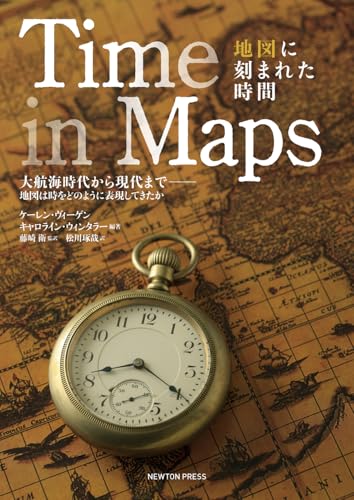書評
『身体と魂の思想史 「大きな理性」の行方』(講談社)
現代人の茫漠たる不安感を示す
日本人にもかなり馴染(なじ)みのラテン語表現にCogito,ergo sum.(私は思う、故に私は在り)がある。近代哲学の祖であるデカルトの語ったもの。心身二元論の立場ながら、自己意識の作用を身体から切り離してしまうのである。しかも、端的に次のように表明している。「私はそこから、自分がひとつの実体であり、その実体の本質なり本性なりは考えることだけにつきるし、またその実体は有るためにどんな場所も必要としなければ、どんな物質的なものにも依存しないことを認識したのです」(「方法序説」白水社)ところで、そもそも中世のキリスト教の文化圏では、霊肉二元論が唱えられた。人々は得体の知れない身体には、理性では制御しきれない活動力があると感じていた。その魔力が人間をふりまわし、そのために神の救済の手にあずかれないという思いがあったのだ。
さて、このような霊肉二元論や心身二元論は、ユーラシアの西部にあっては、一神教が頭をもたげた古代末期から、ほとんど誰もが疑わないものだった。ところが、20世紀のサルトルに代表される実存主義の見方は、欲望の源泉である身体を制御する規範的なものを一掃し、「いま・ここにただ存在すること」の迫真性に向き合わせる。それは「実存は本質に先立つ」という名高い表現になる。この世の生に気づき、何者かになろうと欲し、自らの決意に従って行動すること――その様相に責任が伴うことを含めて、「アンガジュマン」(拘束・関与・参加)という言葉で明らかにした。
しかしながら、このような身体を重視する見方は、すでにメルロ=ポンティの哲学にも表れており、デカルトの考える「身体なき自己」は矛盾に満ちているという。そうすれば、「生きられた身体」をめぐって心身の作用をとらえる視点が浮かびあがる。さらに、サルトルやメルロ=ポンティと同時代の英哲学者ライルもまた、「機械の中の幽霊」と称して、底流をなしていた心身二元論を批判していたのだ。
それらを遡ると、精神分析学のフロイトが現れ、さらにまた19世紀の思想家ニーチェが巨姿をみせる。「自我=外部身体」は「エス=内部身体」から切断されると、身体に流れるエロス的なものとのつながりを失い、「小さな理性」として行動するだけになってしまう。だから、フロイトにとっては、心的トラウマの体験を経て、「二つの身体」を統一し、ニーチェの言う「大きな理性」を取り戻すことが大切になる。本書の副題が“「大きな理性」の行方”となっているのは故なきことではないのだ。
戦前戦後にフランスの人種差別を体験したF・ファノンにとって、評価も判断もつかないまま自己を不確かに眺める――このことが自己身体の「付き合いにくさ」と結びつくという。
メルロ=ポンティは、19・20世紀の思想の見通しながら、心の科学を根源的に刷新する見方を提示する。人間の意識の原初は、「われ思う」ではなく「われできる」(je peux)という一語になるのだ。ここまで来ると、20世紀末以降の「身体化された自己」をテーマとする近未来の認知科学の問題が浮上する。身体と環境世界の間に拡がる心とは何か? それこそは現代の課題なのだ。現代人の茫漠たる不安感がより分かりやすくなるのかもしれない。
ALL REVIEWSをフォローする