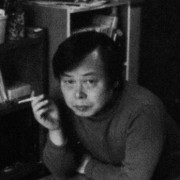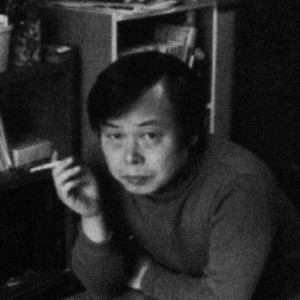書評
『魂の殺人―親は子どもに何をしたか』(新曜社)
犯罪としての教育
少年非行や家庭内暴力が問題になると、「教育が悪いからだ」という声が起こる。間違った教育をしたから、甘やかしたから、親が無関心だったから、子供は非行に走った。だから教育をし直さなければならない。ところが『魂の殺人』の著者の診断はまるでちがう。教育することこそが暴力の原因なのだ。原著名は「はじめに教育ありき」というほどの意味である。教育をしたために、子供は暴力や麻薬や自殺に走ったのである。なぜなら良い教育であろうが、悪い教育であろうが、あるいは反教育主義的教育であろうが、とまれ教育と名のつく教育一切が、教育をしている当事者(両親・教師)が気がつかないままに、幼児虐待の実情をはぐらかすカムフラージュにほかならないからだ、とA・ミラーは言う。
ショッキングな言説である。けれどもこの著者が、少年犯罪の問題をひたすら親・子関係に限って論じる論調の死角をついて、現在の親の前史、つまり親の幼年時におけるその両親との関係を現在の出来事に組み入れるとき、視界はにわかに大きくひろがる。現在の両親は、かつて彼らが子供のころ、権威主義的な(いやイデオロギー的に自由主義的であっても)その両親から受けた幼児期の痛みを、かつての両親の暴力への復讐として、教育の名において現在のわが子の上にくり返しているのだ。
かりに手を上げずに、いい子になるようにいたれり尽くせりの教育的配慮をしたところで、すでに前史のなかで形成された両親の「いい子」幻想とは、生きている子供にとっては、生命の多様性の芽をつみとる暴力的な強制措置にほかならない。無力な子供はそれに反対したり、怒ったりすることができないのだ。子供ははげしい、またはやわらかい暴力の前に服従し、一見いい子になる。しかし無意識のなかに追いやられた精神的外傷は、いつかは爆発せずにはいられない。
ヒトラー、十三歳で麻薬常習者となった少女クリスティアーネ、四人の少年を性犯罪的に殺害した二十歳の「好青年」ユルゲン・バルチュ、の三人の症例を追いながら、ほとんど推理小説的な推論にしたがって「教育」の犯罪を告発する著者の舌鋒は容赦ない。
きれいごとの解決はなく、親子双方が事実を直視し、痛みを痛みとして憤ることしかない。
(子供の側からの)真正の赦しは(両親に対する)憤りの傍をすり抜けていくのではなくて、その真中をくぐり抜けていくものです
【新装版】
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1983年9月19日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする