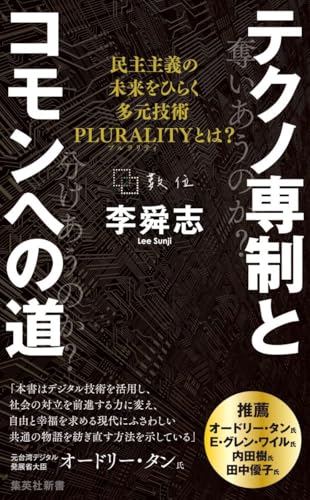書評
『救命センター カンファレンス・ノート』(集英社)
抽象化された死、感覚界に引き戻す
一貫した筋を追ったという本ではない。しかし救命センターのカンファレンス・ノートという形をとっているので、実録に近く、十の事例から何を考えるかは読者にまかされている。事例がいわばバラバラなのは、患者が勝手に運ばれてくるという、センターの実情がそういうものだからである。早朝に前日の入院患者についての報告が行われ、そこでの一問一答を通じて、具体的な事情が判明し、それについての部長つまり著者の想いが記される。身につまされるというか、大変だろうな、と読みながらしみじみ思う。新型コロナウイルスの流行で、医療従事者の負担やそれに対する感謝が話題にされるが、救命センターにしてみれば、それが日常だよ、何をいまさら、ということになろう。救急車で運び込まれる事例は、本人や家族にとっては一大事件であっても、センター側からすれば日常のことである。
現代社会はその意味では強く抽象化、システム化されており、それは本日までの死者何名という数字に示されるとおりである。「死者」として一括される人たちは、実在としては一括できるような存在ではない。本書はその「何名」をできる限り具体化しており、感覚に訴えるという意味で、本書の現代社会に対する教育的な意味は大きいと思う。
感覚の軽視ないし無視は都会人の通弊であり、白板に黒ペンで白と書いたら、素直に白と読んでしまって、いささかの反省もないという人たちである。素直に読むなら黒だろう、というのが、原始的な感覚人の言い分である。現代の小学校で、先生が黒板に黒と白墨で書いたときに、白と読む子がいたら、どう扱われるであろうか。極度に反抗的として罰せられるだろうか。
さまざまな分野で実体験とか、現場と呼ばれるものは、意識が優先する現代社会での感覚の再評価を意味しているのであろう。本書と無関係のようだが、子どもの教育に関しては、このことが重要だと信じる。成人すればどうせAI(人工知能)を中心とする抽象的なシステムの世界に巻き込まれていくのだから、子どものうちくらいは、感覚的な世界に十分に触れさせておくべきではないのか。
本書の全体は十話の事例から構成され、第一話は「それは死体!?」、以後は「死体」の部分が発見系、自殺、運命、善行、寿命、差別、災害、急患、無駄というタイトルになっている。疑問符と感嘆符がすべてにつけられているのは、感覚的な実態から抽象的な概念への移行が常に意識されていると思われ、話はそう単純ではないよ、という著者の想いが感じられる。よく考えられた上手な構成というべきであろう。
第一話は二十六歳の女性、母親と口論した結果、建物の十二階から飛び降りて、中庭の自転車置き場の屋根を突き破って落ちたという症例である。運び込まれたときはすでに手の施しようがない状態だったので、死体?となっているわけだが、その裏には複雑な事情が絡んでいることは想像に難くないであろう。推理小説というジャンルがあることからもわかるように、人生の終末は人々の想像力に強く訴える。各話は一つの短編小説としても読むこともできよう。面白い本だと、不謹慎ながら推薦したい。
ALL REVIEWSをフォローする