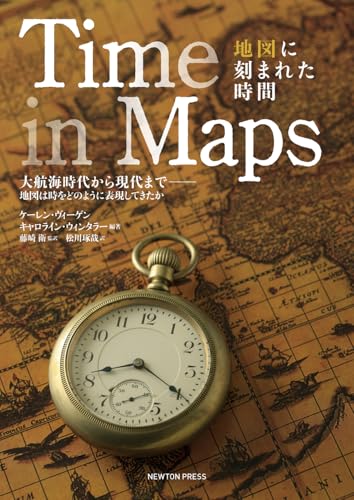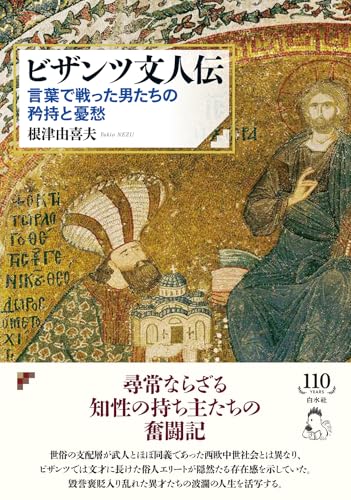書評
『ローマ史再考: なぜ「首都」コンスタンティノープルが生まれたのか』(NHK出版)
ローマ帝国末期をめぐって、たんなる衰退ではなく、むしろ発展と変容の歴史と理解しながら、斜めの視点でローマ史の再考を迫ってくる。
ディオクレティアヌス帝の前代未聞の自らの退位後、数年の混乱を経て帝位に就いたコンスタンティヌスは、旧来の体制に決別すべく新都コンスタンティノープルを建設する。広大な帝国に複数の皇帝がおり、「皇帝のいる場所がローマ」であった。
だが、新都にも元老院が設置されたことは画期的であった。新しい貴族層という支配階層が生まれる種が蒔(ま)かれたからである。しかし、これでも「遷都」と呼んでいいのか躊躇(ためら)われる。というのも、元老院はローマにも相変わらずあったからである。さらに、火急の戦線があれば皇帝が移動し、軍団も官僚団も宮廷もともに移動する。皇帝がコンスタンティノープルに定住するのは4世紀末のテオドシウス帝のときからであった。そのとき初めて「首都」と呼べる華々しい儀礼の舞台が備わるのだ。
帝国末期の出来事のなかでも見過ごされがちな諸問題をとりあげており、異彩を放つ新進気鋭の意気込みが感じられ、心地よい読後感がある。
ディオクレティアヌス帝の前代未聞の自らの退位後、数年の混乱を経て帝位に就いたコンスタンティヌスは、旧来の体制に決別すべく新都コンスタンティノープルを建設する。広大な帝国に複数の皇帝がおり、「皇帝のいる場所がローマ」であった。
だが、新都にも元老院が設置されたことは画期的であった。新しい貴族層という支配階層が生まれる種が蒔(ま)かれたからである。しかし、これでも「遷都」と呼んでいいのか躊躇(ためら)われる。というのも、元老院はローマにも相変わらずあったからである。さらに、火急の戦線があれば皇帝が移動し、軍団も官僚団も宮廷もともに移動する。皇帝がコンスタンティノープルに定住するのは4世紀末のテオドシウス帝のときからであった。そのとき初めて「首都」と呼べる華々しい儀礼の舞台が備わるのだ。
帝国末期の出来事のなかでも見過ごされがちな諸問題をとりあげており、異彩を放つ新進気鋭の意気込みが感じられ、心地よい読後感がある。
ALL REVIEWSをフォローする