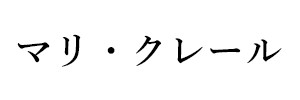書評
『アベラシオン バルトルシャイティス著作集 (1)』(国書刊行会)
偏倚な博物誌
謎に満ちた幻想美術史家の4つのエッセー
ソ連邦崩壊の渦中でなにかと話題のリトアニアの出身でパリに流亡の身を置いた、謎に満ちた幻想美術史家の待望久しい名著邦訳がついに読めた。原著は一九五七年の刊である。邦訳に随分暇がかかったがケガの功名かもしれない。というのも八〇年代、亡くなる前のバルトルシャイティスが一連の主著に思い切った増補改訂を試みて、超有名詩人・美術史家のイヴ・ボンヌフォワが編集の後押しをした作品群が「逸脱の遠近法」という名の叢書となって知的市場にどっとお目見えして一種ブームになったからであるし、そういう動きの中で生年さえ不明だったその生涯を丁寧に追った伝記(シュヴリエ『バルトルシャイティスの肖像』一九八九)まで出てきたからである。図像と視覚をキーワードに文化史記述を九〇年代に開こうとして今一番ホットなMIT(マサチューセッツ工科大学)出版局の「オクトーバー」叢書中の一巻として見事な英訳版の『アベラシオン』が出たこともあって(一九八九)、この中東欧の南方熊楠の本当のブームはどうやらこれからが本番らしい気配だからである。ヨーロッパ中世の怪物その他偏倚なオブジェの東洋起源を超人的な博引傍証を駆使してたどった『幻想の中世』の著者として既に知られていよう(邦訳・リブロポート)。それが出た同じ一九五五年には、遠近法という合理の「視」をはすかいにズラし歪めるアナモルフォーズを扱った作品も出ている。六七年には地母神(イシス)の東洋起源と「エジプト趣味(エジプトマニー)」現象を博捜する大著、そして七八年には鏡のあらゆる伝説と科学を縷説した一大百科全書を出した。このたびの国書刊行会の壮挙はこれらを著作集として一括して紹介しようという、先に言った増補改訂版を底本にした実に有難い企てである。記述・図版とも大幅に増大した見事な増補版であるからだ。飽きさせないカラー図版も、元々の版にはないものである。
要するに「類推の魔」である。オブジェの形態の基本的な骨格を見抜く力は本能的なもので、澁澤龍彦や荒俣宏、ロミやロジェ・カイヨワ、エリアーデやマンリオ・ブルーサティンのそれに似ている。これはあれに似ていると主張するためには当然、類推的想像力が駆けめぐるフィールドとしての博大な知識、特に形態の厖大な記憶というものが必要になるが、この点も想像を絶する。エリアーデもそうだし、ヤン・コットもそうだし、映画作家ジョナス・メカスだってそうだが、そういう中東欧独特の「普遍人」的知識の典型のように思われる。
フランス講壇美術史界の泰斗アンリ・フォションの娘婿であり、自らも教壇に立った。学問的な仕事も多い。一九二〇年代末から五〇年前夜までは中東欧の民俗芸術やロマネスク美術をめぐるきちんと学問的な仕事をしていて、五〇年代以降の仕事の滋養分となっているのだが、「学者」としての彼を好む人たちは妙に反近代という線でハネ上がった感じの後期(?)バルトルシャイティスを嫌う。人を介して、まことに堅実な学風を誇る辻佐保子先生にお伺いを立てたことがあるが、そういうことをおっしゃられた。企画人として、当時の編集者宮崎慶雄氏ともどもハタと悩んだことを、今は懐かしく思いだす。
たしかに五〇年代から六〇年代末にかけてのバルトルシャイティスは、象徴と神話をキーワードに、近代西欧が意識下に抑圧してきたものを掘り起こそうとする世界同時多発的な運動を、しかし野暮なイデオロギー抜きに、図像と類推の飛躍を楽しみながら、代表してきた。そのことがやっと今、見えかかっている。彼を重要な霊感源とした澁澤、種村季弘、山口昌男といった人の仕事の少しずつ見えてき始めた形を通して、と言ってもよいだろう。
想像力のネットワークを追跡することで、ネットワークとしての想像力の構造が見えてくる。それがいつに変らぬバルトルシャイティスの魅力だ。『アベラシオン』も例外ではない。人間の顔に動物の顔を透かし見る想像力、石の模様にキリストの姿や世界終未の惨劇風景を読みとる想像力、ゴシックの伽藍に鬱然たる森の構造を見抜く想像力、そして十八世紀風景庭園に永劫不易の楽園イメージを感得する想像力。この四つの「伝説」の起源と系譜たどりが表向きの主題である。何しろ文字通り偏倚(アベラン)な主題揃いだから、読むだけで愉しい。特に「絵のある石」をめぐる章は澁澤の名エッセー「石の夢」やカイヨワの『石』『石に書く』と比べると、六〇年代型イメージ人間同士の通底する部分、微妙な差異など分かって実に而白い。バシュラールの「大地と夢」をめぐる繊細な文章にも近い。
人間の身振りの底に動物のそれを見る。そういう発想は古代ギリシアに遡るし、イスラムにも遡る。そしてそれが観相術をうみ、リアリズム描写をうみ、十九世紀漫画ブームをうむ。ひとつの「伝説」の現在を描くため、その祖型さがしが時間(古代へ)と空間(東洋へ)の二つのヴェクトルで進められていくこのパターンはいつも同じ。ひとつの想像力が共時、通時の自在なネットワークの中で自ずと浮かびあがってくる仕掛けである。そんなふうに簡単に言ってしまうと身も蓋もないが、祖型遡及の長い長い行程に気が遠くなるほど豊穣につめこまれる逸話、事実、珍奇な人名、書名そのものにこの人の比類ない魅力がある。「猥雑の肯定」者、南方熊楠などのスタイルだが、もう一度言えば中東欧の悠然たる語り部の魅力だろう。エリアーデにもそんなところがあった。二次資料の組み合せでデッチあげたぼくなどの糞ったれ文化史とは格が違うのだ。文献注を一瞥して、ワルブルクやエラノスといった超弩級研究機関の出した研究論文に少し言及があるくらいで、あとは全て生の一次資料。
元の資料をおいしそうに堪能し抜いた挙句に出てくる、語り部自身面白くてたまらなそうな語り口が魅力だ。範疇というものを融通して逸脱現象を集め、その融解の仕方そのものの幻想化作用を堪能させてくれたロミの奇書『偏倚(アンソリット)の歴史』や『偏倚(アンソリット)な饗宴史』にも通ずる語り口(のち前者は『突飛なものの歴史』、後者は『悪食大全』にて邦訳。作品社)。われわれの批評が完全になくしてしまったものが、ある。リトアニアという欧州の辺境という出自がそうさせるのか、それとも五〇年代という大戦直後の崩壊感と祖型渇仰の夢想が貼り合わさった時代がそうさせたのか。とにかくもの凄い世相だったのである。
『アベラシオン』刊行の一九五七年はホッケの『迷宮としての世界』の出た年。ホッケの同書中の歪曲遠近法論はバルトルシャイティスのそれのほとんど丸写しだ。今世紀初頭に生れ、八〇年代に果てたこの二人ほど酷似した精神も少ない。合理主義への否(ノン)。非合理なるものの復権と系譜化。二人とも西欧の底、ヘレニズムの彼方に祖型を求めて「アジア風(ふう)」に逢着した。カントロヴィッチの名著『王の二つの身体』も(のち二宮隆洋差配で平凡社より邦訳)、ロッシの『魔術から科学へ』も、ショーレムの『ユダヤ神秘主義』も、みんな五七年だ。近代批判から中世へ、東洋へ、隠秘哲学へと、多様な遡及のヴェクトルが向いた、ゴシッ建築への深い関心を『アベラシオン』はパノフスキーの『ゴシック建築とスコラ哲学』(一九五七)と共有していそう(これも二宮氏が邦訳企画)。エリアーデの『聖と俗』、フライの『批評の解剖』、チョムスキーの『文法の構造』をうんだ同じ年が『アベラシオン』をうんだ。深層にある創出構造に対する関心、神話と象徴と伝説に対する強迫観念が世界を魅了した、まことにもって奇怪な年である。近代が妙なものへの関心を通じて反近代へと反転していく、ちょうつがいに当る年だ。
想像力そのものが、無碍に動き回るネットワークであることが体感できる本。視線に自由な運動を許す図版が豊富なのも、きっとそのためである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする