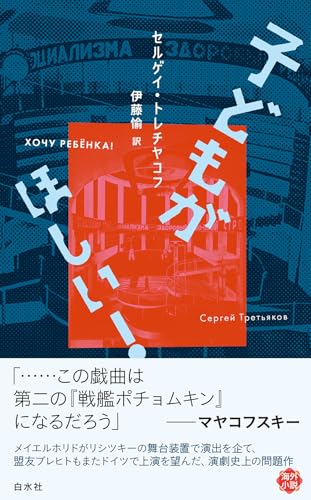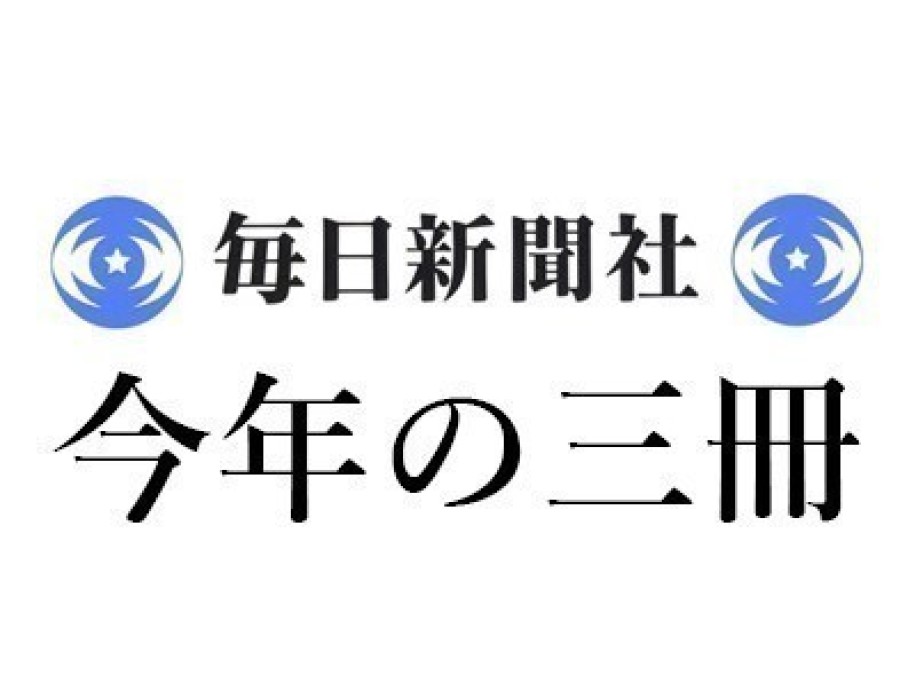書評
『鹿鳴館』(新潮社)
逆説のモラリテ
『鹿鳴館』は、政治的な意匠にくるまれた、愛に関する精妙なレッスンである。登場人物の一人、清原久雄は、「命がけ」の若き行動家という三島が好んで取り上げた典型であり、作者の最期と直結するように、そこでは例によって「大義」の欠如が問題となっている。「大義」があると信じて、結果裏切られる若者というイメージは、『英霊の声』でも扱われている通り、二・二六事件の青年将校たち並びに特攻隊の隊員たちに由来している。他方、最初から「大義」を持てない行動家のイメージは、例えば、『鏡子の家』の俊吉のような戦後世代の青年である。
久雄は、時代こそ違え、明らかにその後者に属している。彼の殺人という行動の源にあるのは、理想主義者の父清原永之輔との一貫した感情的対立であり、即ち私怨である。そして、それを強調するために描かれる、永之輔の政敵影山悠敏との関係は、「敵の敵は味方」の理屈で結びついた、一種の擬父子関係である、青年の純粋さを弄ぶ老人の好智というのもまた、三島文学におなじみの主題だが、その結末は、愛の欠如の象徴として、その身に父の放つ弾丸を受けとめるという悲劇的なものである。これに比べれば、筋書上は少なからぬ意味を持っている顕子との関係は、これまた三島らしく、いかにもあっさりとした若者同士の恋でしかない。
では、その実母である影山朝子はどうであろうか。彼女は、その母性的な愛情によって、久雄との問に一つの絆を得ている。他方で、彼女と永之輔とのかつての熱烈な、短命の愛は、彼女とその現在の夫である悠敏との欺瞞的で冷ややかに持続する夫婦生活に対比されている。
朝子のこうした関係を実現し、支えているのは、人間的な「信頼」である。そして、芝居は、この朝子の信ずるところのものを、悠敏がいかにして破壊してゆくかという点に於いて展開される。
影山悠敏は、政治家である。そして、「鹿鳴館」という彼の居場所が象徴的に示している通り、欺瞞の操作を通じて目的を遂げようとする人間である。芝居の大詰め、夫の計略を知った朝子は、愛情について語る彼に、こんなことを言っている。
もう愛情とか人間とか仰言いますな.そんな言葉は不潔です。あなたのお口から出るとけがらわしい。
この台詞は、ただちに『サド侯爵夫人』の中で、ルネに向けて母親の言う次の言葉を思い起こさせる。
貞淑と言うのはおよし! お前の口からその言葉が、出る度毎にますますけがらわしくなる。
影山は、ルネと同様に、人が通常、最も尊いと信じている言葉に、独自の意味を浸透させ、内からそれを変質させる。彼らのあらゆる言葉が、そのための周到で緻密な論理である。徹底した快楽主義者であるサド侯爵の伴侶ルネにとって、母親に代表される十八世紀的な「貞淑」が、表層的な欺瞞でしかあり得なかったように、権謀術数の渦巻く政治の現実に生きる影山にとって、妻が信じて疑わない「信頼」なるものも、単にナイーヴな「お伽噺」に過ぎない。そういうものは、壊れやすいのである。もしそれが、壊れないとするならば、それこそは、あり得べからざる「化物」である、事実、久雄も朝子も、壮士たちの乱入に接しては、あっさりと永之輔への信頼を失ってしまう。
しかし、だからと言って、ルネも影山も、決してニヒリストではない、ただ、彼らの信じる人間の真実が、人が普通に考えてみるそれとは違っているというに過ぎない。彼らが主張するのは、そうした「貞淑」や「信頼」が、決して見ようとしない醜怪なものが人間にはあるという現実である。それはあらゆるキレイごとを粉砕し、人を絶望させる。「俺は友だちが壊れやすいものを抱いて生きているのを見るに耐えない。俺の親切は、ひたすらそれを壊すことだ」と語ったのは『金閣寺』の柏木だが、しかし、ルネや影山には、徹底したニヒリストである柏木とは違い、その絶望にさえ耐え、その絶望の極みにこそ芽吹く「信仰」や「愛情」がある。その逆説が、この芝居のミソである。
影山悠敏のあらゆる政治的陰謀は、凡そ人が愛に期待する誠実さからはほど遠い。しかし、その心理の力学が「嫉妬」によるものであったならば、それとても結局は、ひとつの愛のかたちではないか。彼が朝子に理解を求めたのは、そうした彼の「心」であり、そして、ついに理解を得られなかったのもまたその「心」だった。
『鹿鳴館』は、夜会のシャンデリアさながらに、きらびやかなレトリックが舞台を飛び交う華麗な芝居である。しかし、そこに「隠された」作者の心は、サド侯爵をモラリストと呼ぶその同じ意味で、モラリストのそれと言うべきではなかったろうか。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
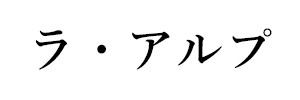
ラ・アルプ 2006年3月
ALL REVIEWSをフォローする