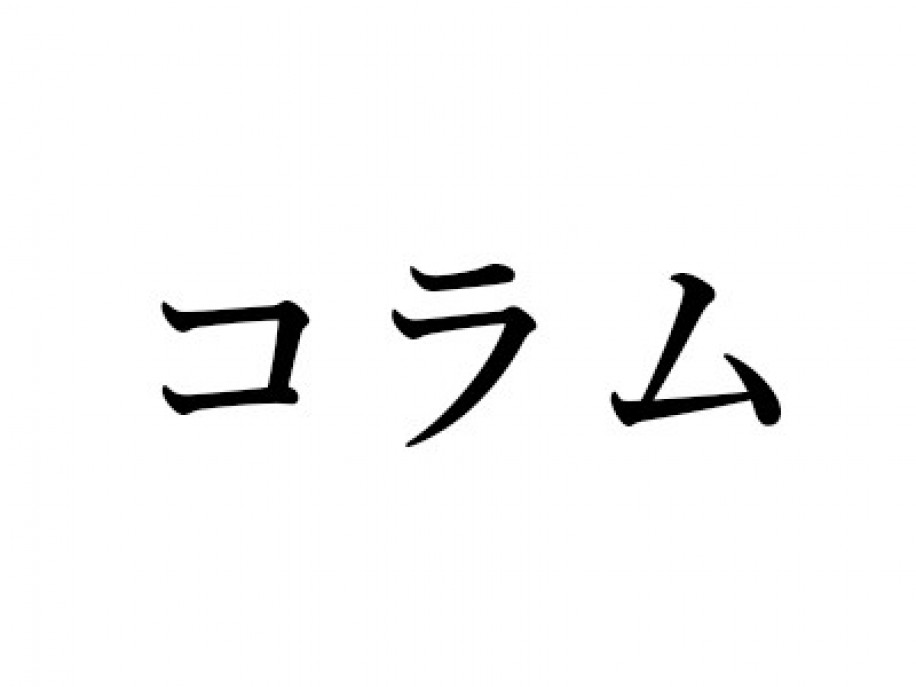書評
『宇垣一成―政軍関係の確執』(中央公論社)
“できすぎる人間”の悲劇
宇垣一成は、並の軍人ではなかった。それどころか、力量と識見とを充分に備えたできすぎた軍人であった。陸軍大臣・朝鮮総督として統治能力は折り紙つき。時折示される憲政や外交関係に関する認識も鋭くかつ深い。できすぎる人間は、それゆえに他から警戒され排除される。器にふさわしい働き場所が与えられない。これは一般論としても組織と人間をめぐる永遠のテーマである。宇垣もまたその例外たりえなかった。戦前期日本を通じて常に首相の本命とみなされながら、ついにその地位に就くことができなかったからである。なんと、首相への就任を自らの出身母体である陸軍の組織をあげての抵抗と、宇垣に期待をかけた宮中勢力の意外なまでの消極的態度とによって阻まれたのだ。
一九二〇年代に陸軍軍縮と軍近代化をなしとげた宇垣の実行力は、三〇年代の陸軍にとってはうとましく、宮中にとっては充分に警戒を要するものとなった。軍官僚制化及び宮中官僚制化が進んだこの二つの組織にとって、強力なリーダーシップは忌避の対象以外の何物でもなくなってしまったのである。
このことは後年の二つの事例で、さらに実証される。第一は日中戦争時、近衛内閣外相としての日中和平工作である。宇垣の和平工作はかなり精力的に行われたにもかかわらず、結局近衛首相及び周辺のサポートを得られず、また興亜院設立という形での陸軍の妨害にあって挫折してしまった。
第二は四〇年代に入ってくり返し試みられる吉田茂の宇垣擁立工作である。この工作の常に障害となったのは、湯浅倉平、木戸幸一という宮中勢力に他ならなかった。
著者は宇垣の一生を網羅的にではなく、いくつかの論点に絞って取り上げてメリハリをつけている。なかでも激しい薩長対立の中での宇垣の陸相就任について次のように述べた点は印象的だ。「陸軍三長官会議という新例で陸相になった宇垣が、後年三長官会議という壁に阻まれて大命を拝辞するに至ったのは皮肉である」。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする