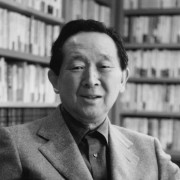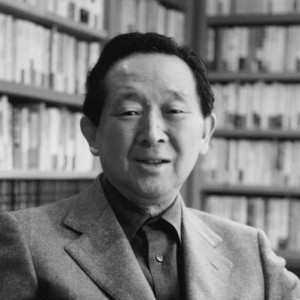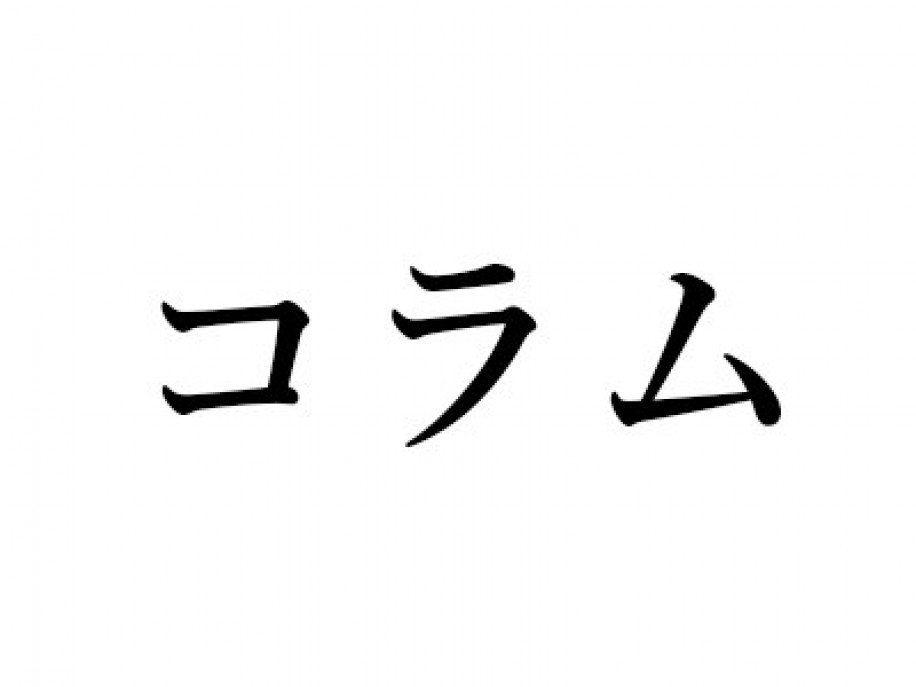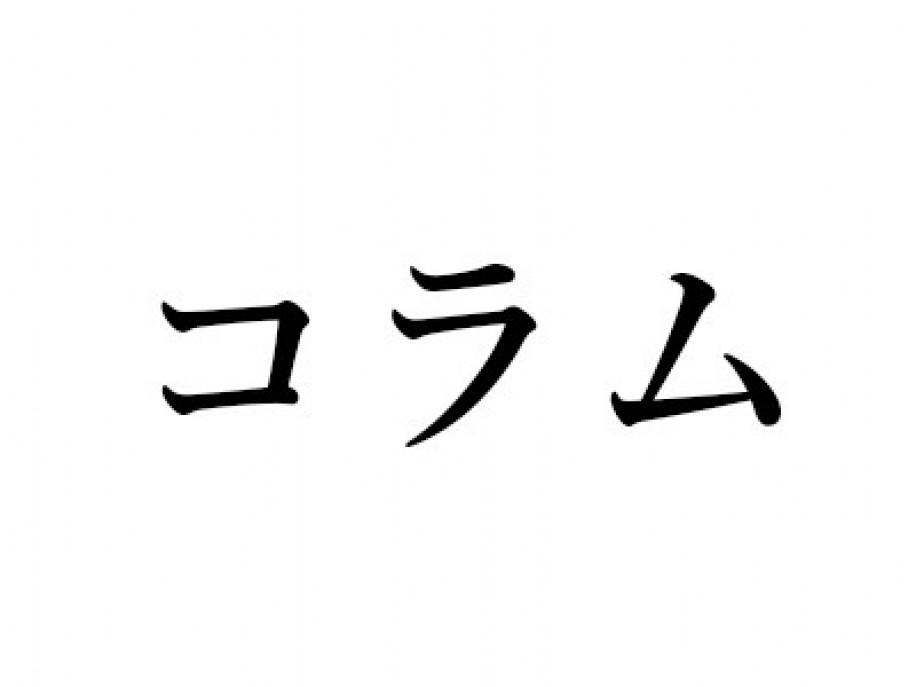書評
『女ざかり』(文藝春秋)
『たった一人の反乱』『樹影譚』と最近の著作に接してきた読者は、近著『女ざかり』を読んで、面白さに引きずられて読み終えたあとで不思議な浮遊感覚に捕えられたに違いない。もともと、丸谷才一の変幻自在ぶりは『樹影譚』を評価した大江健三郎、三浦雅士、小島信夫の三人が、全く異なる美点をあげてこの短篇を推したことにも現われていたが。
『女ざかり』を読んで、八一年に出版された田中康夫の『なんとなく、クリスタル』を想起したと言ったら、これも作者の魔術に幻感された言説と聞こえるであろうけれども。
かつて、海外有名ブランドが作品に登場するだけで感激した読者は、いま、由緒正しき新聞の美貌論説委員、有名大学の助教授、大蔵省理財局の課長補佐、名女優だった主人公の大伯母、北海道の銀行の頭取になっている別れた夫、それにイメージが高いか低いかは別として与党の幹事長、ヤクザの頭領、総理大臣、書道界の宗匠、哲学教授……と当代の〝有名ブランド〟が次々に登場して、世俗的な葛藤を展開するこの作品に感激するに違いない。
たしかにこれはエンターテイメントの専門家には領域侵犯的な作品であり、純文学信者には『樹影譚』の作者らしからぬと批評したくなるような興味を満載にした作品である。そうしておそらく、この作品が多くの読者を獲得した理由は、彼らが、ここには現実の社会が描かれていると思ったからではないだろうか。
この現象は、一面、今や伝統になった趣のある純文学概念の、内面重視、自我の葛藤という舞台が、多くの今日の読者にとっては、なんとなくネクラで胡乱に思えるということを示しているようでもある。
しかし少し注意深く読めば、現代社会の真のドラマと見えていた内容は次第にぼやけて、不可思議な霧のなかに溶解していくようであることは『樹影譚』の世界と通底しているのである。つまり、ここに描かれているのはシミュレーションとしての現代社会である。著者が描き出しているのはノイズとしての体制批判であり、ガゼットとしての愛、正義感、職務への忠誠心であり、現代社会は権力者であっても大衆であっても肩書で値打ちの高下が決まる訳ではないリゾーム構造で出来ているということへの認識なのである。それでいて約束事として肩書が幅を利かせている。それを実体と錯覚するおめでたい人間だけが肩書を目がけて競争する。作中、与党の幹事長榊原が言うように、今日に生きることは、「いやな渡世だなア……」なのである。
人間ばかりではない。ある一定の役割を社会から期待されている新聞も、嘘と知りつつ、また不可能と自認しつつ、それにしては高い気位を持って、良識の普及と世論指導に従事しなければならないのである。
時に、真面目なために虚実皮膜の間隙に落ちる人物が現われる。女性論説委員になった南弓子がその主人公である。美貌で才智に溢れる彼女には、「男四十前十一人衆」と呼ばれる数多くの〝崇拝者〟がいる。編集局などを訪れればごろごろしていそうな、やや古いタイプの記者浦野も、仙台の大学の哲学科の教授豊崎もそのひとりである。
その他、妻が狂っていることを隠していた首相も、虚実の膜がぴったり貼りついてしまった主人公の娘千枝、その男友達の大蔵官僚、日本史の助教授渋川たちは、いずれも浮遊感覚に漂っている。読み方によっては、従来の〝純文学〟は定住者の感性を基礎にしていたが、現代の小説は都市のなかに生きているというふうに、やや舌足らずの分析を行なうことも可能である。言いかえれば、この小説のリズムは新聞のコラムを作るリズムに平仄を合わせて作られているのである。こうした社会では芸術家と呼ばれる人も、与党政治家に喰い込んでいる書道家の大沼晩山のように、宗匠の道を選べば裕福になれるのであり、裕福になるために芸術の道を選ぶ若者も多く、その点では作家詩人のタレント化も進んでいるといっていいだろう。
このような現代社会では、憲法問題と座頭市の正義感と文化人類学のポトラッチ的贈与論は同じ平面に並ぶのである。著者はそのことを描いている。興味に釣られて読んだ後で読者は、現代社会は何なのだろうと考えてしまう。これはそのようなたくらみを巧みに描出した血わき肉おどる純文学と言えよう。
【この書評が収録されている書籍】
『女ざかり』を読んで、八一年に出版された田中康夫の『なんとなく、クリスタル』を想起したと言ったら、これも作者の魔術に幻感された言説と聞こえるであろうけれども。
かつて、海外有名ブランドが作品に登場するだけで感激した読者は、いま、由緒正しき新聞の美貌論説委員、有名大学の助教授、大蔵省理財局の課長補佐、名女優だった主人公の大伯母、北海道の銀行の頭取になっている別れた夫、それにイメージが高いか低いかは別として与党の幹事長、ヤクザの頭領、総理大臣、書道界の宗匠、哲学教授……と当代の〝有名ブランド〟が次々に登場して、世俗的な葛藤を展開するこの作品に感激するに違いない。
たしかにこれはエンターテイメントの専門家には領域侵犯的な作品であり、純文学信者には『樹影譚』の作者らしからぬと批評したくなるような興味を満載にした作品である。そうしておそらく、この作品が多くの読者を獲得した理由は、彼らが、ここには現実の社会が描かれていると思ったからではないだろうか。
この現象は、一面、今や伝統になった趣のある純文学概念の、内面重視、自我の葛藤という舞台が、多くの今日の読者にとっては、なんとなくネクラで胡乱に思えるということを示しているようでもある。
しかし少し注意深く読めば、現代社会の真のドラマと見えていた内容は次第にぼやけて、不可思議な霧のなかに溶解していくようであることは『樹影譚』の世界と通底しているのである。つまり、ここに描かれているのはシミュレーションとしての現代社会である。著者が描き出しているのはノイズとしての体制批判であり、ガゼットとしての愛、正義感、職務への忠誠心であり、現代社会は権力者であっても大衆であっても肩書で値打ちの高下が決まる訳ではないリゾーム構造で出来ているということへの認識なのである。それでいて約束事として肩書が幅を利かせている。それを実体と錯覚するおめでたい人間だけが肩書を目がけて競争する。作中、与党の幹事長榊原が言うように、今日に生きることは、「いやな渡世だなア……」なのである。
人間ばかりではない。ある一定の役割を社会から期待されている新聞も、嘘と知りつつ、また不可能と自認しつつ、それにしては高い気位を持って、良識の普及と世論指導に従事しなければならないのである。
時に、真面目なために虚実皮膜の間隙に落ちる人物が現われる。女性論説委員になった南弓子がその主人公である。美貌で才智に溢れる彼女には、「男四十前十一人衆」と呼ばれる数多くの〝崇拝者〟がいる。編集局などを訪れればごろごろしていそうな、やや古いタイプの記者浦野も、仙台の大学の哲学科の教授豊崎もそのひとりである。
その他、妻が狂っていることを隠していた首相も、虚実の膜がぴったり貼りついてしまった主人公の娘千枝、その男友達の大蔵官僚、日本史の助教授渋川たちは、いずれも浮遊感覚に漂っている。読み方によっては、従来の〝純文学〟は定住者の感性を基礎にしていたが、現代の小説は都市のなかに生きているというふうに、やや舌足らずの分析を行なうことも可能である。言いかえれば、この小説のリズムは新聞のコラムを作るリズムに平仄を合わせて作られているのである。こうした社会では芸術家と呼ばれる人も、与党政治家に喰い込んでいる書道家の大沼晩山のように、宗匠の道を選べば裕福になれるのであり、裕福になるために芸術の道を選ぶ若者も多く、その点では作家詩人のタレント化も進んでいるといっていいだろう。
このような現代社会では、憲法問題と座頭市の正義感と文化人類学のポトラッチ的贈与論は同じ平面に並ぶのである。著者はそのことを描いている。興味に釣られて読んだ後で読者は、現代社会は何なのだろうと考えてしまう。これはそのようなたくらみを巧みに描出した血わき肉おどる純文学と言えよう。
【この書評が収録されている書籍】
中央公論 1993年5月
雑誌『中央公論』は、日本で最も歴史のある雑誌です。創刊は1887年(明治20年)。『中央公論』の前身『反省会雑誌』を京都西本願寺普通教校で創刊したのが始まりです。以来、総合誌としてあらゆる分野にわたり優れた記事を提供し、その時代におけるオピニオン・ジャーナリズムを形成する主導的役割を果たしてきました。
ALL REVIEWSをフォローする