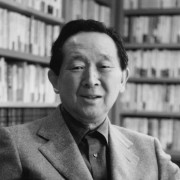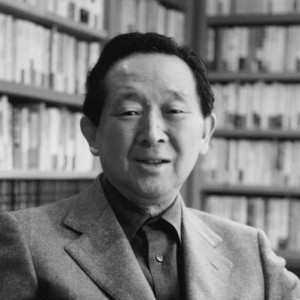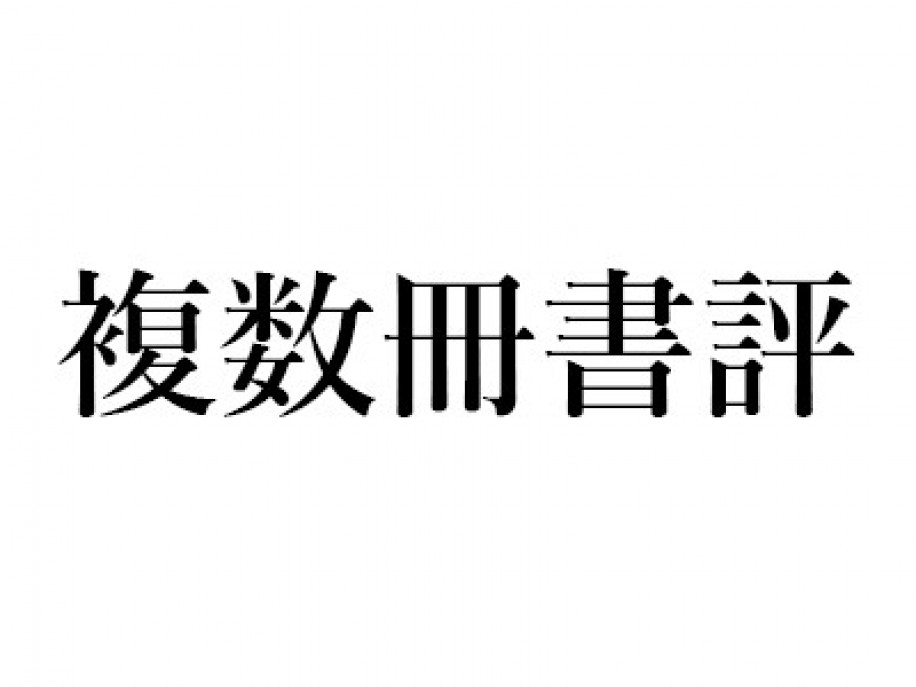書評
『一休伝説』(講談社)
臨済宗の僧としてばかりではなく、日本の思想家として、箱庭みたいな道徳律をはみ出して自在に生き、大きな精神的沃野を拓(ひら)いてみせた一休和尚のことを書くのは、作者・岡松和夫氏の年来の目標であったようだ。
そのために著者は、主題を体内で暖め、一休について採取した資料を胸中で醗酵させ、三十年の歳月の後にこの作品を書きあげたようである。
そうした長期の作業を可能にしたのは、岡松和夫という創作主体と一休和尚との取り組みがある種の、文学的必然性を持っていたからだ、という気がする。その必然性とはどんなものだったのだろう。
著者は『志賀島(しかのしま)』(一九七五年)で芥川賞を受賞して以来、『詩の季節』『薄氷を踏む』など、どの一冊を取ってみても、決して文学的な質をゆるがせにしない仕事を続けてきた作家である。その主題は、文学としか呼びようのない資質と俗との矛盾、葛藤であり、理想と現実との相克であった。一休和尚は、そのような相克を悠々と乗り越えた存在であったから、それは氏の憧憬と探究心と反撥をも含んだ関心を掻き立てずにはおかなかったのだと思われる。
作者は、この『一休伝説』を二人の弟子、墨斉と祖心の互いに立場を異にする目を通して描き出している。墨斉は師の造戒の「山村樹下」の道を、祖心は俗に入って道を極める「酒(しゅ)肆(し)婬(いん)坊(ぼう)」の道を選んだ。この、立場の異なる二人の弟子の目を通すことによって一休という偉人の立体的な姿を描き出すことに作者は成功した。
いうまでもなく、文学にとって、一休が風狂の破戒僧であったか、本当は脱俗の禅僧であったかは関心の外の事柄である。文学を読む興味と、週刊誌を読む興味とは、ここのところが根本的に違うのである。文学にとっては、一休がどんな目付きをしていて、どんな体臭を放ち、どんな声で話したかが問題なのだ。それは、平家が勝つか源氏が勝つかは「吾か事にあらず」と言い放った藤原定家の態度にも通じていよう。妥協した言い方をすれば、一休は破戒僧であったから、脱俗の僧でもあり得たのであった。作者・岡松和夫氏はそのことを文学的に確かめ得たことによって、一休和尚を描き出すことに成功し、同時に氏の文学世界を確固とした空間として形成したのである。
【この書評が収録されている書籍】
そのために著者は、主題を体内で暖め、一休について採取した資料を胸中で醗酵させ、三十年の歳月の後にこの作品を書きあげたようである。
そうした長期の作業を可能にしたのは、岡松和夫という創作主体と一休和尚との取り組みがある種の、文学的必然性を持っていたからだ、という気がする。その必然性とはどんなものだったのだろう。
著者は『志賀島(しかのしま)』(一九七五年)で芥川賞を受賞して以来、『詩の季節』『薄氷を踏む』など、どの一冊を取ってみても、決して文学的な質をゆるがせにしない仕事を続けてきた作家である。その主題は、文学としか呼びようのない資質と俗との矛盾、葛藤であり、理想と現実との相克であった。一休和尚は、そのような相克を悠々と乗り越えた存在であったから、それは氏の憧憬と探究心と反撥をも含んだ関心を掻き立てずにはおかなかったのだと思われる。
作者は、この『一休伝説』を二人の弟子、墨斉と祖心の互いに立場を異にする目を通して描き出している。墨斉は師の造戒の「山村樹下」の道を、祖心は俗に入って道を極める「酒(しゅ)肆(し)婬(いん)坊(ぼう)」の道を選んだ。この、立場の異なる二人の弟子の目を通すことによって一休という偉人の立体的な姿を描き出すことに作者は成功した。
いうまでもなく、文学にとって、一休が風狂の破戒僧であったか、本当は脱俗の禅僧であったかは関心の外の事柄である。文学を読む興味と、週刊誌を読む興味とは、ここのところが根本的に違うのである。文学にとっては、一休がどんな目付きをしていて、どんな体臭を放ち、どんな声で話したかが問題なのだ。それは、平家が勝つか源氏が勝つかは「吾か事にあらず」と言い放った藤原定家の態度にも通じていよう。妥協した言い方をすれば、一休は破戒僧であったから、脱俗の僧でもあり得たのであった。作者・岡松和夫氏はそのことを文学的に確かめ得たことによって、一休和尚を描き出すことに成功し、同時に氏の文学世界を確固とした空間として形成したのである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
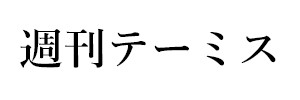
週刊テーミス(終刊) 1991年7月17日
ALL REVIEWSをフォローする