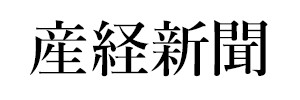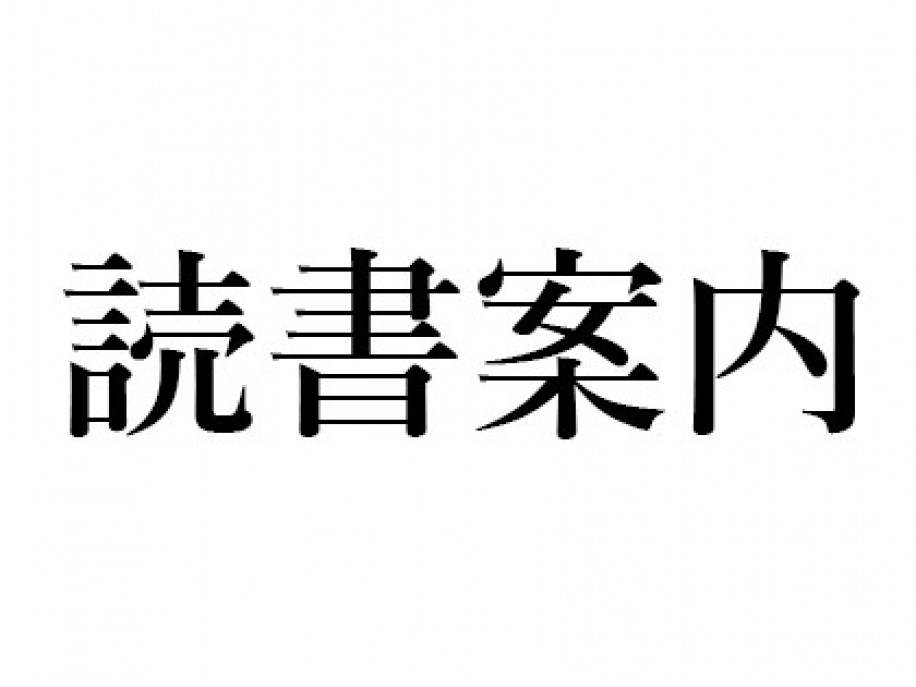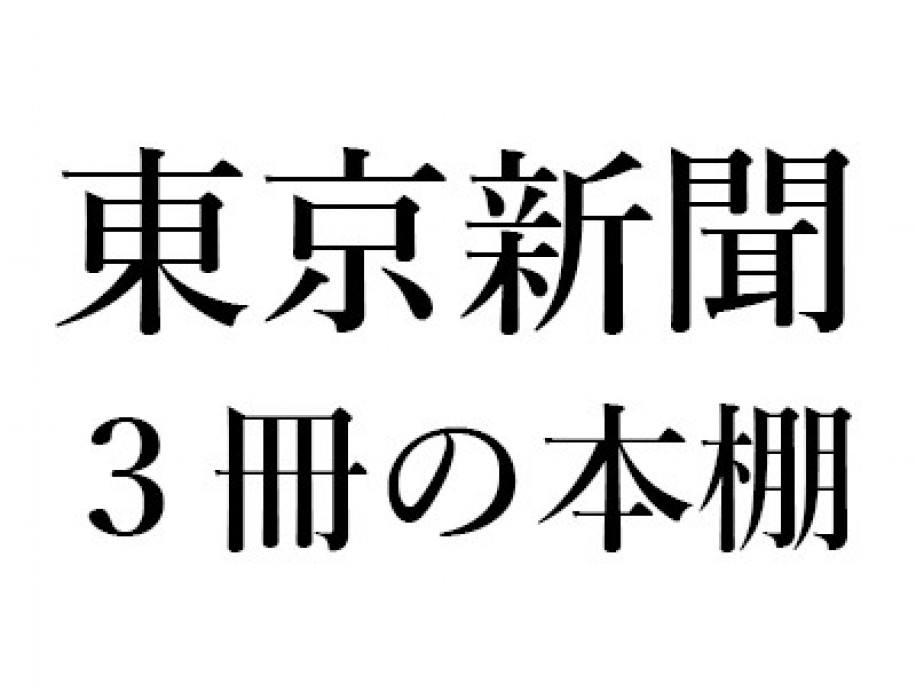書評
『偶景』(みすず書房)
著名なフランスの記号学者ロラン・バルトは、一九八〇年、惜しくも不慮の事故で亡くなった。彼の仕事は遺稿を含め、ほとんど翻訳で読むことができる。今回新たに訳された『偶景』も、そうした遺稿のひとつである。しかしこれはまた、何という作品だろう!
全体は細かな断片の寄せ集めだ。中心となるのは、一九六八年から翌年にかけて、モロッコで執筆された「偶景」と、一九七九年の「パリの夜」。どちらも未発表だったテクストは、日記のようにも読めるが、習作のようでもあって、すぐに意図がわかりにくい。著者の説明によると、これは「俳句」でもある。何かそれ以上のことを言うための材料ではなくて、その刹那のすべてを書きとめる充実。
この作品の狙いを、題名が隠しているらしい。偶景(アンシダン)とは〈ミニ・テクスト、短い書きつけ、俳句、……すべて木の葉のように落ちてくるもの〉のこと。他のテクストについてのべる(記号学の)かわりに、直接のべること、ただしただの小説になることを拒む「小説的なもの」をつづることを、バルトはめざしている。だがそれにしては、描かれている世界が異様だ。バルトはいまや老残の同性愛者で、モロッコの街頭やパリの裏町を、偶然の出会いを求めて彷徨する。その視線は男たちの肢体の上でねばついており、かなり淫靡だ。描かれていることに、嘘はあるまい。他人のこういう生理につきあうのは、正直言って愉快なものでない。
これらの遺稿は、公表するつもりで書かれたらしいが、生前活字にならなかった。ありのままをさらすのは、自分の死後にしようと計算したのかもしれない。
さて、『偶景』の文学的価値についてだが、私にはよくわからない。翻訳から判断してしまっては危険でもある。ふつうのスタイルで書かれていたら、『ヴェニスに死す』みたいな評価を受けたかもしれない。
少し気になることをのべよう。モロッコでもパリでも、登場するのは、現地や第三国人の男娼(ジゴロ)ばかりである。バルトの興味をひかない人びとや光景はすべて(不快)、(愚か)、(退屈)などと片づけられてしまう。彼は日課のように街を徘徊し、自室に戻ると、パスカルの『パンセ』を読む。この平然とした落差に、ブルジョアジーの傲慢を感じてしまう。
これはフランス中心主義の知識人の傲慢でもある。たとえば、ホメイニについて、バルトは〈びっくり仰天。……怒る気もしない。この時代錯誤的妄想には理性的説明があってしかるべきだ〉と書く。だが、イラン革命は起こった。どちらが妄想だったのか。
記号学という、いちおう客観的にみえる解読の手さばきが、その実どういう精神の舞台裏に支えられている(場合がある)かについて、この本は多くを考えさせてくれた。また花輪光氏の長文の解題「小説家バルト?」も、本文を読むうえで大いに参考になった。
【この書評が収録されている書籍】
全体は細かな断片の寄せ集めだ。中心となるのは、一九六八年から翌年にかけて、モロッコで執筆された「偶景」と、一九七九年の「パリの夜」。どちらも未発表だったテクストは、日記のようにも読めるが、習作のようでもあって、すぐに意図がわかりにくい。著者の説明によると、これは「俳句」でもある。何かそれ以上のことを言うための材料ではなくて、その刹那のすべてを書きとめる充実。
この作品の狙いを、題名が隠しているらしい。偶景(アンシダン)とは〈ミニ・テクスト、短い書きつけ、俳句、……すべて木の葉のように落ちてくるもの〉のこと。他のテクストについてのべる(記号学の)かわりに、直接のべること、ただしただの小説になることを拒む「小説的なもの」をつづることを、バルトはめざしている。だがそれにしては、描かれている世界が異様だ。バルトはいまや老残の同性愛者で、モロッコの街頭やパリの裏町を、偶然の出会いを求めて彷徨する。その視線は男たちの肢体の上でねばついており、かなり淫靡だ。描かれていることに、嘘はあるまい。他人のこういう生理につきあうのは、正直言って愉快なものでない。
これらの遺稿は、公表するつもりで書かれたらしいが、生前活字にならなかった。ありのままをさらすのは、自分の死後にしようと計算したのかもしれない。
さて、『偶景』の文学的価値についてだが、私にはよくわからない。翻訳から判断してしまっては危険でもある。ふつうのスタイルで書かれていたら、『ヴェニスに死す』みたいな評価を受けたかもしれない。
少し気になることをのべよう。モロッコでもパリでも、登場するのは、現地や第三国人の男娼(ジゴロ)ばかりである。バルトの興味をひかない人びとや光景はすべて(不快)、(愚か)、(退屈)などと片づけられてしまう。彼は日課のように街を徘徊し、自室に戻ると、パスカルの『パンセ』を読む。この平然とした落差に、ブルジョアジーの傲慢を感じてしまう。
これはフランス中心主義の知識人の傲慢でもある。たとえば、ホメイニについて、バルトは〈びっくり仰天。……怒る気もしない。この時代錯誤的妄想には理性的説明があってしかるべきだ〉と書く。だが、イラン革命は起こった。どちらが妄想だったのか。
記号学という、いちおう客観的にみえる解読の手さばきが、その実どういう精神の舞台裏に支えられている(場合がある)かについて、この本は多くを考えさせてくれた。また花輪光氏の長文の解題「小説家バルト?」も、本文を読むうえで大いに参考になった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする