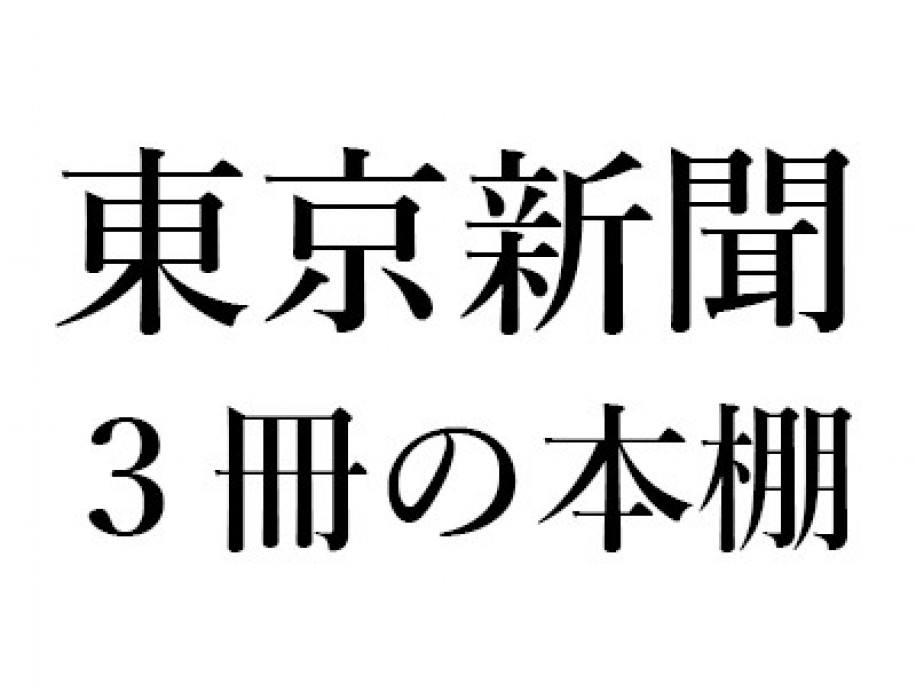書評
『ラシーヌ論』(みすず書房)
「恋愛悲劇の作者」像を覆す伝説の書
30年も前からみすず書房の近刊予告に載っていた伝説の書物がついに姿を現した。これだけで「事件」である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2006年)。その上、本書はバルトの本のなかでも〈ヌーヴェル・クリティック(新批評)〉の理念を具体化し、従来の実証主義的文学研究者の激怒を呼んだ記念碑的な著作だ。実際、パリ大学教授・ピカールは「新批評あるいは新たないかさま」という本を書いて、バルトを攻撃し、文学史に残る論争に発展したのだった。
だが、そうした歴史的な事情から遠ざかったいま、虚心にこの書物に接する読者を打つのは、バルトの読解のこの上ない鮮烈さだろう。
フランス古典主義を代表する大詩人ラシーヌ。優雅をきわめる恋愛悲劇の作者というイメージは一挙に覆される。
「悲劇の偉大な場所は、海と砂漠のあいだの、絶対的な影と太陽に追いつめられた不毛の土地である」
冒頭の一文に代表される直感的な世界把握の鋭さ。そして触覚的ともいえる感性の冴え。一方には、夜と影、灰燼、涙と眠りと沈黙の断絶なき現前があり、もう一方では、武器、松明、叫び声、きらめく衣装、生贄を焼く祭壇、金と炎とが際立つ。そんな明暗法の世界としてラシーヌを再構成するあざやかな読解に、私たちは息をのむしかない。
しかし同時に、バルトは恐るべき荒々しさで、ラシーヌの世界を、エロスと暴力、血と罪、挫折と死が渦まく原始遊牧民的な欲望の世界としても図式化してみせる。
その繊細さと暴力性のコントラストに、哲学、言語学、精神分析の薬味を絶妙の匙加減でふりかけるバルト節、こんな文章のアクロバット芸は誰にもまねできない。どんなに難解な概念を操っても、どれほど荒唐無稽に論理を飛躍させても、バルトの書くものには、つねに名人芸の色と艶があって、読む者を楽しませ、酔わせてくれるのだ。
解題と訳注の密度と量にも驚嘆する。特に、100ページに及ぶ卓越した解題は、フランス演劇に精通する訳者ならではの、ラシーヌを通して現代演劇の最前線を照らしだす試みにもなっているのである。
朝日新聞 2006年12月03日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする