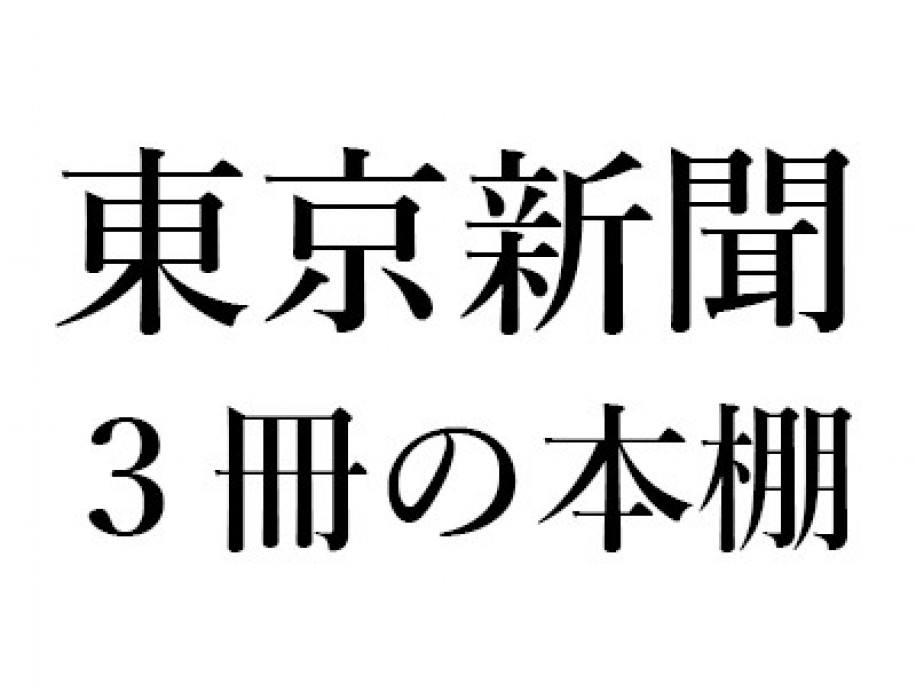書評
『モードの体系』(みすず書房)
二十世紀はのちのひとたちによってモードの世紀とよばれるかもしれない。流行の論理に巻き込まれないものはおそらくない。衣服をはじめとして、自動車や電気製品、歌やゲーム、さらには思想やアートの領域にもモードの論理は浸透していったし、この世紀の終わりには、その存在が尊厳そのものであるような顔にまで流行りすたりがいわれるようになった。
モードは身体に近いところほど深く浸透する。衣服、化粧といった身体の表面。あるいは歌やダンスといった身体の運動。それがわたしたちの存在そのものだからかもしれないし、あるいはアランも書いていたように、身体にも倦怠というものがあるからかもしれない。
あるいは資本の論理。物の生産、情報の生産がある種の飽和状態をむかえたとき、それは物や情報への欲望そのものの生産へとシフト変換せざるをえなくなる。つねに新しい欲望へと欲望そのものを更新するために、それを紡ぎだす物語を更新しなければならなくなる。二十世紀の神経はネオマニー(新しいもの狂い)を患いだしたのである。
ネオマニーという名の健忘症。その世界はヴァニティ・フェア(虚栄の市)であり、きらびやかで虚ろな「かげろうの帝国」である。ひとはそれに魅惑され、うっとりし、そして飽きればすぐにそれを棄てる。気分としては恣意的にであるが、構造としては強制的にである。
その儚い魅惑の構造を、その微妙な差異の論理を、記号現象としてクールに分析したのが、ロラン・バルトの『モードの体系』であった。バルトはファッション雑誌の言語、つまり「書かれた衣服」という、衣服よりもさらに”軽薄な”意味の断片を精密に分析し、そこから、「モードとは無秩序に変えられるためにある秩序である」とか、「モードは、みずからせっかく豪奢につくり上げた意味を裏切ることを唯一の目的とする意味体系というぜいたくな逆説をたくらむのだ」といった、フランスのモラリスト的伝統の見本のような文章を紡ぎだしたのだった。
以後、この書物は、映画や広告、都市や雑誌を織りなす社会の無意識を解読する文化記号論のバイブルのような存在として位置づけられることになったのだが、この書物がわたしを揺さぶったのは、その記号論的分析のあざやかな手つきによってよりも、むしろその言葉のきめ(テクストのテクスチュア)によってだった。意味の揺れ、意味の震えに身をゆだねながら、意味を通りすぎ、意味を衰弱させ、意味以後を想像する……そのふるまいには、わたしのような青くさい読者をも感応させる力があった。
意味のまとまりよりも意味のほつれをこそ愛で、単一性ではなく複数性を、集極ではなく散乱を、深さよりは表面を、固定よりは転位を選びとったバルト、その触角は閉じた体系としての知でなく、開かれ、横滑りしていく知のいかがわしくも官能的なよろこびを教えてくれた。
【この書評が収録されている書籍】
モードは身体に近いところほど深く浸透する。衣服、化粧といった身体の表面。あるいは歌やダンスといった身体の運動。それがわたしたちの存在そのものだからかもしれないし、あるいはアランも書いていたように、身体にも倦怠というものがあるからかもしれない。
あるいは資本の論理。物の生産、情報の生産がある種の飽和状態をむかえたとき、それは物や情報への欲望そのものの生産へとシフト変換せざるをえなくなる。つねに新しい欲望へと欲望そのものを更新するために、それを紡ぎだす物語を更新しなければならなくなる。二十世紀の神経はネオマニー(新しいもの狂い)を患いだしたのである。
ネオマニーという名の健忘症。その世界はヴァニティ・フェア(虚栄の市)であり、きらびやかで虚ろな「かげろうの帝国」である。ひとはそれに魅惑され、うっとりし、そして飽きればすぐにそれを棄てる。気分としては恣意的にであるが、構造としては強制的にである。
その儚い魅惑の構造を、その微妙な差異の論理を、記号現象としてクールに分析したのが、ロラン・バルトの『モードの体系』であった。バルトはファッション雑誌の言語、つまり「書かれた衣服」という、衣服よりもさらに”軽薄な”意味の断片を精密に分析し、そこから、「モードとは無秩序に変えられるためにある秩序である」とか、「モードは、みずからせっかく豪奢につくり上げた意味を裏切ることを唯一の目的とする意味体系というぜいたくな逆説をたくらむのだ」といった、フランスのモラリスト的伝統の見本のような文章を紡ぎだしたのだった。
以後、この書物は、映画や広告、都市や雑誌を織りなす社会の無意識を解読する文化記号論のバイブルのような存在として位置づけられることになったのだが、この書物がわたしを揺さぶったのは、その記号論的分析のあざやかな手つきによってよりも、むしろその言葉のきめ(テクストのテクスチュア)によってだった。意味の揺れ、意味の震えに身をゆだねながら、意味を通りすぎ、意味を衰弱させ、意味以後を想像する……そのふるまいには、わたしのような青くさい読者をも感応させる力があった。
意味のまとまりよりも意味のほつれをこそ愛で、単一性ではなく複数性を、集極ではなく散乱を、深さよりは表面を、固定よりは転位を選びとったバルト、その触角は閉じた体系としての知でなく、開かれ、横滑りしていく知のいかがわしくも官能的なよろこびを教えてくれた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする