書評
『現象学入門』(NHK出版)
むずかしいのが値打ち、と言わんばかりでとっつきの悪かったフッサールの現象学を、これはまた思い切って、誰にでも手のとどくサイズに噛みくだいてある。この本を読んでもまだ、現象学のことがわからない人は、よくよく自分が哲学に向いていない、と愕然としてもらいたい。
著者竹田青嗣氏のいろいろな思いが、この一冊にはこめられているようだ。
平明なわかりやすさが基調である。ふつうに生きることと、ものを考えることの距離をなくすこと。哲学することの躍動をとりもどすこと。下手な哲学の専門家には滅多にお目にかかれない、誰でも哲学できるはずだという率直な確信が快い。それを読者と共有しようとする態度が、わかりやすさの根底になっている。
そのうえで著者は、現象学を、もっとも果敢で先端的な哲学と位置づける。デリダなどポスト構造主義の潮流あたりが、現象学を、形而上学とか独我論とか決めつけるのは、とんでもない誤解なのだ。なぜなら近代哲学の根本的な謎、つまり《〈主観/客観〉の難問にたいしてほぼ完全なかたちで解答を与えたのは……フッサールの現象学だけ》(二四頁)なのだから。
ポイントは現象学がなぜ、独我論的構成をとるのかだろう。著者によればそれは、当然の選択である。フッサールは、主観/客観の一致(真理)を確かめることなど不可能である、と洞察した。にもかかわらず、誰もが世界・他者・事物の存在を「確信」してしまうのはなぜか? むしろ、それを解明すべきである。そのためには、主観の側から出発すること。それも、主観をとらえる一切の憶見(ドクサ)を排除し尽くした(還元した)ところから出発することが、戦略的に重要だー。
フッサールの著作は、いつでも積木くずしのように、もっとも原理的な場所から議論を組み上げていっては、いいところで一から出直す繰り返しで、全貌がつかみにくかった。しかしこの本を読むと、すっきり晴ればれ、フッサールという人物をつき動かす思考の必然が見えてくる。このわかりやすさは、すべての語彙をいったん咀嚼したうえで、嘘のない著者自身のことばに直して語っているところから来るものであろう。最後の章では、ハイデガー哲学との接続や、後読するさまざまな批判に対する反論もとりあげられていて、いちだんと広がりが出ている。まことに理想的な、現象学の入門書の登場である。
しかし、現象学と別の路線を進む私の立場からは、あえて異論も挟まねばなるまい。
著者はフッサールの境位が、余人の及ばないものであるという。しかし著者の描くところを信ずるなら、たとえば、確実性の問題を問いつめていった後期のヴィトゲンシュタインも、かなり近いところにいたことになるのではないか。彼の“言語ゲーム”の議論もまた、あらゆる懐疑論に抗して、人びとの日常のふるまいのなかの「確信」を掘り起こす作業にほかならなかった。同様に記号論や構造主義も、それほど捨てたものでないはずだ。主観/客観の図式を組み換えることが、そもそもこうした議論の動機であるから。
一方、現象学には固有の問題点もある。著者はフッサールの「他我」論の難点を、《フッサールが〈知覚〉直観を「他なるもの」の了解の第一起点(原的なもの)とした点にある》(一三六頁)と指摘する。そして、そのかわりに《情動的所与》を「原的な所与」に位置づけ直したらよいと言う。しかし私は、主観の彼岸にあるという点で、「言語」の重要性こそ無視できないのではないか、と思う。《要するに現象学で言う「本質」とは、言葉の意味のことだと考えていい》(五九頁)とまで言うのであれば、《メルロ = ポンティやJ・デリダのように〈知覚〉直観を「身体」や「言葉」によって“構成”されたものと考えるのは、現象学的には〈客観〉から〈主観〉を説明することになって背理となる》(一三七頁)と、簡単に言ってすませるわけにはいかないと思う。このあたりの議論を始めるときりがないが、著者は別の機会に氏の情動 = エロス論をさらに敷衍されるそうなので、楽しみに待ちたい。
竹田氏は、フッサールがこれまでおおむね誤解されてきたと言う。私もそんな誤解のくちだったと思う。氏の主張には説得力がある。が、フッサールの文章に、そのような誤解を受けても仕方のない部分があったことも、また確かではないか。本書のフッサール像が解釈として成立するか否か(成立してほしい!)は、テキストの詳しい検討にゆだねるべき問題で、私には何とも言えない。しかし、現象学の積極的かつ現代的な意味を最大限に引き出すことに成功している本書の、功績は疑いようもないのである。
【この書評が収録されている書籍】
著者竹田青嗣氏のいろいろな思いが、この一冊にはこめられているようだ。
平明なわかりやすさが基調である。ふつうに生きることと、ものを考えることの距離をなくすこと。哲学することの躍動をとりもどすこと。下手な哲学の専門家には滅多にお目にかかれない、誰でも哲学できるはずだという率直な確信が快い。それを読者と共有しようとする態度が、わかりやすさの根底になっている。
そのうえで著者は、現象学を、もっとも果敢で先端的な哲学と位置づける。デリダなどポスト構造主義の潮流あたりが、現象学を、形而上学とか独我論とか決めつけるのは、とんでもない誤解なのだ。なぜなら近代哲学の根本的な謎、つまり《〈主観/客観〉の難問にたいしてほぼ完全なかたちで解答を与えたのは……フッサールの現象学だけ》(二四頁)なのだから。
ポイントは現象学がなぜ、独我論的構成をとるのかだろう。著者によればそれは、当然の選択である。フッサールは、主観/客観の一致(真理)を確かめることなど不可能である、と洞察した。にもかかわらず、誰もが世界・他者・事物の存在を「確信」してしまうのはなぜか? むしろ、それを解明すべきである。そのためには、主観の側から出発すること。それも、主観をとらえる一切の憶見(ドクサ)を排除し尽くした(還元した)ところから出発することが、戦略的に重要だー。
フッサールの著作は、いつでも積木くずしのように、もっとも原理的な場所から議論を組み上げていっては、いいところで一から出直す繰り返しで、全貌がつかみにくかった。しかしこの本を読むと、すっきり晴ればれ、フッサールという人物をつき動かす思考の必然が見えてくる。このわかりやすさは、すべての語彙をいったん咀嚼したうえで、嘘のない著者自身のことばに直して語っているところから来るものであろう。最後の章では、ハイデガー哲学との接続や、後読するさまざまな批判に対する反論もとりあげられていて、いちだんと広がりが出ている。まことに理想的な、現象学の入門書の登場である。
しかし、現象学と別の路線を進む私の立場からは、あえて異論も挟まねばなるまい。
著者はフッサールの境位が、余人の及ばないものであるという。しかし著者の描くところを信ずるなら、たとえば、確実性の問題を問いつめていった後期のヴィトゲンシュタインも、かなり近いところにいたことになるのではないか。彼の“言語ゲーム”の議論もまた、あらゆる懐疑論に抗して、人びとの日常のふるまいのなかの「確信」を掘り起こす作業にほかならなかった。同様に記号論や構造主義も、それほど捨てたものでないはずだ。主観/客観の図式を組み換えることが、そもそもこうした議論の動機であるから。
一方、現象学には固有の問題点もある。著者はフッサールの「他我」論の難点を、《フッサールが〈知覚〉直観を「他なるもの」の了解の第一起点(原的なもの)とした点にある》(一三六頁)と指摘する。そして、そのかわりに《情動的所与》を「原的な所与」に位置づけ直したらよいと言う。しかし私は、主観の彼岸にあるという点で、「言語」の重要性こそ無視できないのではないか、と思う。《要するに現象学で言う「本質」とは、言葉の意味のことだと考えていい》(五九頁)とまで言うのであれば、《メルロ = ポンティやJ・デリダのように〈知覚〉直観を「身体」や「言葉」によって“構成”されたものと考えるのは、現象学的には〈客観〉から〈主観〉を説明することになって背理となる》(一三七頁)と、簡単に言ってすませるわけにはいかないと思う。このあたりの議論を始めるときりがないが、著者は別の機会に氏の情動 = エロス論をさらに敷衍されるそうなので、楽しみに待ちたい。
竹田氏は、フッサールがこれまでおおむね誤解されてきたと言う。私もそんな誤解のくちだったと思う。氏の主張には説得力がある。が、フッサールの文章に、そのような誤解を受けても仕方のない部分があったことも、また確かではないか。本書のフッサール像が解釈として成立するか否か(成立してほしい!)は、テキストの詳しい検討にゆだねるべき問題で、私には何とも言えない。しかし、現象学の積極的かつ現代的な意味を最大限に引き出すことに成功している本書の、功績は疑いようもないのである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
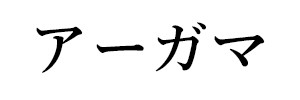
アーガマ(終刊) 1989年10月
ALL REVIEWSをフォローする









































