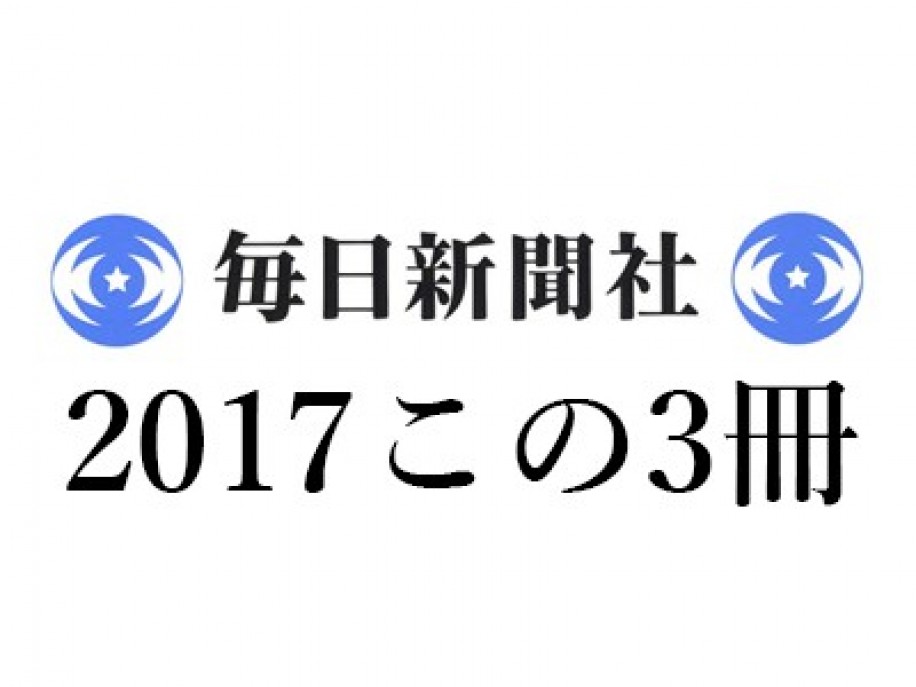書評
『恋愛論』(筑摩書房)
狂気と日常、論理と感性の架け橋
小説で恋愛を描くとき、自分に言い聞かせているのは「考えるな、感じろ」ということ。けれど考えることが嫌なのではなく、むしろ逆で、考えたくて仕方がないのだ。ただ、考えると恋愛小説は書けない。経験的にそう感じる。「恋愛について考える」ということは、「恋愛を(文学の中にだが)生み出し深める」ことに真っ向から反する。分析的に眺めたとたん、小説にとって最も大事な恋愛の「熱」は、陽炎(かげろう)のごとく消えてしまうのだ。というパラドックスを、男性に理解して貰(もら)うのはかなり困難だろう。これまで女性によって書かれた優れた恋愛小説は数多く存在するが、世界的に特筆すべき恋愛論が見あたらないという、厳然たる事実もある。
男性はそれを女性の論理的思考の弱さだと考えがちだが、それは少し的外れだ。他のジャンルでは男性以上に鋭く論を展開できる女性はいるけれど、あえて恋愛を論じようとはしない。
封建社会においては仕方なかったにしても現代においても同様。論では恋愛を掴(つか)まえきれず、後追いにしかならないことを身体的に知っているからだ。だから小説やエッセイで、個別の恋愛事情を、主観的に提出(表現)する。俯瞰(ふかん)や分析に背を向けてしまうのだ。
それでも女性は恋愛論を読む。「恋愛という生命体」を腑分(ふわ)けするメス捌(さば)きに感嘆の声を上げながら、ふむふむなるほどと、過去に恋愛した人も、目下恋愛中の人も、恋愛論の優れた消費者にはなれるのだ。ただしそれは、慰めや納得や発見には繋(つな)がっても、決して「恋愛」そのものを充実させはしないのだが。
恋愛論とは、そうした宿命を帯びたタスクなのである。
さて、本書はプラトンの「エロス論」やスタンダールの「恋愛論」また、ロレンスの「セックスと美の関係」やトルストイの「心身二元論」などを踏まえ、小説の描写を具体的なサンプルとして示しつつ、作者自身の実感をそこに付与することで、およそ恋愛に関するあらゆる局面を探り、恋愛とは何かを実存論的に提示している。
「恋愛感情と生活感情」「狂気性と日常性」「プラトニズムとエロティシズム」という対立項を置きながら、それらは現実の人間の中で分かちがたく混沌(こんとん)としていることに言及し、恋愛論でありながら、論として整理分類できないものの魅力を伝えている。それは結果として恋愛賛歌にもなっている。
神と人間の架け橋としてのイエス。そのように「恋愛小説」もまた、狂気性に満ちた「恋愛感情」と日常的な「生活感情」の架け橋となる、という説は、恋愛小説をめぐる現象を正しく把握しているが、同時に本書もまた、プラトン以来の男性賢者による恋愛論と、「この世には二種類の人間がいる、今恋をしている人間と、していない人間だ」「すべての恋愛論は、恋をした男性の不安や不全感をエネルギーとして書かれたに違いない」などと直感で捌く、私のような感性人間との、架け橋にもなり得ている。
作者は本書が『陽水の快楽』から生まれたことを明かしているが、井上陽水の音楽の、およそ因数分解不可能な魅力に言葉で迫ったことと、恋愛というこれまた論で捉(とら)えることが困難なものに触手を伸ばしたこととは、同じ根を持つ衝動だろう。であれば、なぜ恋愛論は男性によって書かれるのかを、今後実存論的に解明して欲しい。
本書は私にとって、プラトン以来の恋愛認識における「欠落の発見」でもあった。
ALL REVIEWSをフォローする