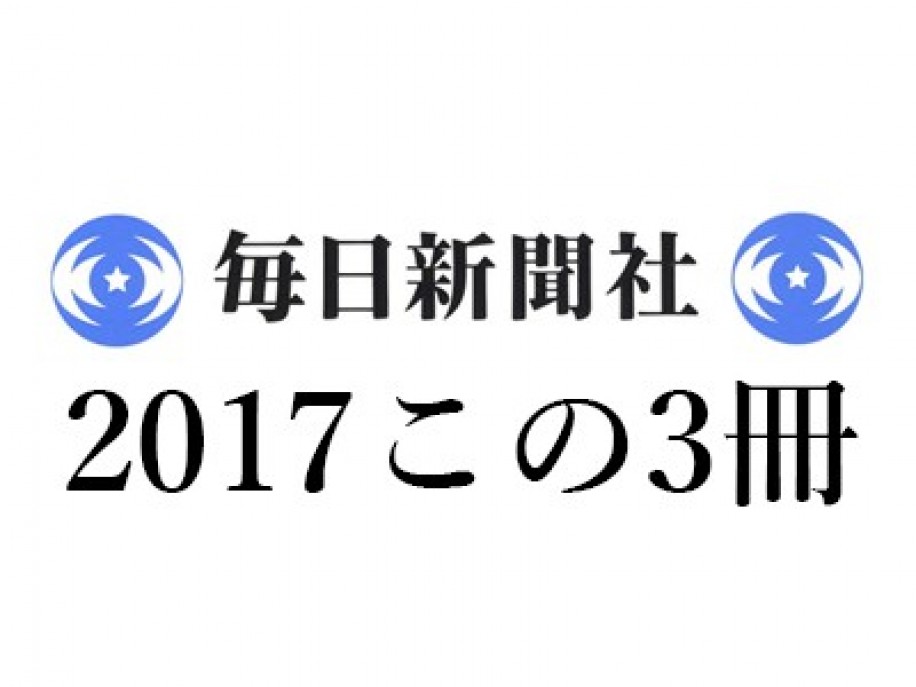書評
『欲望論』(講談社)
哲学的原理 総転回の試み
圧倒的な議論の密度。現代哲学のフロンティアのその先へと踏み出す、創造的な業績だ。二○一七年は竹田青嗣氏の『欲望論』二冊の刊行年として、記憶されるだろう。全体を貫くのは「ゴルギアス・テーゼ」。何ものも存在しえない/存在しても、認識しえない/認識しても、言語化されえない、という《懐疑論=相対主義の論理的原理》だ。哲学は古代ギリシャの昔から、この難題をめぐり苦闘してきた。竹田氏は『ソフィーの世界』のように、だがずっと本格的に、近代に至る哲学の歩みを語り直す。カントやヘーゲルの「完全解読」シリーズを書き継いできた著者ならではの手際である。
竹田氏が《一切の哲学的原理の、総転回の試み》の足がかりにするのは、フッサール、ニーチェ、ハイデガーの三人だ。フッサールは、独我論の方法をとりながら、間主観的な確信が生まれる条件を追究する。ニーチェは、対象は欲望相関的にあらわれると洞察する。ハイデガーは、存在が実存にとって意味をもつ機制を明らかにする。しかしほとんどの哲学者は、三人を理解しなかった。三人は世界の「本体」があると考えるのをやめ、実存的な確信のあり方を解明しようとした。ここにこそ、哲学の閉塞(へいそく)を打ち破る指針がある、と竹田氏は考える。
ゆえに、本書のキーワードは「言語ゲーム」だ。言語ゲームは後期ウィトゲンシュタインが着想した、世界の根底をなす人びとの営み。竹田氏はそれを、《本体論の完全な「解体」》の根拠とする。言語ゲームこそ、人びとが意味と価値を現に確信できるその前提だからだ。
本書の文体は独特だ。数行から数十行にわたる、断章の連なりからなる。ウィトゲンシュタインに通じるこの文体は、熟慮の末に選ばれたのだろう。緻密な論証を積み上げる哲学の専門論文のスタイルと異なるので、やや戸惑う。読み進むにつれ、大物の哲学者たちをつぎつぎねじ伏せていく力業に、ちょうどよいのだとわかってくる。
哲学は本来の使命を忘れ、病んでいる。ポストモダンやそれ以降の現代思想は、ゴルギアス・テーゼの変奏にすぎない相対主義に深く蝕(むしば)まれている。そう竹田氏は診断する。哲学を甦(よみがえ)らせ閉塞を突き抜ける原理を手にしようと、苦闘が始まる。
竹田氏のいう「欲望」とはなにか。フロイトやラカンが想定する、何か実体めいたものではない。実存の内的体験として、誰もが知る情動である。人間にとって大事な意味と価値は、この欲望と相関的に生まれているはず。その実態をつきとめ、フッサールとニーチェを越えることを、竹田氏は課題とする。
欲望相関性の考え方は、四○年ほど前に着想されたという。以来、哲学に目を向け、修練を積んで、現代哲学やポストモダンの迷宮を潜(くぐ)り抜けて来た。そして本書の執筆だけに、まる五年を要したという。これほど浩瀚(こうかん)で徹底した哲学の思索は、わが国にほとんど類例がない。しかも世界的なレヴェルに達している。もともと三巻の予定が、まず二巻まで出版された。続きを読みたいと切に願う。
第1巻「『意味』の原理論」は、ギリシャから現代まで哲学の展開と蹉跌(さてつ)を俯瞰(ふかん)する。その論旨の透徹ぶりに感嘆する。第2巻「『価値』の原理論」は、幼児の発達を事例に欲望の形成を素描する。一見ありがちな議論の根底に、フッサールとニーチェのモチーフがどのようにウィトゲンシュタインの着想と化学反応するのかが読みどころだ。真剣な読解を誘う大作の登場を喜びたい。
ALL REVIEWSをフォローする