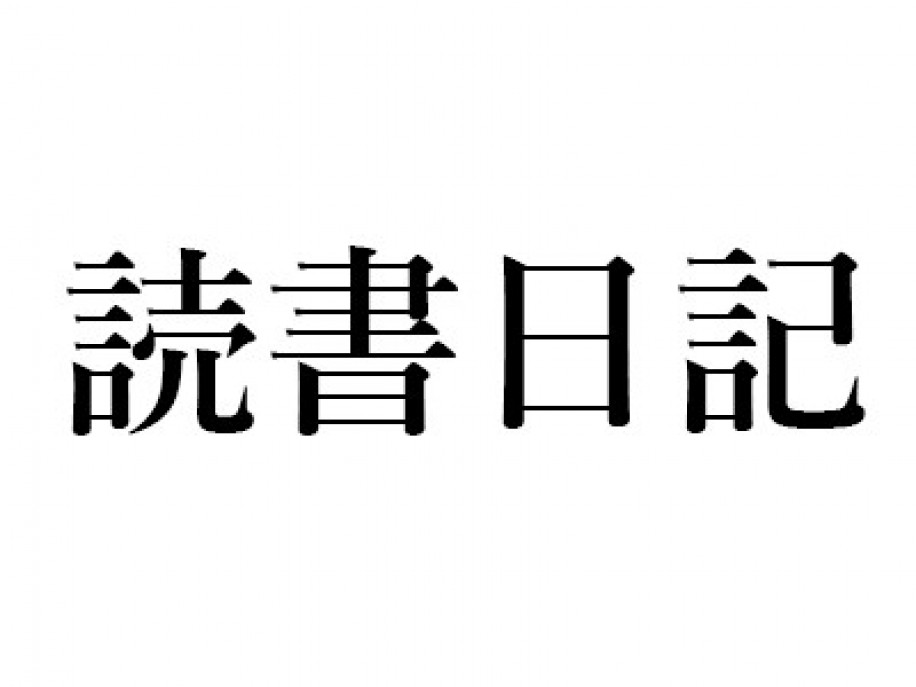解説
『山田風太郎明治小説全集 (4) 幻燈辻馬車』(筑摩書房)
「異次元の歴史」の風太郎ワールド
幻燈辻馬車。なんという見事なタイトルだろうか。鹿鳴館時代の東京の四辻に、薄ぼんやりとした幻燈に映し出されたような幽明定かならぬ一台の辻馬車が、戊辰戦争で死にそこねた会津藩町方同心の干潟干兵衛に御されて不意に姿をあらわすとき、そこには、いかにも過去にありそうな、それでいて、決してあったはずのない摩詞不思議な「異次元の歴史」、山田風太郎ワールドが現出する。
辻馬車の行くところ、薩長の大物や、自由民権運動の壮士、権力の密偵、さらには坪内逍遥や三遊亭円朝、幼き日の田山花袋など明治の実在の有名人が次々に登場し、それぞれ歴史年表に記載されたような事件に遭遇するが、もちろん、彼らは彼らであって彼らではない。彼らもまた実在の歴史からさまよい出て、「異次元の歴史」の中に迷いこんだ風太郎ワールドの住人なのだ。
その一方で、この「異次元の歴史」には、もう一つの世界すなわち、あの世からの閲入者も姿を見せる。西南戦争の田原坂で戦死した干兵衛の息子蔵太郎が、辻馬車に乗った一粒種お雛の「父!」という銀鈴のような叫びに答えるがごとくに、紺の軍服に白刃を引っさげて出現するのである。そればかりか、蔵太郎が呼ぶと、今度は、会津城の攻防戦のさなかに官軍の隊長に犯されて自刃した干兵衛の妻お宵までがあらわれてくる。
これら、実在してはいるが実在していない人物と、実在してはいないが実在している人物とが相まみえて「異次元の歴史」を織りなしてゆく出会いの場(トポス)、それがほかならぬ、干潟干兵衛の辻馬車なのである。そればかりか、この辻馬車自体もまた、実在と非実在の境目に位置している。現に、語り手は、そのことをちゃんと断っている。
東京の町には、もうかれこれ十年くらい前から、乗合馬車が走っている。つまり、このごろ円太郎馬車と呼ばれているやつだ。おえら方のお傭い馬車もある。この六月ごろには、新橋・日本橋間に鉄道馬車が走ることになっている。
しかし、昔の辻待ちの駕籠にあたるゆきずりの客を拾う辻馬車というのは珍しい。まったく無いわけではなく、それを営業にしている店も一軒か二軒あるにはあるが、むろん複数の馬車をそろえ、それも汚い幌をかけただけのしろものだ。
この記述は、最近、中公新書から出た斎藤俊彦氏の力作『くるまたちの社会史人力車から自動車まで』を参照するときわめて正確であることがわかる。つまり、明治の十年代であっても、日本には、乗合馬車や自家用馬車はあっても、ヨーロッパにあるようなクーペやベルリーヌなどの箱馬車スタイルの辻馬車はほとんど存在していなかったのである。なぜかといえば、辻で客待ちするタクシー的乗り物としては人力車という便利で安価なものが明治三年から存在し、ニッチをほとんど独占していたからであり、また価格の高い箱馬車では、辻馬車として客を乗せても、とうてい採算は取れなかったからである。辻馬車があったとしたら、語り手も言っているように、人力車とほぼ同じ構造の幌付き二輪馬車キャプリオレで営業するぐらいだが、これとて、せいぜい、ハイヤー馬車としてしか使い道はなかった。
したがって、現実には、明治の東京に箱型の辻馬車が走ってる可能性はほとんどなかった。いいかえれば、歴史的事実からすれば、辻馬車というのは非実在の乗り物だったのである。
だが、山田風太郎の筆にかかっては、この非実在の辻馬車がたちまちのうちに実在してしまう。さきほどの引用の続きを見よう。
それが、その親子馬車は、ちゃんとした自家用なみの二頭立ての箱馬車で、しかも個人営業らしい。その上、親子馬車と呼ばれているように、馭者は五十近い男だが、馭者台のそばにもう一つ小さな台を作って、可愛らしい女の子をチョコナンと乗せて走っているというので、人々の話題になった。
さらに、語り手は、用意周到に、辻馬車は、干潟干兵衛が、会津藩家老で落城後降伏し、のちに陸軍少将にまで出世した山川大蔵の弟、東京大学助教授山川健次郎の古い箱馬車を譲り受けたことにしている。いかにもありそうな話である。すなわち、本来なら実在しないはずの箱型の辻馬車が、実在の人物、山川健次郎を介することによって、あっと言う間に実在して、われわれの脳髄の中で、現実のどんな乗り物よりも確固たる存在を主張しはじめるのである。
そして、こうして実在しはじめた辻馬車が、会津の中・老年組の防衛隊の名にあやかって「青竜」と「玄武」と名付けられた二頭の廃馬同然の老馬に引かれながら、キイクル、キイクルと耳ざわりな摩擦音をたてて東京の町を走るとき、そのまわりでは、実在と非実在の人物がさながら走馬燈(ランテルヌ・マジック)のように次々あらわれて、われわれの記憶のスクリーンに幻影を投げかけ、現実の歴史でも、まったくのフィクションでもない、「異次元の歴史」が生み出されてくるのである。
この意味で、山田風太郎の小説、とりわけ、明治物とよばれる一群の時代小説の方法論は、干潟干兵衛の辻馬車に凝縮されているといっても決して言いすぎではないのである。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする