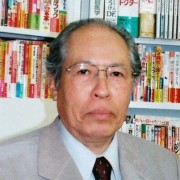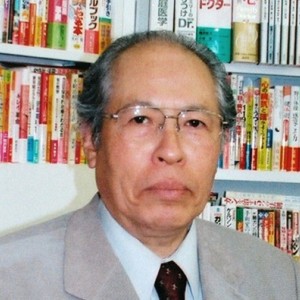書評
『日本遊戯思想史』(平凡社)
遊ぶ精神の変遷利用する権力
日本人の遊びといえば、古くは双六(すごろく)や百人一首、蹴鞠(けまり)や流鏑馬(やぶさめ)など、みやびな遊びが念頭にうかぶが、第2次大戦後からしばらくの間は、パチンコやゴルフ、麻雀、競馬などが遊びの代表で、ギャンブル化したものが多かったことは記憶に新しい。本書はこのような遊びの変遷を追いながら、日本特有の遊びの思想を探ろうとした労作である。中世のはやり唄の一節には、無心に遊ぶ子どもの姿を「遊びをせんとや生まれけむ」(子どもは遊ぶために生まれてきたのだなあ)とあるように、人間にはほんらい遊戯精神が備わっている。この考え方は、20世紀スペインの哲学者オルテガの、遊戯というものが人類の文化以前に存在し、文化に浸透し続けてきたという認識にほぼ一致するといえよう。
しかし、多くの遊戯は刺激を高めるために賭博化する宿命を帯びていた。著者は広く文献をあさりながら、公権カが賭博を取り締まりの対象としていく経過と、その一方で江戸時代の富くじのように、便宜的な財源として利用する二面性が生じたと指摘する。
第2次大戦中の政府は、戦意高揚の目的に子ども向けの双六や玩具まで動員した。カルタには「今に見ろ太平洋は日本海」といった文言まで飛ひ出し、青少年に影響を与えた。「遊戯具は本来、楽しく遊ぶためのものであり、決して戦争に赴くことを促す用具ではない」という著者の抗議には、好戦的ゲームの多いなか、耳傾けるべきであろう。
現代は電子ゲーム全盛だが、カジノ構想も浮上し、全体に市場中心主義が目立つ。日本人の遊戯精神は健全とは言いがたいことがわかる。
初出メディア
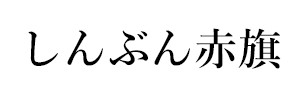
しんぶん赤旗 2014年12月21日
ALL REVIEWSをフォローする