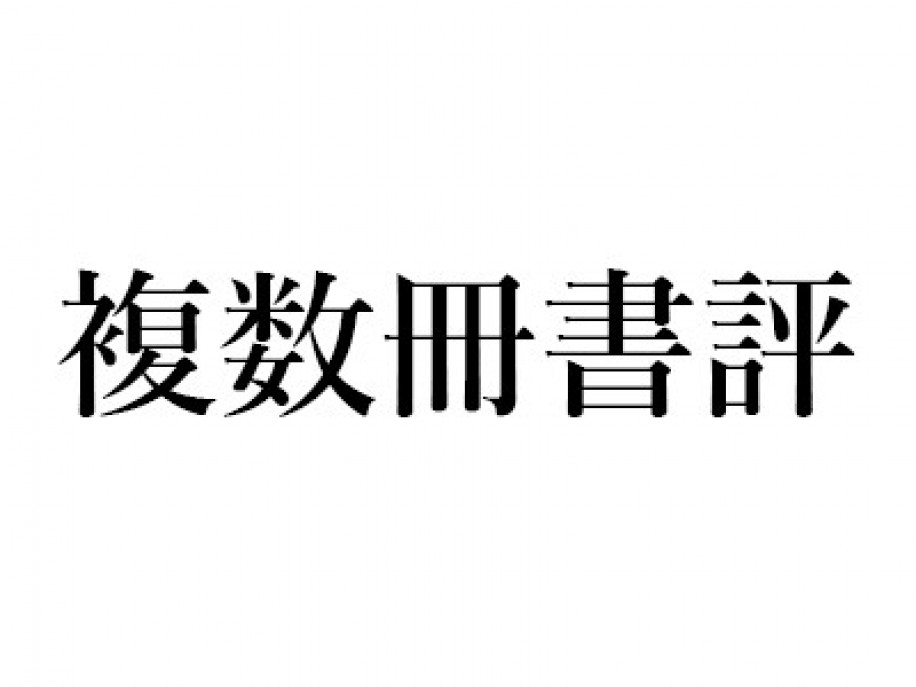書評
『この部屋に友だちはいますか?』(河出書房新社)
その小説は面白いですか?
そう質問されたら、もちろん、「とても面白いよ」と答えるな。ああ、「その小説」ってのは三浦俊彦の『この部屋に友だちはいますか?』(河出書房新社)なんだけれどね。
三浦俊彦の小説について噂は聞いていたし、その噂っていうのはこの本の帯に書いてあるように、「これまで見たことのないユニークなもの」というやつで、読んでみようかと思ったけど、ハーディングやオクサナ・バイウルを見なくちゃならないので、いままで読む機会がなかったのだった。
ところで「これまで見たことのないユニーク」という言葉からぼくが想像していたのはアメリカ小説で、アメリカにはいまでも「ユニーク」としか言いようのない超変な作品を書いてる作家がけっこういて、彼らはコマーシャリズムなんかクソクラエ!で、考えようによっては古い前衛(変な言葉だけど)かもしれないが、とにかくそういう作家もまた平気で生き延びられる不均等な場所がアメリカなわけで、そういうものを予想していたら、そういうものではなかったのだった。
とはいっても、日本の、それも「純文学」という基準からいうと、そうとう変わっているのは事実なんだけど。
この小説の「テーマ」は「友情」で、「友情」というとぼくは武者小路実篤の『友情』を思い出すのだけど、あれもそうとう変な小説だった。「友情」というやつは「愛情」に輪をかけて扱いにくく、どんなに真面目に書いても「バカみたい」に見える可能性がおおきくて、実篤の『友情』もほとんどバカ丸出しである。しかし、そこから先が実篤の只者ではないところで、『友情』を読んでいると、この人はタダのバカではなく、確信犯的な超バカではないかという気さえしてくるのだが、その日本文学にとっての危険(?)なテーマに挑んでみせたところに、まず作者のセンスのよさを見なくちゃいけないだろう。作者が実篤の『友情』を読んでいるかどうか定かではないが、読めばゲラゲラ大笑いして、好きになることだけは間違いない。
そうはいっても、テーマなんてのは小説を書く上ではどうでもいいことなので、どうでもよくないことについて触れてみようね。もちろん、文体。この小説の「売り」は文章で、読んでいると、作者の苦心や思惑がしのばれてなんだかシンミリとしてしまう。とりあえず、どんな文章かっていうとだね、「朝は輝かしきいま一日の予感に悦び震え、昼は公園の鳩に仔猫に生命の尊さ愛らしさを慈しみ、夕は窓外ヘッドライトの流れに人類の未来活力臨み見て胸熱く高鳴り、夜は家々門灯の明りに無数の家庭幸福感受して五臓六腑ことごとくときめく。……。食べては舌鼓法悦に躍り、出しては胃腸の確かさ硬軟形状頼もしく、着ては彩なる社交応接綾錦の自信溢れ零れ、脱いでは膚の滑らかに気漲(みなぎ)る」。
というようなのが典型で、リズムを刻みながらクレッシェンドしていくのだけれど、読者によっては筒井康隆の小説や何人かの現代詩人の作品(たとえば、ねじめ正一の)を連想するだろう。その連想は決して間違っているわけではなく、三浦に先行する作者たちも、日本語で小説を書くとどうしてあんなに文章が単純になってしまうのか(日本語だけでもないのかもしれないし、散文だけでもないのかもしれないが)と悩み、音楽的な散文を心がけたのだった。そうした散文を作るために必要なのは作者の「耳」の良さだが、文末への繊細な心配りを見ればこの作者が優れた「耳」を持っていることに疑いの余地はないようだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする