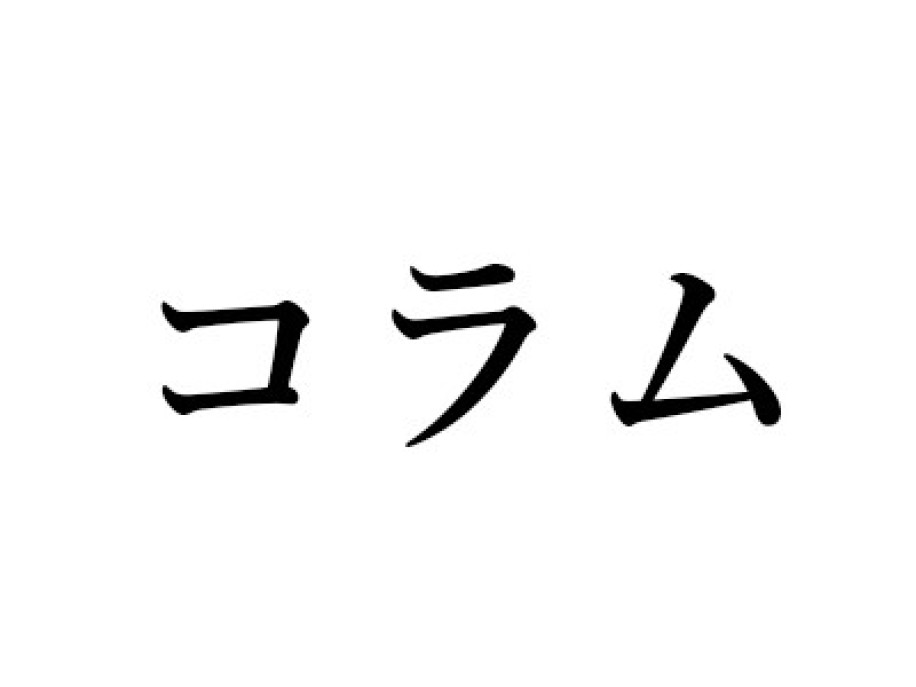解説
『侯爵サド』(文藝春秋)
これまでのサド観をくつがえす
正直に白状すると、この作品を文藝春秋の編集者氏から勧められるまで、私は藤本ひとみの小説を一つも読んだことがなかったのである。たしかにヴァンデの反乱のような、日本ではとんとなじみのない題材をもとに小説を書き上げた女流作家がいるということは知っていた。だが、わざわざ金を払ってまで、小説を読もうという気持ちは起こってこなかったのである。だから、編集者氏に対談を持ちかけられたときには、読んでみておもしろかったら、という条件をつけた。
で、読んだ結果はというと、これが驚きの一語。いや、すごいね。日本にも、「論理」でもって小説を書ける作家が出てきたんだ!時代は変わった、と思わざるをえなかった。
では、この「論理」というのはなんなのか? それは、「事実」の叙述ではなく、思想から生まれる論理と論理の戦いそのものからカタルシスを導きだすことである。
『侯爵サド』は、シャラントン精神病院に幽閉されていた晩年のサドが、警視総監フーシェの通達によって、操行調査という名目で院内裁判にかけられ、過去の行いをもう一度あらいざらい暴かれる一種の法廷小説だが、この法廷小説を突き動かしている論理とは、途中までは、次の文章に書かれている三つの立場に要約される。
院長コラールと警視総監デュボワの意を受け、侯爵サドを犯罪者と認定すべく審問項目を用意した調査団に対し、理事長ドゥ・クルミエは病人説に絶対の自信を持っていた。侯爵本人は、あくまで冤罪に泣く常人たる立場を主張するつもりでいる。
この図式は、現在、少年の凶悪犯罪が起きるたびに蒸し返される論理の対立と基本的に同じだといっていい。すなわち、法律で定められた社会秩序に違反した者は、いかに異常な犯罪であろうとも、すべて犯罪者であり、しかるべき罰を受けるべきだとする検事の論理。一方は、異常な犯罪者は判断力に欠陥があるゆえ、犯人というよりもむしろ病人であり、刑罰ではなく治療が必要であるという弁護士の論理。そして、そのいずれによっても自分は理解されておらず、「犯罪」というかたちで表現した思想が裁かれるのは不当だと考える被告の論理。
したがって、この三つの論理が戦いを繰り広げる精神病院内の「サド裁判」の場面は、現代の異常な事件の裁判の構造そのものを象徴していることになる。おそらく、著者にも、部分的には、そうした意図があったにちがいない。
その証拠に、裁判において、蒸し返されるサドの過去の同じ悪行が、それぞれの論理によってまったく勝手な角度から裁断される場面は、正確に現代の戯画となっている。裁判所で、サドと同じように、次のように叫ばなかった少年犯罪者がいるだろうか?
「牢がなんだ。私は、病人と言われるよりは、悪人と言われることを選ぶ。その方が私らしいのだ」「確かに私は、神になりたかったのかもしれない」
もっとも、著者は現代の戯画を描くためにこの小説を書いたのではない。著者が表現したかったもの、それは、圧倒的な迫力で、身勝手きわまりない論理を説き続けるサドその人の姿である。藤本ひとみの描くこのサドは、じつに魅力的だ。私は、多少ともサドの伝記を読んできたから、サドのもてあそぶ理屈は承知しているが、それが藤本ひとみ版のサドの口から発せられると、なんとも生き生きした言葉となり、そこからサドという人物の、矮小にして偉大な姿が浮かび上がってくるのだ。サドという人間とその思想のエッセンスを知りたかったら、膨大な伝記群を読むより、藤本ひとみのこの小説を一冊読んだほうが、はるかに鮮明な映像を得ることができる。おそらく、時代が一九六〇年代の後半だったら、小説はこれだけで傑作となりえただろう。
だが、時代は二十世紀のどんづまりである。この「反抗者サド」のイメージがいかに魅力的であろうと、それだけでは、時代にふさわしい傑作とはならない。まだ、なにかが必要なのである。
そのなにかを、著者は、第四の要素というかたちで導入する。フーシェの秘書という名目で、サド裁判に送り込まれてきた女性、ダニエル・サブロニエールの存在である。ダニエル・サブロニエールは、サドによって牢獄に放りこまれた女中アンヌ・サブロニエールの娘であり、サドの隠し子である。
この認知されざるサドの娘という存在が、三者の論理の戦いを一挙に無効にしてしまうほどの起爆力を秘めている。なぜなのだろうか?いかなる理由で、サドの娘が、検事や弁護士の論理ばかりか、サドの論理をも根底から覆して、最終的に法廷小説を「文学」へと変える要素となりえているのか?
それはサドの娘、ダニエル・サブロニエールには、著者の「私」が凝縮されているからである。つまり、寄る辺なき存在として、なによりも親の愛を求めながら、ついにそれを与えられなかった子供、いいかえれば、中絶された胎児と同じ程度にしか顧慮を与えられなかった子供の悲しみと怒りという、著者の全作品の底流に流れるトラウマが、さながら大天使ミカエルのごとき仮借なき審判者となって噴出し、六〇年代の「反抗者サド」を、九〇年代の「ただの老いぼれ」に格下げしてしまうのである。
その意味で、『侯爵サド』はそれまでのサド観をくつがえす画期的な作品であり、著者の最初のピークをなす代表作となっているのである。藤本ひとみからは、ここ当分、目が離せそうにない。
ALL REVIEWSをフォローする