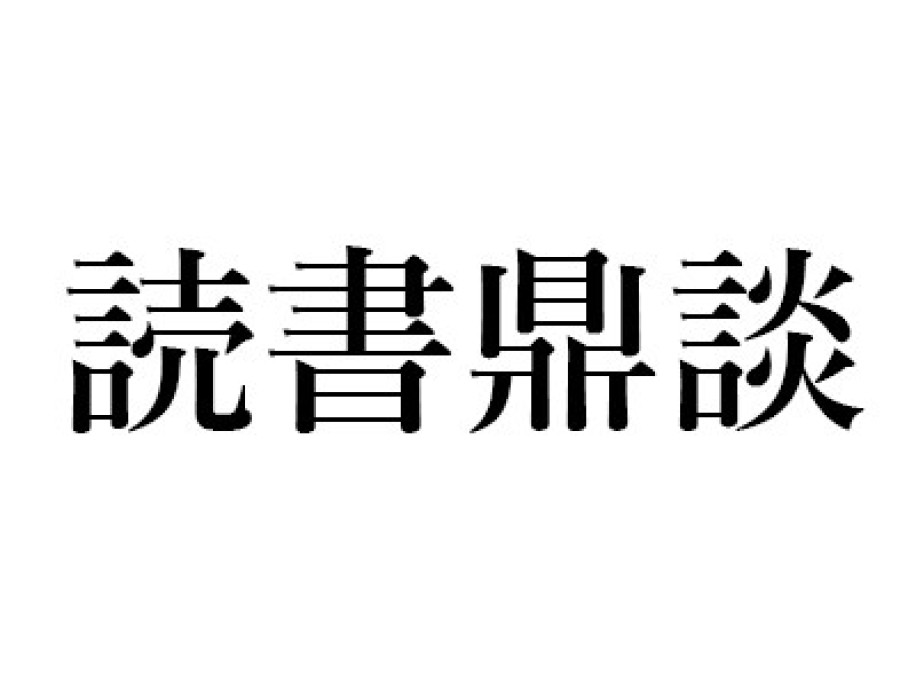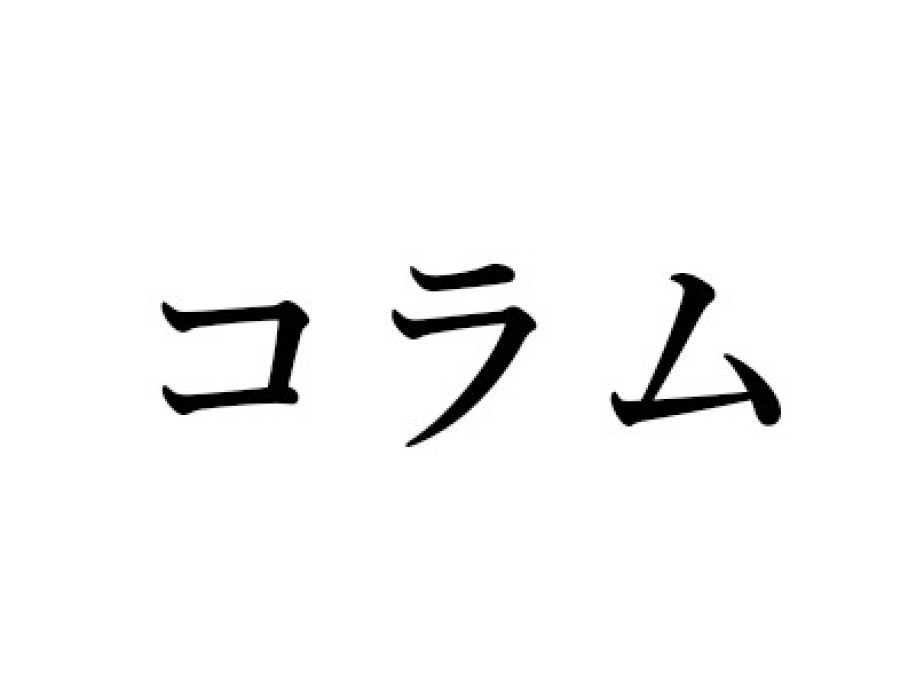解説
『偏食的生き方のすすめ』(新潮社)
いきなりですが、(『偏食的生き方のすすめ』の)百八十一ページに注目していただきたい。
中野翠の名が出て来る。著者は『人生を〈半分〉降りる』という本の巻末解説を中野翠に依託したのだが、その出来あがりを見て、こう感じたというのだ。「私に遠慮していて中野さんらしい切れ味がない」。それでさっそく「そう彼女に伝える手紙」を書いたというのだ。
はい、確かにそういう趣旨のおたよりを頂戴しました。数行の文面だったけれど、冒頭の一言だけはハッキリとおぼえている(たぶん一生忘れないと思う)。それは、
「失望しました」
というものだったのだ。いきなり、これ。ズバッと、これ。私も長い間、ひとの書いた本の「解説」やら「書評」やら「推薦文」やらを書いて来て、著者の方がたから「ありがとう」という礼状をいただいたことはあるけれど、「失望しました」は初めてだ。
一瞬、気分が落ちこんだし、シャクにもさわったのだけれど、すぐに……そうですねえ、三分後くらいにはおかしくなってしまった。妙にわくわくした。「うーん、なるほど変わった人だなア。そう来たか」と。
返事を出したくなった。こういうおたよりをいただいても私は気を悪くしていないということだけ短く伝えたかった。しかし、それをどう書いたらいいのだろう。普通は「御期待に添えなくてごめんなさい」とか「力不足で申し訳ない」とか謝まるのだろうが、私はちっとも悪いとは思っていないのだ。手抜きしたおぼえはないし、謝まる筋合はない。何とか謝まったりせずに、私の気持を正しく伝える言葉はないものか……。それで思いついたのが、
「残念です」。
その時は真面目な気持でハガキにそう書いて送ったのだけれど、日を追って何だかしみじみとおかしくなって来た。中島義道という人物に対しても自分自身に対しても。「失望しました」と「残念です」。両方嘘いつわりなく、スッキリしていて好もしい言葉だけれど、ひとが見たら、ずいぶん素っ気ないやりとりと思うかもしれない。珍味の体験をしたと思った。
とまあ(短く書くつもりが思いのほか長くなってしまった)……百八十一ページの一節にはそんな秘話もあったのだ(それなのに今回また「解説」を依託されたというのは、いったいどういうわけだろう。失望はしたが、絶望までには至らなかったということか。私にとっては幸か不幸か)。
私は仕事の裏話(特に業界の人間関係の話)を書くのがなんとなく厭で、この話は今までどこにも書かないで来たのだけれど、他ならぬ本書の「解説」という場だったらOKだ。著者の人物像が鮮かに出ていると思うし、本書のテーマにもかかわりのあることだし。そう思って今回ここに初めて書いた(ちなみに、私はまだ一度も著者と会ったことはない)。
さて、本題の「解説」ですが……この本自体が中島義道という並はずれて理屈っぽく、また理屈力(論理力と言ったほうがいいのか)の強い人による自己解説の書なのだ。このうえさらに私が「解説」を加えるなんて、いわゆる「屋上、屋を架す」というようなもので、どだい無駄というか野暮というか。
私にできることは少ない。思い切って本書の発散する〈笑い〉に的を絞って書いてみよう。哲学者の書でありながら(いや、違う。ほんとうは哲学者の書ゆえに、なのだ!)この『偏食的生き方のすすめ』(新潮文庫)は、圧倒的におかしい。最高に笑わせてくれる。ほとんど全ページ、「モレなく」と言っていいくらいヘンでおかしい。やっぱり珍味のおかしさである。
話題は食べものばかりではなく私生活の全般に及んでいるのだけれど、いわゆる「食わず嫌い」を主題に据えて、こんなにも執拗にして軽快に、そして深刻にして軽妙につづった読みものは珍しいのではないか。少くとも私は、他に知らない。執拗さと軽快さが、深刻さと軽妙さが、両立しうるという事実に驚かされる。
私が一番笑ったのは四月の章あたりから出て来る、ストンという妙なリズムだ。出版社とのトラブルをネチネチと書き連ねたあと、唐突に「嫌いな食べもの」の話に変わる。例えば、こんなふうに。
「シャコは巨大なダンゴムシ(石の下などに丸くうずくまっているもの)のようで不気味であるが、なぜか食べられる。大好きなエビの形態圏に接しているからかもしれない。エビが私を救ってくれているのかもしれない」とストンと転調するのだ。
私はそのストンという感じが好きで好きで。まるで、今まで編集者相手に本のことで一席ブッていた人が、突然クルリと振り向いて「シャコはねえ」と語り出したかのようじゃないか。話題はガラリと変わるのに理屈っぽさだけは変わらないところもおかしい。巧まざる(実は巧んでいるのか?)おかしさだ。
さらに次のようなイマジネーション――。
(次ページに続く)
中野翠の名が出て来る。著者は『人生を〈半分〉降りる』という本の巻末解説を中野翠に依託したのだが、その出来あがりを見て、こう感じたというのだ。「私に遠慮していて中野さんらしい切れ味がない」。それでさっそく「そう彼女に伝える手紙」を書いたというのだ。
はい、確かにそういう趣旨のおたよりを頂戴しました。数行の文面だったけれど、冒頭の一言だけはハッキリとおぼえている(たぶん一生忘れないと思う)。それは、
「失望しました」
というものだったのだ。いきなり、これ。ズバッと、これ。私も長い間、ひとの書いた本の「解説」やら「書評」やら「推薦文」やらを書いて来て、著者の方がたから「ありがとう」という礼状をいただいたことはあるけれど、「失望しました」は初めてだ。
一瞬、気分が落ちこんだし、シャクにもさわったのだけれど、すぐに……そうですねえ、三分後くらいにはおかしくなってしまった。妙にわくわくした。「うーん、なるほど変わった人だなア。そう来たか」と。
返事を出したくなった。こういうおたよりをいただいても私は気を悪くしていないということだけ短く伝えたかった。しかし、それをどう書いたらいいのだろう。普通は「御期待に添えなくてごめんなさい」とか「力不足で申し訳ない」とか謝まるのだろうが、私はちっとも悪いとは思っていないのだ。手抜きしたおぼえはないし、謝まる筋合はない。何とか謝まったりせずに、私の気持を正しく伝える言葉はないものか……。それで思いついたのが、
「残念です」。
その時は真面目な気持でハガキにそう書いて送ったのだけれど、日を追って何だかしみじみとおかしくなって来た。中島義道という人物に対しても自分自身に対しても。「失望しました」と「残念です」。両方嘘いつわりなく、スッキリしていて好もしい言葉だけれど、ひとが見たら、ずいぶん素っ気ないやりとりと思うかもしれない。珍味の体験をしたと思った。
とまあ(短く書くつもりが思いのほか長くなってしまった)……百八十一ページの一節にはそんな秘話もあったのだ(それなのに今回また「解説」を依託されたというのは、いったいどういうわけだろう。失望はしたが、絶望までには至らなかったということか。私にとっては幸か不幸か)。
私は仕事の裏話(特に業界の人間関係の話)を書くのがなんとなく厭で、この話は今までどこにも書かないで来たのだけれど、他ならぬ本書の「解説」という場だったらOKだ。著者の人物像が鮮かに出ていると思うし、本書のテーマにもかかわりのあることだし。そう思って今回ここに初めて書いた(ちなみに、私はまだ一度も著者と会ったことはない)。
さて、本題の「解説」ですが……この本自体が中島義道という並はずれて理屈っぽく、また理屈力(論理力と言ったほうがいいのか)の強い人による自己解説の書なのだ。このうえさらに私が「解説」を加えるなんて、いわゆる「屋上、屋を架す」というようなもので、どだい無駄というか野暮というか。
私にできることは少ない。思い切って本書の発散する〈笑い〉に的を絞って書いてみよう。哲学者の書でありながら(いや、違う。ほんとうは哲学者の書ゆえに、なのだ!)この『偏食的生き方のすすめ』(新潮文庫)は、圧倒的におかしい。最高に笑わせてくれる。ほとんど全ページ、「モレなく」と言っていいくらいヘンでおかしい。やっぱり珍味のおかしさである。
話題は食べものばかりではなく私生活の全般に及んでいるのだけれど、いわゆる「食わず嫌い」を主題に据えて、こんなにも執拗にして軽快に、そして深刻にして軽妙につづった読みものは珍しいのではないか。少くとも私は、他に知らない。執拗さと軽快さが、深刻さと軽妙さが、両立しうるという事実に驚かされる。
私が一番笑ったのは四月の章あたりから出て来る、ストンという妙なリズムだ。出版社とのトラブルをネチネチと書き連ねたあと、唐突に「嫌いな食べもの」の話に変わる。例えば、こんなふうに。
「シャコは巨大なダンゴムシ(石の下などに丸くうずくまっているもの)のようで不気味であるが、なぜか食べられる。大好きなエビの形態圏に接しているからかもしれない。エビが私を救ってくれているのかもしれない」とストンと転調するのだ。
私はそのストンという感じが好きで好きで。まるで、今まで編集者相手に本のことで一席ブッていた人が、突然クルリと振り向いて「シャコはねえ」と語り出したかのようじゃないか。話題はガラリと変わるのに理屈っぽさだけは変わらないところもおかしい。巧まざる(実は巧んでいるのか?)おかしさだ。
さらに次のようなイマジネーション――。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする