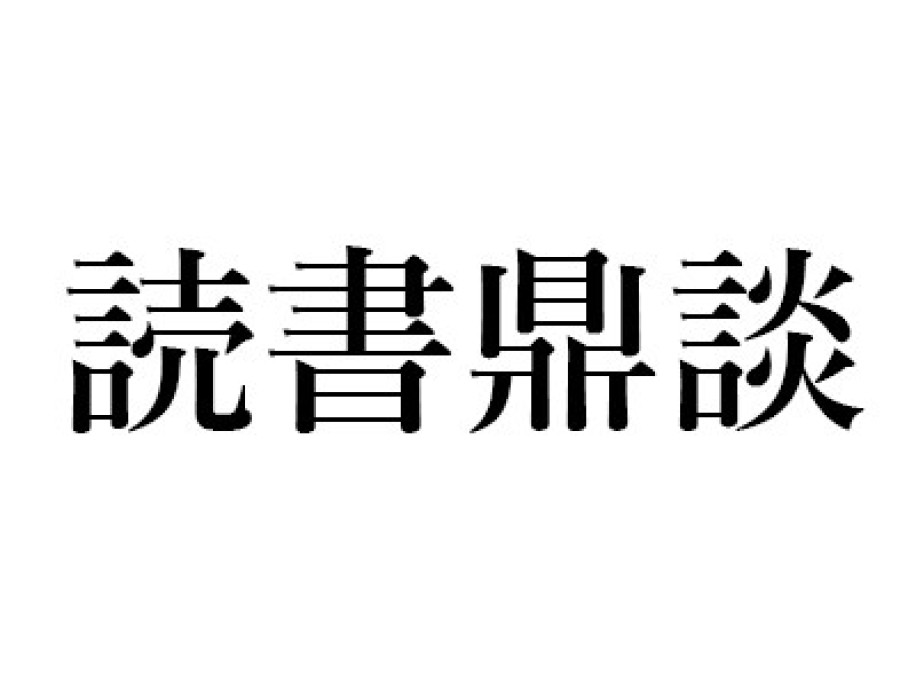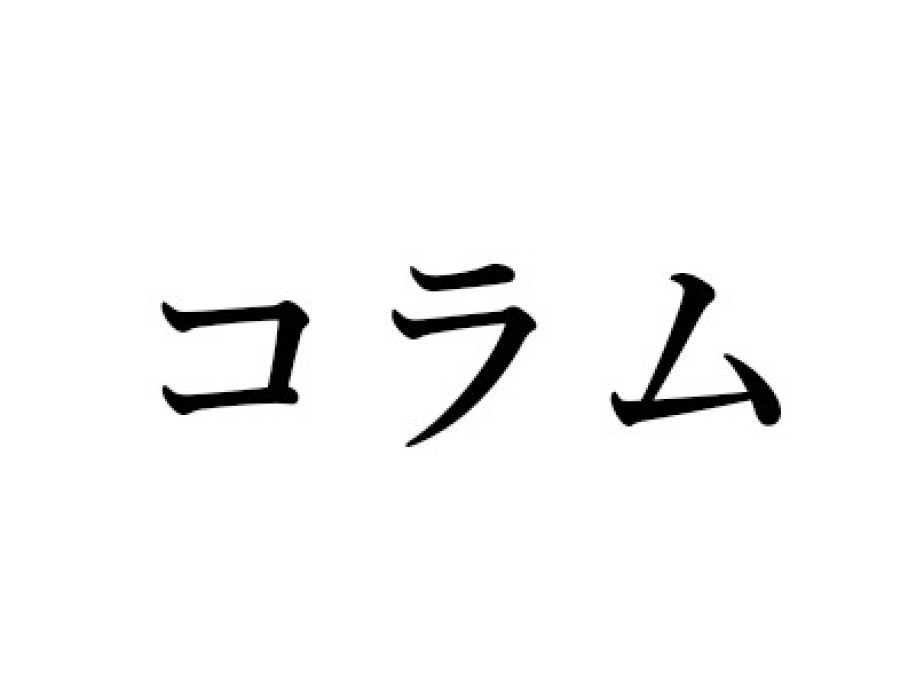解説
『偏食的生き方のすすめ』(新潮社)
「鳥は羽毛があるからいいので、羽毛をむしってしまうと爬虫類そのものだ。その『かたち』は不気味である。白鳥やダチョウが恐竜によく似ていることは誰の目にも明らかだが、鳥の『顔だち』と恐竜の『顔だち』はほんとうによく似ていると思う」
「タラコや数の子は嫌いではないが、子持ちカレイや子持ちシシャモのようにそれが母体にへばりついているのは陰惨な感じがして食べられない。いかにも母親と子宮の中の胎児とを一緒に食べる感じがするからイヤなのだ」
「牡蠣は好きであるが、大きな牡蠣はイヤである。目玉か睾丸を食べているようで気持ち悪い」
「『卵』という漢字は卵の内部構造をそのまま示していて、グロテスクだなあと再確認する」
……まあ、ね。そう言われれば確かにそう。きっと誰もがウッスラと感じている。けれど生きるためには、楽しく生きるためには、そういう感受性は抑えぎみにしたほうがいいと思い、「まっ、いいか」とやりすごす。生あるものはことごとくグロテスクを免れないことを暗黙のうちに察しているのだ。言っても仕方がないような無駄なこと、損なことには興味を持たないのだ。
ところが著者には「まっ、いいか」が無い。追及の手をゆるめない。グロテスクへの感受性を研ぎ澄ます。嬉々としてそのグロテスク性と、それに怯える自分の姿を活写するのだ。私に言わせれば、そこが哲学者らしいところ。無駄を無駄と思わない。つまり一種の馬鹿というか酔興というか。
私はその馬鹿馬鹿しいような情熱――落語の「小言幸兵衛(こごとこうべえ)」よりはスペインの「ドン・キホーテ」に近そうな情熱に、思わず笑い出してしまう。そこには何か、懐しさのような感情も混じっている。子どもの感受性と直結しているような感じがするのだ。研ぎ澄まされた稚気、といったものを感じるのだ。
そのこととどういう関係があるのか自分でもよくわからないが、私は次のくだりに、「あっ」と思った。
「美の求道者は『醜いこと』には無関心なのだ。醜い光景には心の蓋をして、さっさと茶室や料亭や高級ホテルに引っ込めばそれでいいのである。だが、偏食家は醜いことを『求める』者だから、こうした身のまわりの醜さに関心が集中し、心はずたずたに切りきざまれ、喘(あえ)ぎ喘ぎたどり着いた茶室で心を落ちつけることはできない」
「美の求道者は美しさと同じように醜さにも敏感であるわけではない。むしろ醜さに鈍感な者が多い。美がよりよく見えるようにするために、醜を見ないようにする技術を体得した者が多い。これは最近の貴重な発見である」
これは私にとっても貴重な発見だった。日頃ウッスラと感じていたことが、この文章によってカチッと焦点が合って、ハッキリと見えたという感じがした(もの凄く下世話な話で言うと、私が女性誌にうまくなじめない理由はそこのところにあるような気がしたのだ。私はオシャレな世界が好きだけれど、その方面のスター文化人を見ていると、なんだか小さな世界に自足しているようで、いつもイラつくのだ。そうかあ、私はオシャレに憧れながらも「醜を見ないようにする技術」に欠けているというわけかあ。やっとわかった)。
私もいささか偏食的人間だが、著者にあって私に決定的に欠けているものは執拗さと厳密さだ。しつこさとこまかさと言ってもいい。だからこそ著者は「まっ、いいか」で生きられないわけだが、私は「まっ、いいか」で生きられる。しつこくてこまかい人は嫌われがちなものだが、著者のそれは常識の範囲を突破するほどの高水準に達しているので、思わず笑わされてしまうのだ。
〈笑い〉の基本は「意表をつく」ということだ。人びとの思い込みや固定観念や常識を打っちゃってみせるところから生まれるのだ。「ぼくは偏食人間」と居直った瞬間から、著者はハツラツたるギャグライターになったと言ってもいい。著者の心からの叫び、大真面目な発想、真剣な感慨……すべてが「まっ、いいか」で生きている人間にとっては「意表をつく」ものになるのだから。
私はたいせつなことをこういう形で語れる著者を、独創的で風変わりな形で大人になった人だなと思う。そして、そこに至るまでの苦痛の歴史を、ちょっとだけだが、思う。
だから、十二月の章の携帯電話少女の話には心を揺さぶられずにはいられなかった。
おざなりな対応をする少女に「すべての人に注意するんです。あなたには想像もつかないと思いますけど、こういう人間もいるんですよ」「注意したときにあなたが私の言葉を無視したことに腹を立てたんです。なんで私に言葉によって答えないんですか?」と詰め寄る著者は立派だ。
たかがケータイ、たかが女の子、たかがゆきずりの関係なのに、著者は自分の全体重を乗せて会話を成立させようとしている。その立派さは、極度の偏食的人間(たいていの人が平気でいられるものでも、苦痛と不快の種になる)ゆえに余儀なくされたものなのだけれど。
やっぱり特権的な苦しみを知る人でなければ特権的な喜びも得られないものなのだ。
泣きわめいていた少女が最後には駅長室の外で著者を待っていて、「おじさん、おもしろい人だから連絡先教えてください」と言った。こういうことこそコミュニケーションと言うのだ。
「まっ、いいか」で暮らしている人は、たぶん、こういう特権的瞬間を味わうことはできないのだろう。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする