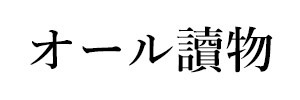選評
『不時着―特攻 「死」からの生還者たち』(文藝春秋)
日本推理作家協会賞(第58回)短編部門・評論その他の部門
受賞作=日髙恒太朗「不時着」(評論その他の部門)/他の候補作=高原英理「ゴシックハート」、浜田雄介「子不語の夢」、村上貴史「ミステリアス・ジャム・セッション」、吉田司雄「探偵小説と日本近代」(評論その他の部門)/他の選考委員=京極夏彦、桐野夏生、藤田宜永、宮部みゆき、北村薫(立会理事)/主催=日本推理作家協会/発表=「オール讀物」二〇〇五年七月号死を見つめる目
『不時着』(日髙恒太朗)は、これまでに書かれた陸海軍の特攻隊についての書物の中でも屈指の一冊、迷うことなく受賞作に推した。作者は、〈仕事の行きづまり、体調の不良、家族を捨てたという呵責の思い〉から、死場所を探しながら放浪をつづけていた。つまり自分で自分に死刑台へ登るよう命じたわけだが、あるとき、同じような状況に追い込まれていた特攻隊員の存在に思いあたる。作者の場合は、死刑の宣告を自分で解除することもできなくはないが、特攻隊員にはそれができない。命令は絶対である。そこで作者は、〈特攻隊員に選抜され、基地を飛び立ち突入するそのときまで、いわば死刑台の階段に足を乗せ、そのステップを一歩一歩踏みしめながら登っていくとき、彼らは何を思ったのか、何を思ったのか。それを知りたい――〉と思うようになった。
とりわけ作者は、死ねなかった特攻隊員の事情に深い関心を寄せる。「死なずにすむならそうしたい」という作者の切実な思いがそうさせたのだ。
普通ならば、カクカクシカジカであったという事実を得たところで、読者の仕事はおしまいだ。もちろん事実を知るだけでも大したことなのだが、本書では、カクカクシカジカでこうだったが、その結果、作者と「死」の距離はどうなったかという物語がつく。解明される客観的な事実と作者の生死のかかった物語――この二重の構造が、本書にいささか陰鬱だがそれでも香しい文学精神を吹き込んだ。証人から証人へと聞き込みをつづけて行く追跡の過程にも上質の推理小説を読むような興趣が溢れている。
さて、作者の突き止めた事実はどうであったか。たとえば、軍は、昭和十九年には、約十五万人の特攻要員を採用する。作者の言葉を借りれば、〈「消耗品養成」という言葉でしかいえないような予科練の大量採用をくり返した〉
そして特攻隊員に指名されたときの若者たちの心境は、〈自分の名前が出てこないように、胸のなかでひたすら祈っていた。だがその願いもむなしく自分の名前が告げられた。一瞬目の前が真っ暗になった。/カアッと熱い血がのぼり、一瞬それが冷水となってザアーッと音を立てて引くような名状しがたい状態に置かれた。/自分の存在が、足下の一匹の蟻にも及ばないように思えてみじめだった。/おえら方に向かって「お前らはなんで征かんのか? この腰抜けめ!」とあたりかまわずわめきたい衝動に駆られた〉
えらい人は生き延びて、若者だけが死なねばならないという不条理(ばかばかしさ)、そして命中率が一~三パーセントという愚挙。
ついに作者は怒り出し、そして、この若者たちの口惜しさを書かないうちは死んでなんかいられるものかと発奮する。このあたりの感動は筆舌に尽くしがたいが、おびただしい死の向こうに生の明かりを観て、作者はここへ生還を果たした。死を凝視して怯(ひる)まぬ作者の度胸に脱帽する。
【この選評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする