書評
『大隕石衝突の現実―天体衝突からいかに地球をまもるか』(ニュートンプレス)
“忘れているだけ”の宇宙災害に迫る
中国古典『列子』に有名な「杞憂(きゆう)」の話がある。杞の国の人は、天が落ちてくると心配しただけではない。日・月・星の落下も憂えている。しかし、古代中国人は「日・月・星は気が積み重なったものの中にある輝きにすぎない」といい、「墜(お)ちしむるも、また中傷する所有る能(あた)はず(墜ちてきても危害の生じようがない)」と、なだめた。太古の昔から、隕石(いんせき)落下による被害は笑い話のたぐいであった。しかし、それは違うらしい。私は江戸時代における隕石落下の古文書を調べてみて、それを確信した。東京だって隕石に直撃されている。近くは、1823年に、大音響とともに、早稲田に隕石が落ちて、町医者の玄関の屋根を破壊している。人間の寿命が80年前後と短く、忘れてしまうだけだ。隕石というものは、我々の想像以上に、頭上に降り注いでいる、と、私は古文書の研究から気づいた。そこへきて今年2月15日の、ロシアへの隕石落下である。世界中で、宇宙落下物からの防護=スペースガードの認識が高まった。
本書は、宇宙落下物、天体衝突の問題について、「はやぶさ」のプロジェクトチーム・リーダーであったJAXAの吉川真氏ら、日本スペースガード協会のメンバーが、まったく現実的に、科学的根拠に基づいて論じている。きちんと計算された具体的数字の根拠が並んでいて、目からウロコの記述が多かった。地球軌道の周辺には、大きなものから数メートル以下のものまで、無数の小惑星があって、現在60万個以上みつかっている。「現在、発見されている小惑星の地球衝突を心配する必要はない」ものの、無数にあるわけだから、未発見の天体が不意に現れて地球に衝突する危険は笑い事では済まないことがよくわかった。米国偵察衛星などの観測によると、直径5m前後の広島型原爆と同じ破壊エネルギーを生じる天体(隕石)が毎年1個は地球に衝突しているらしい。10mのものも数年に一度落ちている。しかし、10mまでの大きさなら地球の大気の抵抗で爆発し、破片の隕石がパラパラ落ちてくるだけ。直撃されない限り、大きな被害はない。
問題は直径20~30mを超える隕石である。50年から100年に一回の確率で落ちてくる。これは幅数十キロから100キロ四方に災害をもたらす。さらに数万年に一回の確率だが、小惑星イトカワぐらいの500m級の天体が衝突すると、1000キロ先の海に落ちても、高さ数十m以上の津波に襲われる。生きているうちに、これをみる確率は高くないだろうが現実にそれはあるし、現に、恐竜をはじめ、過去の地球の生物や人類は、いま忘れているだけで、この宇宙災害を経験してきたのである。
では、どうすればよいのか。本書の巻末に提言が載っている。「2日以上前に、直径10m以上の地球衝突天体をみつけられる観測システムを作ったほうがいい」というのだ。地球にぶつかりそうな天体は早くみつけたほうがいい。直径100mの天体なら3トン、500mなら350トンほどの物体を衝突の10年前にぶつければ、軌道を変えることができ、地球からそれるらしい。科学、そして新聞書評も、社会に危険を事前に知らせるレーダーのようなものであろう。「はやぶさ」のリーダーの意見に耳を傾けたい。我々は、何千年も、杞憂を嘲笑してきたけれども、杞憂を笑うものは、いつの日か天体衝突に泣くかもしれないのだ。
ALL REVIEWSをフォローする











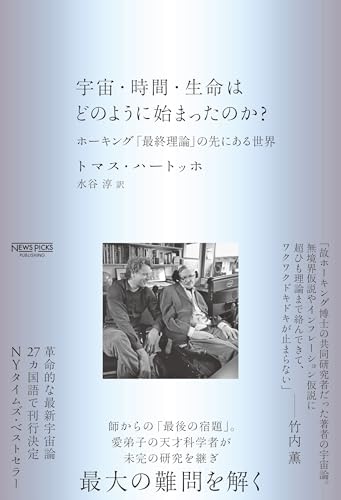




![[図説]100のトピックでたどる月と人の歴史と物語](https://m.media-amazon.com/images/I/517NxrWrasS._SL500_.jpg)


















