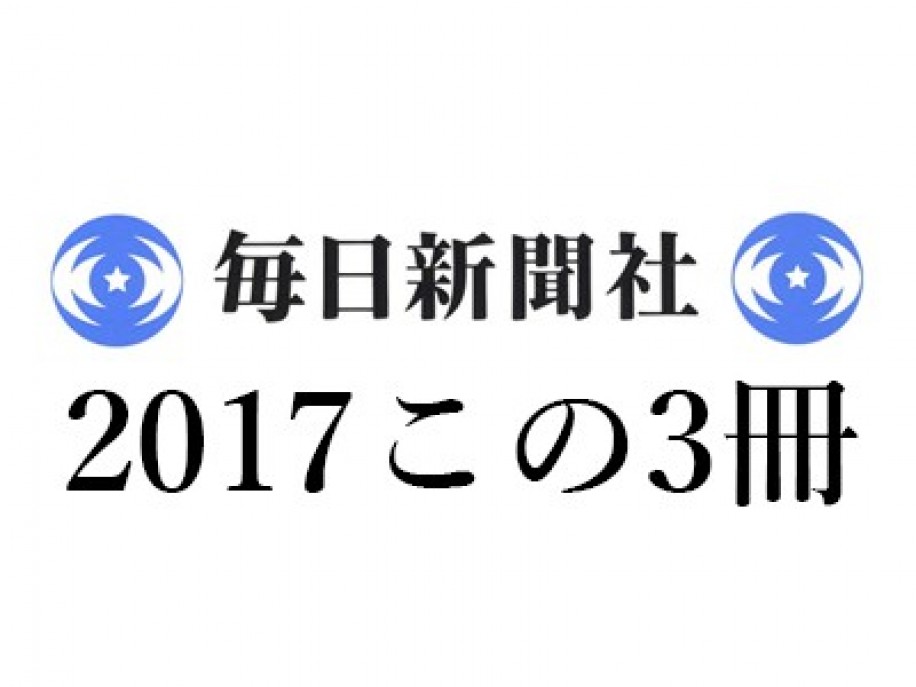書評
『ウォークス 歩くことの精神史』(左右社)
思索と創造の原動力に
「歩くこと」の精神史を網羅的に論じた大作である。猿人が直立歩行を始めて以来、数百万年の時を経て、歩行はサバイバルのための生物的戦略から、思索と創造の原動力、推進力へと変わっていった。欧州において文化的歩行の原点には、思索する散歩者ルソーがいる。
第一部「思索の足取り」は、身体を通じた歩行と思考の連動を論ずる。なぜ近現代人は歩くと考えられるのだろう? ひとつには、ディストラクション(気を散らすもの・こと)という抵抗要素があるのではないか。キェルケゴールは、街の喧騒(けんそう)から離れるより、騒乱に抗して思考するからこそ、無限に湧きでる想念を受け止められる、と言う。
一方、歩行は祈りや信仰の発露でもある。その巡礼の精神は、古来の聖地参りから、患者の支援金集めの「エイズ・ウォーク」にも見られるだろう。身体を使って一歩一歩移動していく真摯(しんし)さが祈りに通じる。映画監督へルツォークは友人が重病と知らされたとき、「自分の足で歩いていけば、あのひとは助かる」と信じて、コンパスを手にミュンヘンからパリへ歩きだした。
聖地の近くで見かけたキャデラックをめぐる考察も興味深い。車体には、「十字架への道行き」が描かれており、ソルニットは、巡礼の本質であるキリストの「まねび」すなわち模倣と反復を思い、この連続画を見る者は「物語へ身体ごと入ってゆく」と表現する。それは、詩人マリアン・ムーアの名言、「空想の庭」にいる「本物のヒキガエル」になることだ、という思考の鮮やかな跳躍は、まさに歩行によって得られたものではないか。
第二部「庭園から原野へ」は、人々が邸内や造りこまれた庭園から出て散策することの意義を考察する。十八世紀以降、自然が脅威から美的なものとして讃(たた)えられるようになったことと深く関係するだろう。主役は、あらゆる紐帯(ちゅうたい)からの解放を望むワーズワースらロマン派詩人たちだ。彼らにとって不便な環境のなかを歩くことは、「詩の領野を強固にする」ことだった。その一方、見かけと裏腹にラディカルなオースティンの『高慢と偏見』では、ヒロインは歩くことで革命を起こす。上流の田園詩的な散歩から逸脱し、実用のために三マイルも歩いてみせるのだ(「用があって歩く」のは下々のすることだった)。大地を歩むことが政治的「抵抗」の表明でもあったことは、ドイツの初期ワンダーフォーゲル活動にも見てとれるだろう。
第三部「街角の人生」は、街中の散策である。「街路」という言葉は「自然」に対して後ろ暗く、俗な、エロティックな、危険なものをひきつけるという。ロンドンの雑踏を歩く匿名者の悦(よろこ)びを綴(つづ)ったウルフのエッセイが魅力的だ。同じころパリでは、同様に近眼で猫背の遊歩者(フラヌール)ベンヤミンとジョイスがすれ違っていた(かもしれない)。前者はパリを歩くボードレールの試論を書き、後者はダブリンを歩く男を主人公に『ユリシーズ』を書いた。ブルトンはナジャと街で一夜をすごす。しかし女性は夜の遊歩者になれなかった。歩けば「商品」と見なされる恐れがあるからだ。本書では、歩行への取り組みにおける男女の違いも浮き彫りになる。
著者は人類学、文学、哲学、美学、政治、都市論、フェミニズムなどの領野を悠々と、ときに熱に浮かされたように渡り歩く。原題はWanderlust。漂泊への想(おも)い。芭蕉の「おくのほそ道」の英訳でドナルド・キーンがこの単語をあてているのは、「そゞろ神の物につきて」という箇所だ。私たちは遠い祖先が立ち上がった時から、歩行熱にとりつかれている。(東辻賢治郎訳)
ALL REVIEWSをフォローする