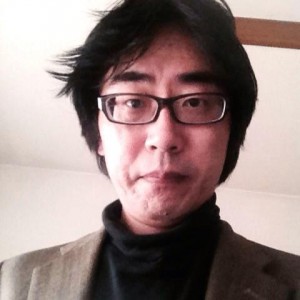書評
『製鉄天使』(東京創元社)
少女たちの精神史を再話
山陰地方の架空の村を舞台に、山人の血を受け継ぐ万葉以下、毛毬、瞳子と続く製鉄所一族の女三代記を描いた「赤朽葉(あかくちば)家の伝説」の外伝的作品。「赤朽葉家―」の設定と微妙に似ているが、本作の舞台となるのは赤珠村。主人公の名は赤緑豆小豆である。物語の始まる1979年3月の時点で小豆は小学生。製鉄所の娘である彼女には、彫刻刀からバイクまで、鉄製の道具ならば意のままに操れる特殊な才能が備わっている。中学進学後、わずか4人の手勢で女子暴走族「製鉄天使」を結成した小豆は、地元の「エドワード族」を倒したのを皮切りに、山陰地方、ついで中国地方全土の制圧に成功する。
戦いのなかで一瞬の生を燃やすことが「少女」であることの誇りだ、といわんばかりに、小豆は刹那(せつな)を生きる。だが「製鉄天使」を脱退して進学校に進学した元盟友のスミレが少女売春の元締めとして検挙され、獄中で死を遂げたとき、小豆は自身の「少女の時間」が、ついに終わりつつあることに気づいてしまう。
こう書くとわかるとおり、登場人物の名こそ微妙に違え、「製鉄天使」のストーリーは「赤朽葉家の伝説」で描かれた毛毬の物語と同一である。それもそのはず、「製鉄天使」は「赤朽葉家―」の第2章「巨と虚の時代」で、少女マンガ家となった毛毬が描く作中作「あいあん天使(エンジェル)!」として構想されていた部分を、独立させた作品なのである。
「シャン」「てへっ」「イヤン!」等、マンガ的というより「死語」といったほうがふさわしい言葉を意識的に用いた「製鉄天使」は、ガルシア・マルケスの「百年の孤独」を思わせる超時間的な濃厚さをたたえた「赤朽葉家―」とは対照的だが、コミカルな言葉の合間にしばしばみられる寺山修司を思わせるフレーズからは、遠い昔に失われた少女たちの「精神史」を再話することへの、著者の強い意志を感じた。
初出メディア
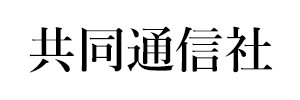
共同通信社 2009年12月10日
ALL REVIEWSをフォローする