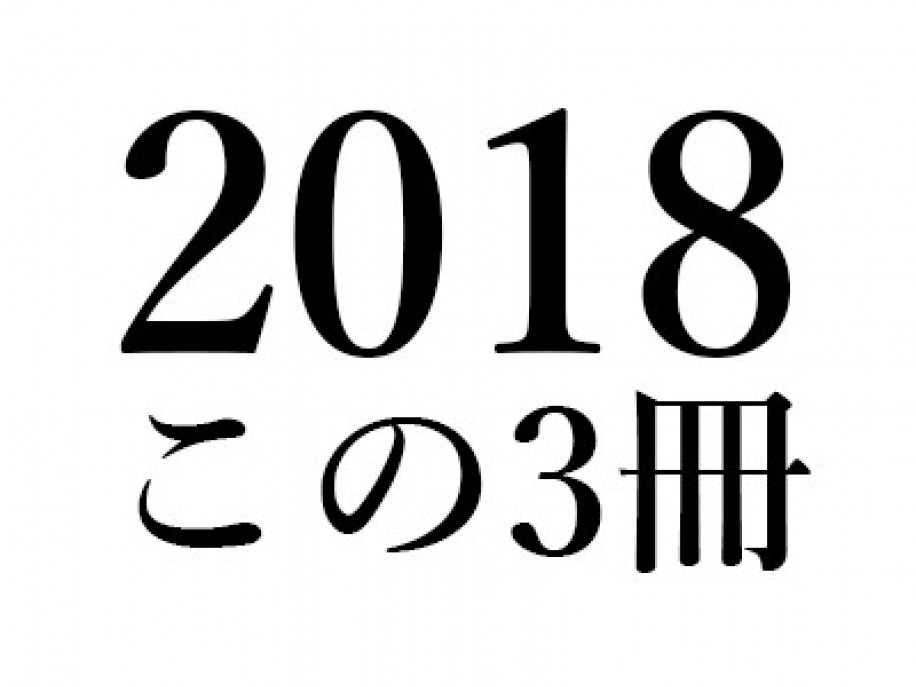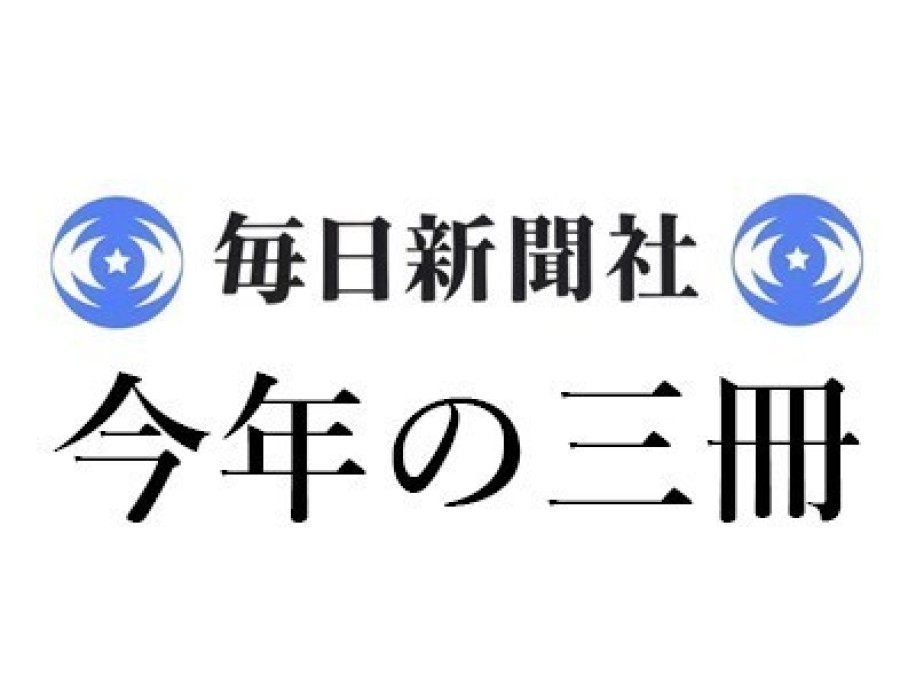書評
『バカロレア幸福論 フランスの高校生に学ぶ哲学的思考のレッスン』(講談社)
考え方の「型」を学ぶことは可能だ
「幸福になるためにはあらゆることをしなければならないのか?」「孤独のなかで幸福でいられるであろうか?」読者諸氏はこうした問いに答えられるだろうか? 「はい」か「いいえ」だけではいけない。「はい」にしろ「いいえ」にしろ、その理由を理路整然と述べるばかりか、根拠となるような哲学的著作からの引用を行い、さらには予想される反対意見に対する反論をこれまた引用に基づいて行って最終的には「はい」でも「いいえ」でもない第三の答えが現れるように論を結ぶのが理想である。
こんなことができるのは、日本人では修業を積んだ哲学者だけだが、フランスでは、普通バカロレア(大学入学資格試験)を受験する高校生の大半が制限時間四時間のうちに答えを出しているのである。
そんな奇跡のようなことが可能なのだろうか? 可能なのである。考えるための哲学的訓練さえ積むならば。げんに、フランスの高校生は最終学年でこの訓練を受けているのだ!
本書はバカロレア哲学試験の「受験解説書」の体裁を取って、幸福になるためには幸福について考える術を学ばなければならないと訴える哲学書である。
例を二〇一一年出題の「孤独のなかで幸福でいられるだろうか」に取ってみよう。これに答えるにはまず出題が「・・・は可能か」を問う二者択一型の問題であることを見極め、次にどのようなテーマかを分析する。キーは幸福と孤独でこれを高校で学習した哲学者の定義を踏まえつつ再定義し、両者の関係はいかにというかたちに展開を図る。
これが済んだら孤独のなかでも実現できる幸福があるという立場と、孤独のなかでの幸福には限界が存在する立場の二つを検討するが、まず、どのように展開するのか式次第(設計図)を明示することが必要である。
次いで、二つの立場の検討に進むのだが、ここでは学習成果の披露を心がけると同時に哲学論議の論理的配列にも気を配る。
前者の立場なら、孤独は主観的なものだから孤独でも幸福であり得るとするカントをまず出し、次いで孤独をポジティブに考えるストア派、孤独のなかにこそ完璧な幸福があるというルソーなどの例を挙げる。そうしておいてから、孤独での幸福も存在するが、そこには他者の不在という限界があるのではと疑問を呈し、もう一つの立場の検討に入っていく。
すなわち、幸福も不幸も他者との共感が不可欠というヒューム、民衆全体の幸福を提起したサンジュスト、最大多数の最大幸福という原則を提唱したベンサムなどを挙げて、他者や集団との関係における幸福を論じ、最後にこうした検討を踏まえたうえで、孤独のなかでの幸福も可能だが、そこには他者や社会との関係がないがゆえの限界が存在しているという結論を述べる。
さて、以上のような模範解答を見て読者はどう感じるのであろうか? 高校生が本当にこんなことが書けるかと疑問に思うだろう。しかし、書けるのである。考え方の「型」を学んでいるから。あるいはこんなに平凡な結論でいいのかと思う人もいるかも知れない。いいのである。バカロレアで問われているのは思想ではなく、考え方の「型」の修得度だからである。
「型」があって、それが学校で教えられているということは、われわれもその「型」を学ぶことが可能だということです
議論の渦中にある日本の教育改革におおいに参考になる一冊。
ALL REVIEWSをフォローする