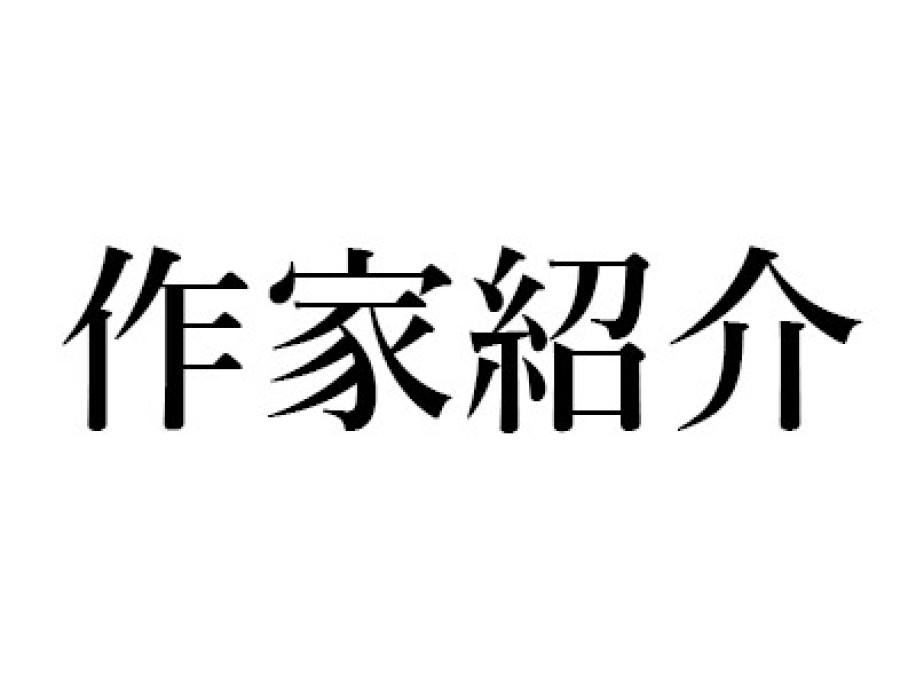書評
『東京裁判論』(大月書店)
こうして決まった被告二十八人
もし東京裁判が行われなかったならば、という仮定をしてみると、それがいかに大きな意味をもっていたかがわかるのではなかろうか。これまで戦争責任追及の不十分性や、裁判の尻すぼみ的な終結の問題点が指摘されてきた。だが今になって思うと、もし東京裁判がなかったならば、果たしてどれだけ戦争責任が追及できたのだろうか。ポツダム宣言受諾にあたって、軍部が自主裁判によりこれを逃れようとした一事をもってしてもわかる。
あるいは、勝者による裁判の欺瞞性が言い立てられ、その無意味さが指摘されてきた。だがこの議論では、占領から講和にいたるまでの時期の国際関係が東京裁判によって維持されたこと、この裁判の結果を受け入れてこそ講和がなったことを忘れてしまっている。実に今日の日本の国際関係の基礎は、東京裁判によって築かれたのである。
だから、東京裁判については徹底的な究明が必要である。戦争責任を考えるうえでも、戦後の国際関係を考えるうえでも。
著者は主として戦争責任論の視角から東京裁判の意義とその限界を見つめ、戦争責任の深化をはかろうと考えた。そのためには何が必要か。「無責任の体系」として天皇制を処理するだけでは駄目であり、東京裁判がこれにどうメスをいれたかを具体的に跡づけることによって明らかにしなければならない。
そこで著者はワシントンのダウンタウンにある米国立公文書館に飛び、ここに残された東京裁判の国際検察局の膨大な文書を入手する。キーナン首席検事や検察局スタッフの活動がじかに伝わってくるそれらの資料に接して、著者の精力的活動は開始されたのである。
東京裁判の被告二十八人はどうして決められたのか、被告とならなかったA級戦犯容疑者の免責の理由はなにか、あるいはどうして天皇は訴追されなかったのか。これまではあやふやな外部資料で推測されてきたことを、内部資料で正し、さらにその経過を具体的に描いてゆく、これが本書の白眉である。
裁判関係資料のわかりにくさ、英文資料の壁をこえて、丹念に事実を追究し、問題点を明晰に提示しており、東京裁判の実像はくっきりと明らかになってきた。それとともに戦争責任の追及の難しさと、にもかかわらず、これをなさねばならぬ重要さとが浮かび上がってくる。東京裁判の意義がまことによくうかがい知られる。
さらに新聞報道でも注目を集めた、戦前の化学兵器・細菌戦に関する資料の発掘、張作霖爆殺の真相をめぐる政府の資料の紹介など、東京裁判に際して集められた価値の高い資料、証言を公にし、その意義を明らかにしたことも評価されよう。
本書を読みつつ改めて思った。東京裁判で示された「平和に対する罪」と「人道に対する罪」、日本はこの二つを自覚し、平和と人道の二つの理念を求めることによって、国際社会に受け入れられたのであり、それによってこそ今日の繁栄があったのだと。
ALL REVIEWSをフォローする