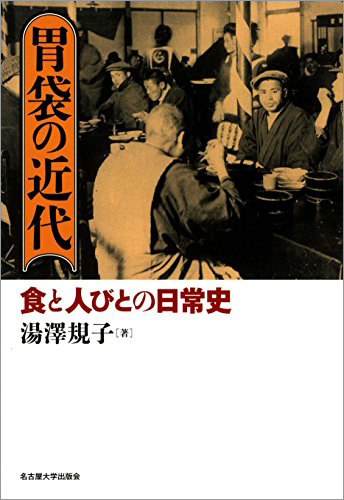書評
『旅の終わりに』(東京創元社)
人や世間が何と言おうと、この上ない「ハッピーエンド」
八十代の老夫婦が主人公だ。夫は認知症がすすんでいる。妻はガンを病み、進行は遅いが全身にひろがった。娘と息子が相談している。結論は言うまでもない。父は施設へ、母は病院へ。アメリカの小説だが、同じような家族なら日本にもワンサといる。ごく身近に、つぎつぎと思いあたる。多少とも毛色が違っているのは、妻が決意して夫と最後の旅に出ることだ。誰にも告げない。幸い夫は、なんとか運転はできる。子どもが幼かったころ、家族で愛用したキャンピングカーがある。何度も走った大陸横断のルートは、過去への旅でもあって、空間、並びに時間旅行ができる。
スライドでアルバムをながめていれば、おおかた消えてしまった夫の記憶も、少しはよみがえるかもしれない――。
イリノイ州、ミズーリ州、カンザス州、オクラホマ州、テキサス州……。ふつうアメリカの映像におなじみでない風景がつぎつぎと語られていく。かつてなじんだ国道は、いまは旧道であって、その道路沿いの都市もまた時代にとり残された。通りにひとけなく、商店は閉じられ、半ば廃虚化している。夫が定年まで働いていた自動車の街デトロイトをはじめ、見捨てられた町々の数珠つなぎだ。老夫婦のノスタルジア旅行が同時に、アメリカの老朽化した都市の巡礼にもなる。ドナルド・トランプという、およそ不適格な人物を大統領に押し上げたのも、この数珠つなぎの回廊だったのではなかろうか。
小説『旅の終わりに』は先だって封切られた映画「ロング,ロングバケーション」の原作にあたる。映画化されると、原作は軽く見られがちだが、これは映画化とともにお役ごめんにされるのがとても残念な気がする。認知症の夫との二人旅は、いやでも病のあらゆる症例がかぶさってくる。今日が何曜日かもわからなくなっていて、自分の名前すら思い出せない。ところが朝のほんのひととき、昔どおり、いたってまともだったりする。よろこんだとたん、昔の夫はもういない。
控え目で穏やかな人だったのが、記憶をなくし始めて以来、人に言いたくて言えなかったことばかり口にする。何を覚えていて何を忘れているのか、妻にも、もうわからない。腹立たしく翻弄(ほんろう)されているさなかに、時が止まったような、やすらかな一瞬が訪れる。いそいでつかもうとすると、すでにもぬけの殻。医学の及ばない心の領域にちがいない。
勇気ある妻が一つの決断をした。自分たちの最期のときをどう生きるか、自分の責任で自分で決める。それは、どう死にたいかの選択でもある。私たちはすでに、そんな選択の時代に生きているのではなかろうか。
アメリカの作家は直截(ちょくせつ)であって、目覚めのない眠りのための処置をしたあと、最後にはっきりと収支決算を掲げている。旅に出なかった場合、夫は施設に入れられ、一年だか、二年だか、三年だか、必ずや惨めな、ひどい状態になりながら過ごしただろう。そして自分は「現代医療とやらに、尊厳を踏みにじられて、ひとつも病気はよくならず、しまいには見放されて」死ぬしかなかっただろう。だから人が何と言おうと、この上ない「ハッピーエンド」を実現した。
ALL REVIEWSをフォローする