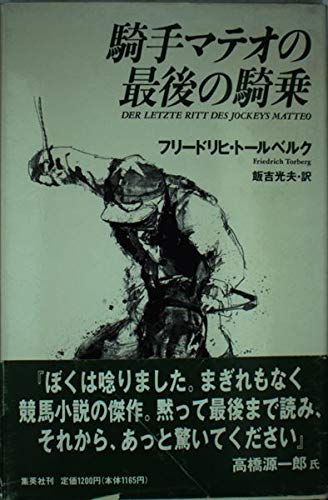書評
『ケストナーの「ほらふき男爵」』(筑摩書房)
ケストナーの贈物
エーリヒ・ケストナー。名前を聞くだけで胸が踊る。『ふたりのロッテ』『エーミールと探偵たち』そしてあの『飛ぶ教室』。戦後生まれの子どもなら、どこの学校図書館でも出会えた本。何度も繰り返し読んだ夢の玉手箱。
彼の子どものための本十九冊のうち、再話の仕事が六冊ある、とはじめて知った。それがすべて訳されて、多数の天然色挿絵入りで大判の本にまとまった。『ケストナーの「ほらふき男爵」』(池内紀、泉千穂子訳、筑摩書房)。画家の名はW・トリヤーとH・レムケ。年輩のトリヤーの絵は柔らかくほのぼのした抒情があり、三十歳年下のレムケの絵はシャープで諧謔(かいぎゃく)味がある。だけれどトリヤー風のレムケの絵もあってどっちがどっちだか、そこがお楽しみ。
さわりをご紹介しよう。
「目が覚めると、キラキラ太陽が輝いている。辺りを見廻し、あらためて目をこすった。おどろいたね、村にいる。しかも教会の墓地ときた! 誰だって墓石のあいだで目覚めたくないではないか。それに馬がいない。昨夜、すぐ近くに手綱を結びつけたはずだ」
結わえたのはじつは教会の風見鶏、一夜あければ雪が溶けて、馬は空高くいななく、ご存じ『ほらふき男爵』の一節。
三人の子どもに読んでやった。少し大時代がかった声を出すと大喜び、訳文の口調がよく勢いがあるので、親の方も退屈しない。読者のみなさんも、ちょっと声出して読んでみて。ほらふき男爵が、トルコ戦争のとき、敵陣視察を命ぜられたくだり。
「やにわに大砲が火を吹いた。このチャンスを逃してなるものか。即座に心を決めて砲弾にとび乗った。弾もろとも敵陣へ乗り込もう! だが風をきって飛んでいくなかで考えた。とびこむのは簡単だが、どうやってもどってくる。軍服によって、すぐさまこの身をさとられる。とすると、向こうに待っているのはしばり首!/思い直した。このときトルコ側が大砲をぶっぱなしたので、砲弾がとんでくる。かたわらをかすめた瞬間、ヒョイと跳び移った。はからずも、とはいえ五体にかすり傷一つなく、わが陣営に舞いもどった」
なぜケストナーは再話を買って出たのか。訳者は「本文をお読みになればすぐにわかる。語りのリズムとテンポがちがう。筋の運びと速さがちがう。人物の描き方、光の当て方が微妙にちがう」という。そう思う。
たとえば『ドン・キホーテ』。サンチョ・パンサは主人の耳に包帯を巻きながらやさしくささやく。
「騎士道ってのは大変だね。旦那さま。もうちっと戦さをへらさないかね。王国なんていらない。おいらには中くらいの伯爵領で十分だ」
語り口にケストナーの世界観が顔を出す。彼の本はブレヒト、トーマス・マン、レマルクらの本と共に、ナチス・ドイツによって発禁となり、焚書(ふんしょ)にされた。
ほかの作品も駄洒落の合間に権力をおちょくり、空いばり、鈍重さを笑いとばし、思いやりのなさや凡人の悲しみ、つまり人間の本性をくっきりさせている。練達・清新の二人の訳者の功も大きい。一人の訳者はこう書いている。
名うての古典的名作でも、そのままにしておくとカビがはえる。古くさい味がする。名作の名のもとに古くさい味を押しつけるのは、子どもの本の著者の怠慢というものではあるまいか。何はともあれ、子どもはとりわけ舌が敏感な生きものなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする