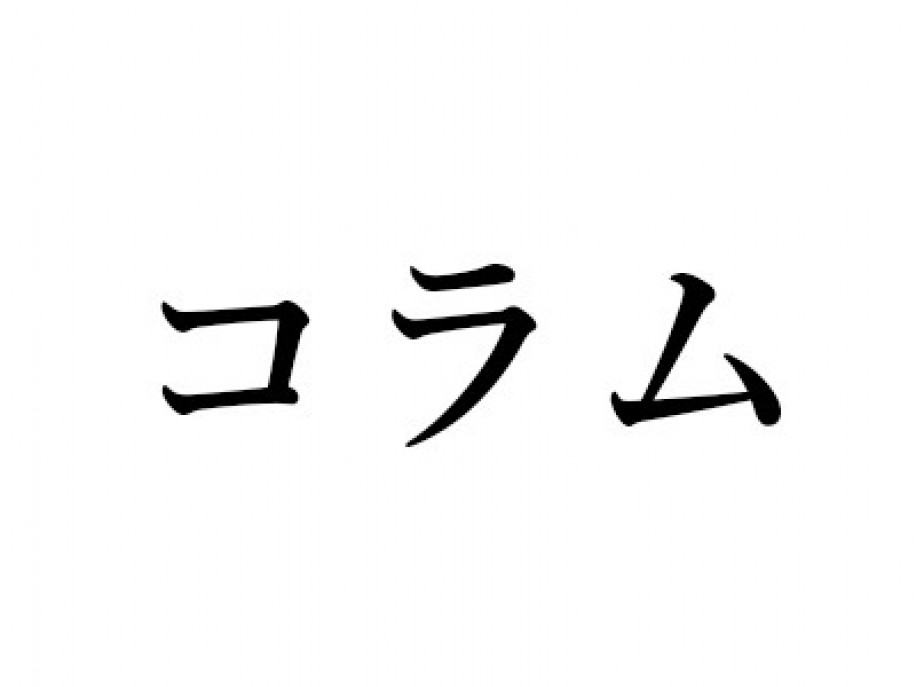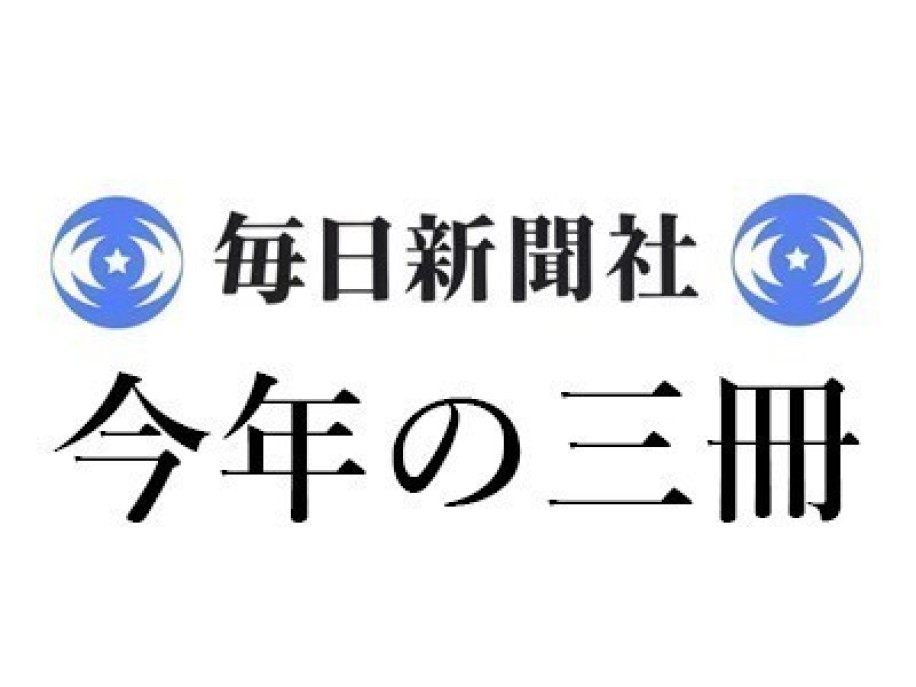書評
『水声』(文藝春秋)
魂の荒野を彷徨い生まれ来る人間
思えば、「いもせ」という日本語は中世前には、夫婦を意味すると同時に、兄妹または姉弟も意味したのだった。両者には同じ語(妹背/妹兄)が充てられていた。古来、男女のきょうだいが結ばれて土地の始祖になる、世を治めるという考えは日本だけのものではなく、ギリシャ神話にも、古代エジプトの王家にも見られた。『水声』の語り手の女性「都(みやこ)」と一歳年下の弟「陵(りょう)」は、母の没後十年を経た三十代後半から古い実家にふたりで暮らし、共寝している。「あらあら、そんなことして、いいのかしら」と死んだママの声。しかしふたりはそれ以前にも、「鳥が太く短く鳴いた」夏の一夜を密かに経験していた……。
人間というのは、魂の荒野を彷徨(さまよ)ってから生まれてくるのではないか。そこで感じた孤独、寄る辺なさ、悲しみ、怒りを体と心に刻印して生まれてくる。わたしたちは予め害された存在なのではないか。しかしながら同時に、わたしたちは予め赦し、赦された存在なのかもしれない――『水声』を読みながら、そんなことを思った。甘美にして苦しい読書体験だ。苦しさの間に、心が平らかにぬくむひと時がある。
陵は地下鉄サリン事件の現場に居合わせ、ほんの偶然から命拾いをした後、姉に同居の申し入れをし、眠れないという理由でふたりの共寝が始まる。「まだあの時のことをたびたび思い浮かべてしまう<中略>おれには確かに、あの時の手ざわりがあるんだ」……。
実母を空襲で失ったママ。ママを愛し憎んだ都。作中の諸々(もろもろ)のなりゆきを「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」とか「不適応」とかといった学術用語で分析することも可能かもしれない。しかし陵はさらに言う。「まったく知らぬもの、想像もしてみないものならば、こんなにずっと残ったりしないにちがいない。一度でもその遠い呼び声を聞いてしまった者なら<中略>決して知らんふりできない。そういうものの手ざわりを、おれはあの時感じたんだ」。その「呼び声」の真の出所はサリン事件の遥(はる)か遠く深いどこかにある。
「だって都は<中略>柔らかで突けばすぐに死んじゃうようなものだったじゃない」
赤子のころの都をこんなふうに平気で言うママは、古代の女神のように残酷でもあり、姉弟婚をしたクレオパトラのように男性を惹(ひ)きつけてやまず、「いろんなものを壊す癖」があった。今風にいえば「毒親」だろうし、それでも都は呼ばれるとママに「吸いよせられ」、彼女も陵もパパも「互いを見ないように聞かないように<中略>実体をもつただ一人のママの周囲を、半透明な三人が常にそぞろ歩いているかのよう」という一家は、「機能不全」などと評されるかもしれない。しかも都と陵の関係はある意味、反復にあたるのだから、代々の家庭環境が「歪(ゆが)んだ」関係を作りだした、などと。実際『水声』には、東京大空襲、昭和の終わり、サリン事件、東日本大震災など、いかにも人々の人生の転機となり、人格形成に影響を与えたと思わせる史実も書きこまれている。だからこそ、注意が必要だ。何かの原因を何かに「負わせる」こと、説明がつくことの安心に。「あの夏のことだけにすべてを負わせるのは、きっとまちがっている。いつもそれはあったのだ」
謎は他にもいろいろとある。「奈穂子」とは何者なのか。その従姉妹(いとこ)の「薫」が描く自画像が彼女に似ていることの衝撃とは何か。もっともらしい所以(ゆえん)を見つけたと思ったとたん、川上弘美の小説は踏まれた蛇のようにずるりと逃げる。別なものに化身する。
ALL REVIEWSをフォローする