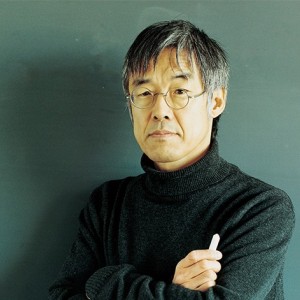書評
『1000年後に生き残るための青春小説講座』(講談社)
1000年後に生き残れなかったとしても
この本の序にはこんなことが書いてある。本書は、「群像」という文芸誌の依頼を断ったゆえに生まれました。「一世を風靡したが今は消えてしまった戦後文学作家の小説を読み直し、ディスカッションしてその価値を再発見する」という、「戦後文学を読む」なる眠たくなりそうな企画に呼ばれたのですが謝絶し、「作家のセレクトはそちらの提案に沿うが、語るよりも書かせてほしい」と編集部に要請しました。こうして、企画に反撥するかたちではじまった連載をまとめたものが、本書になります。
その、「戦後文学」とは縁もゆかりもない、ずっと若い世代の佐藤さんを反撥させた企画の片棒を担いだ者としては、ほんとうに申し訳ないことをしたと思う。そもそも、どうしてそんな企画に参加することになったのか、正直いって、おれにもわからないからだ。
企画自体は、編集部のSさんの「戦後文学をもう一度読み返したい」という「熱い思い」で出発したのじゃなかったかと思う。おれ? おれはそれを聞いて「変わったことを考える人がいるものだ」と思いましたが。だいたい、そんなもの、今頃読みたいと思うやつがいるんだろうか。おれだって、胸に手を当てて考えてみたけど「別に」という感じだった。そりゃあ、おれだって若い頃は読んだけど。おれだけじゃなくて、「文学」志望者には「読まなきゃならない必須の本」みたいなものがあって、その中には、この企画に登場したり、登場する予定だったり、登場してもおかしくない名前がたくさんあった。ノマヒロシとかタケダタイジュンとかハニヤユタカとかシマオトシオとかヒラノケンとかタケウチヨシミとかナカノシゲハルとかタカミジュンとかハナダキヨテルとかフクダツネアリとかイトウセイとかオオオカショウヘイとかホッタヨシエ……最近、こうやって思い出していっても、出てくる名前が減ってきてる……とかだ。おれは、この名前の人たちが書いた本を読んだ。面白かったものもあった。それほど面白いとは思えないものもあった。もちろん、ぜんぜん面白くもなんともないものもあった。それはどの時代のどんなジャンルの文学(だけじゃないけど)も同じだった。で、その時期が過ぎると、おれはまた、別の種類のものを読むようになった。それからまた、次の時期も過ぎると、さらにまた別の種類のものを読んだ。気がつくと、「戦後文学」というジャンルの人の作品から遠ざかっていた。読むことも、読んだことも思い出すことも、だ。
いや、待てよ。この書き方だと、「戦後文学」というものは、「外国文学」とか「SF」とか「マンガ」とか、そんなたくさんあるジャンルの一つとまったく同じということになってしまうか。そうではなかった。なにかそこには独特のものがあった。「戦後」ということばに象徴されるものが。おれたち自身がその一員であるような「時代」から生まれたもの、という感じだ。おれ自身は直接参加したわけではないが、その空気をすごくよく知っているもの、という感じでもある。それは、まあ、仲間というか同志というか友だちというか、親戚のおじさんとか、そんな種類のものでもあったのだ。
でも、気づいたら、まったく会わなくなっていた。ずっと前は、あんなにしょっちゅう会っていたのに。一晩中しゃべったりするのが当たり前だったのに。もう何年も音信不通になってんのに、連絡をとる気をなくしていた。どうしてなんだろう……。
いや、そこで重大なことに気づいたわけだ。どうして、こんな風にあっさり忘れちまうのか、ってことに。
そもそも、おれたちはなんでも忘れちまうのだ……では、答にならない。おれが問題にしているのは、それが「文学」の問題だからだ。だってだよ、「文学」なんてものは、そもそも「永遠」とか「普遍」とかを目指すものなんじゃないですか。忘れられないものを目指してるわけじゃないですか。なのに、その他の、「流行り廃り」があるジャンルのものとまったく結果が変わらないとしたら、「文学」の独自性なんかないんじゃないか。ってか、文学に意味なんかある? まあ、おれは、「戦後文学」のことを考えているうちに、そういうことを考えるに至ったのだ。
おれがそんなことをいっても、同意してくれるやつは、どこにもいなかった。佐藤友哉以外には、なんだが。
長い前置きで、すまん。もう一回、この本の序に戻ろう。序は、実は、こんな風に始まってる。
長年僕が関心を持ってきたのは、時の流れを乗りこえる方法です。我々は一〇〇〇年後には死に絶えます。一〇〇〇年前に生まれた人々が死に絶えているのと同様に。当たり前に。常識として。ならば文章は?
答は明白だ。ほとんどのものは残らない。誰だって当然だと思う。ところが、変わったやつがいて、どうすれば一〇〇〇年後に残るのかを真剣に考えたのだ。心底バカだ……。まあ、実のところ、おれも考えてたんだ。だから、バカはひとりじゃなかったのか、と思ったけど。
この本の中で、佐藤友哉は、「戦後文学」の何人(何冊)かと律儀に付き合ってみせる。最後には、「生き残った『戦後文学』」No.1、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』まで登場する。その結果(というか、途中でわかっちゃうんだが)、永遠に(近く)生き残るために必要なものが明らかになるのである。なんだ、「あれ」だったのかい! でもって、佐藤友哉は、誰よりも「あれ」を持ってる作家だったんだけどな。あと、おれも。
だからといって、おれや佐藤友哉が一〇〇〇年後まで生き残れるってわけじゃないんだが。
ALL REVIEWSをフォローする