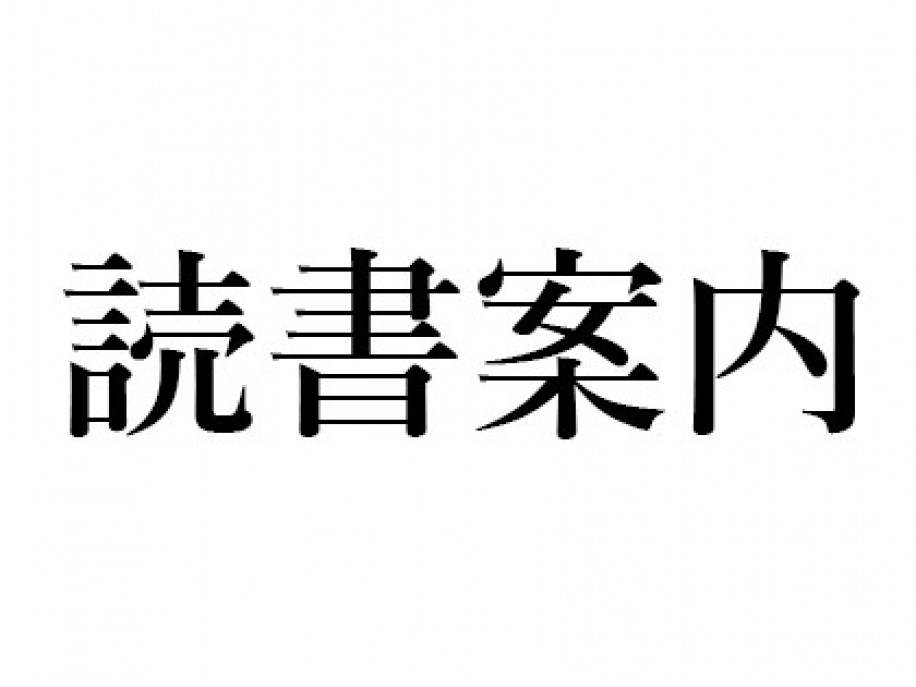書評
『比較史の方法』(講談社)
科学的、合理的な「考え方」教える名著
一九二八年、後にアナール派史学の開祖と仰がれることになる四二歳のストラスブール大学教授マルク・ブロックはオスロの国際歴史学会で「ヨーロッパ諸社会の比較史のために」と題した講演を行った。本書は訳者がこれに詳細な解説を施したわずか一三〇ページの小冊子であるが、非常に示唆に富む歴史学の「方法序説」となっている。ブロックは、社会学者や比較言語学者が考え出した、類似性を持つ二つの現象の厳密な比較検証法こそ、歴史学徒が「日常的に使用できるような技術的道具」であるとして、これを歴史に応用することを提起するが、同時に、似ているというだけの安易な比較は慎むように警告も発する。
たとえばリムーザン地方における荘園を比べるような、同一の起源が歴然としている複数の均質的社会状況に類似を発見しようとすることは避けるべきである。
では、歴史学にとって比較対象としてふさわしい社会状況とはどのようなものかというと、それは大きく二つあるという。
ひとつはフレイザーが『金枝篇』で試みたような、時間・空間的に隔たりがあるため「影響関係」によっても「起源の共通性」によっても類似性が説明されえないような諸社会の比較だが、ブロックはこれは民族学の範疇(はんちゅう)であるとして棚上げにしておく。
となると、残るは「影響関係」か「起源の共通性」かを探ることのできる発展過程に類縁性を持つ互いに隣接した社会すなわちヨーロッパ諸社会のような複数社会の比較ということになる。
ところで、比較とはまず類似、次いで差異を探ることに尽きるが、この場合も注意を要する。呼び名は同じようだが実質は異なっている疑似的類似物があるからだ。
次は影響関係があるか否かを調べることである。世俗的王権だったメロヴィング・フランク王国に比べてカロリング・フランク王国ではキリスト教との祭政一致的傾向が強かった。これはガリアだけに目を向けると「ほとんど無からの創造物のように思われる」が、隣国スペインに注目するとムスリムの征服を避けてガリアに亡命した司祭たちの影響を見ることができる。
というわけで、いよいよ比較史の本番である「起源の共通性」を探る段階に入るが、そこでブロックが定式化した法則は「一般的現象の原因は同様に一般的なものでなければならない」ということである。たとえば、フランス地方三部会成立の研究には地方限定の原因を探ることも必要だが、比較の範囲を広げて全ヨーロッパ規模で眺めると、三部会や地方議会の現象は一般的であることが観察されるので、原因もまた一般的でなければならないということになる。
しかし、さらに比較の範囲を広げると、一般的現象と見えたものが個別現象にすぎないことが判明する場合もある。この場合には一般的原因とされたものに再検討を加え、別の仮説を設ける必要がある。
かくて比較史で最も肝要なことは次のように要約される。すなわち、まず「古くさくなった地誌的仕切り」を破壊し、「内側から規定される固有の地理的枠」をつくること、つまり独自の分析が重要なのだが、「分析(、、)は、はじめから総合(、、)を視野に入れ、かつ総合に役立つように配慮するのでなければ、総合には役立たないのである」。
歴史学に限らずあらゆる知的分野に適用できる科学的で合理的な「考え方」を教えてくれる名著。解説は歴史学徒必読である。
ALL REVIEWSをフォローする