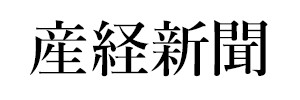書評
『松本俊夫著作集成I──一九五三─一九六五』(森話社)
ハードかつ明晰な論考
松本俊夫は1969年に初の長編劇映画『薔薇(ばら)の葬列』を発表して、センセーションを巻きおこした。当時、大島渚と今村昌平をトップランナーとしてきた日本映画に、従来とはまったく異なる映画の作り方があることを示し、世界映画の最前線に並んだのだ。題材は古代ギリシャのエディプス神話で、主人公を現代日本のゲイボーイにして、原作の有名なドラマを、母を殺し父と交わる物語に転換してしまった。主役を演じたのは、映画初出演の美少年ピーター(後の池畑慎之介)だった。
だが、それ以前に松本俊夫は、実験的記録映画の旗手であり、さらに、日本の映画理論の水準を格段に高めた批評家として知られていた。私はそのころ中学生だったが、松本の批評集『映像の発見』と『表現の世界』を読み、映画を見、文学を読み、芸術を享受することの根源的な意味と、それを言葉で論理的に説明するやり方を教わった。当時の芸術を志す若者への松本の影響力の大きさは、今では信じられないだろう。
だが、ここへ来て、松本俊夫の再評価の波が大きく起こっている。気鋭の映画監督・筒井武文は10年かけて、なんと11時間40分のドキュメンタリー『映像の発見=松本俊夫の時代』を昨年完成したし、全文業を網羅する『松本俊夫著作集成』(全4巻)がついに刊行されはじめた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年6月)。
本書はその第1巻で、1953年から65年までの松本の文章を収めている。大判2段組み、600ページ超という圧倒的な手応えだ。
その時代、松本はまだ30代の若さで、前衛的実験映画と記録映画を統一しようと試みていた。その壮大な野心を語るハードな論考が本書の柱である。だが、それらは緊張感に貫かれた名文で書かれているが、一般読者にはすこし敷居が高いかもしれない。
しかし、松本は難解さに安住する批評家ではない。読売新聞夕刊に13回連載され、本書に初めて原形で収録されたエッセーを読むといい。これは、映画の入門者から高度な研究者にまで開かれた、日本における映画批評の最も明晰(めいせき)な達成のひとつなのである。
ALL REVIEWSをフォローする