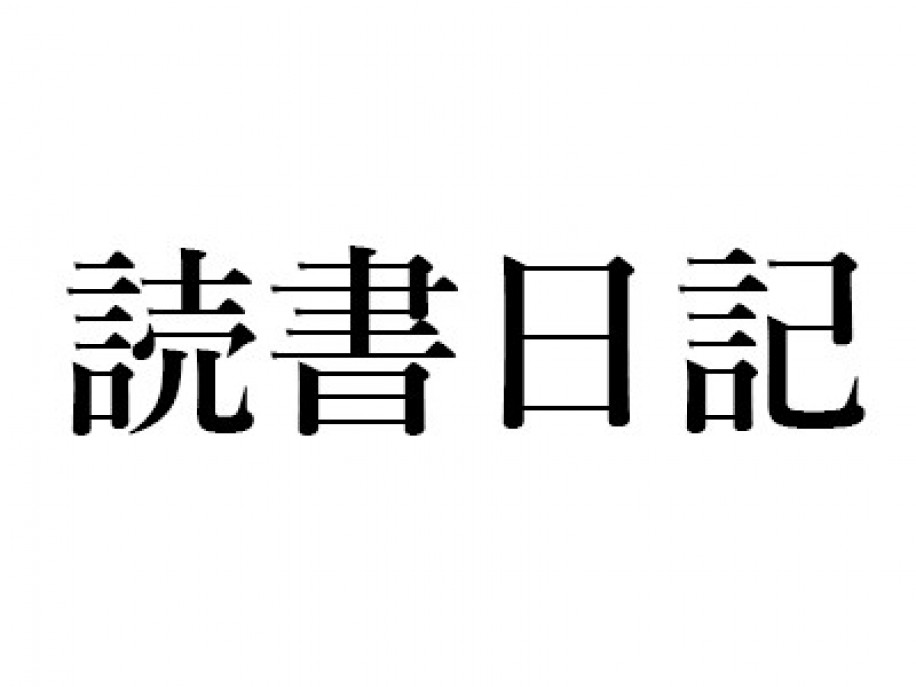書評
『できそこないの世界でおれたちは』(双葉社)
「勝ち負け」の代わりの価値観を得る
語り手である四十代半ばのシロウは、十数年前親しかった女友だちと再会し、それをきっかけにして、当時つるんでいた仲間たちと、また密につきあいはじめる。仲間たちの状況はだいぶ変わっている。全国的に有名になったバンドのドラマーもいる、離婚を機に自分の名義となったバーを営む女性もいる。三十代のときは小説を書こうとしていたシロウは、現在フリーランスのコピーライターで、離婚した妻に、十一歳の息子の養育費を払っている。とはいえ彼らは、世間一般的な四十代、五十代からすれば、やけに軽やかだ。それぞれに悩みはあれど、背負っているものが圧倒的に少ない。だから、再会した彼らが三十代のころと似たような日々を過ごしはじめても不自然ではなく、若さへの固執とも思わないし、中年のあがきとも思わない。彼らの軽やかさを可能にしているのは、彼らが三十代のころすでに「日本社会が暗に奨励するライフスタイルから意識的にせよ無意識的にせよ逃れ出て」きたからだ。その脱出には成功した。彼らは自由を手にした。彼らが三十代を過ごした二〇〇〇年代、日本の社会は人生を勝ち負けで表現していた。そこから逃げ出した彼らは、人生に勝敗を持ちこまずにすんだ。さらには日本社会が奨励する典型的な加齢をも免れた。
けれどじわじわと、彼らは免れたものたちから仕返しされている。かつて獲得した自由が、案外過酷であって、その自由ゆえに「悪戦苦闘」しているとシロウは思う。その悪戦苦闘を、私はたとえば、シロウが正月に実家に帰り、母親手製のおせちを食べながら更年期障害の話をする場面で、漠然とした恐怖として感じる。彼らはいつ年を取ればいいのか? 彼らは「そこ」を目指して大人になったのに、今彼らが手にしているものは何かといえば、年齢相応の中年の姿と、三十代とさほど変わらない人生なのである。いつ年を取ればいいのか?というのはつまりは、どう生きたらいいのか?ということでもある。それが見えないのは、つらい。
それは彼らが特殊なのではなくて、現在の中年域の人の多くが似たような戸惑いを持っているのではないかと思う。日本社会が奨励するライフスタイルに則(のっと)って加齢しても、今の社会状況が、そのライフスタイル自体を不可能にし、その先にあったモデルケースは存在しない。一方で、百歳時代などといわれ、かつてずっと高齢だと思っていた六十代、七十代はものすごく元気だ。年齢と体力と精神の差はひと昔前よりどんどん開いていって、自分の人生というものが、自分ごとなのに捉えがたい。私は今人生のどのあたりにいるのか? 後ろを振り返るべきなのか、前を目指すべきなのか?
シロウたちは、あるひとりの男の子によって、自分たちの立ち位置を確認することになる。もちろん軽やかにふざけている彼らが急にシリアスになるはずもない。ただ彼らは、いやシロウは、かつて自身の人生に持ちこむことを拒否した「勝ち負け」の代わりになる価値観を、この一連の日々のなかで得たのだと思う。
私もずっと、大人になったら悩んだり泣いたりしないのだと思っていた。大人になったらロックは聴かなくなるのだろうと思っていた。大人になったら、きちんと大人になるのだと思っていた。そしてもういい加減大人にならないとまずいと思いながら、今に至っている。だからこの小説に登場するどうしようもない大人たちをあまり好きにはなれないのだし、同時に、生身の人に感じるような親近感も覚えるのである。同じ時代に同じ世界を生きる者として。
ALL REVIEWSをフォローする