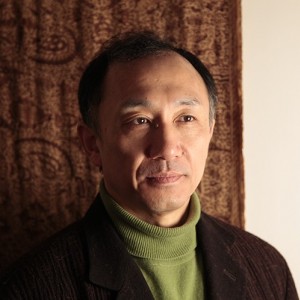書評
『通貨を考える (ちくま新書)』(筑摩書房)
ドル基軸下、金融危機の核心をえぐる
経済は難解である。それは経済学者や財界トップの意見こそが眉唾(まゆつば)の最たるものであるところに象徴されている。たとえば「競争力」という考え方について。日本は経済成長率が下がっている、だからTPP(環太平洋パートナーシップ協定)に加入して鍛え直さなければならない、そうすればアジア諸国の発展に「乗る」ことができると言われる。「乗る」とは、日本からアジア諸国に輸出できるということだ。だが、待って欲しい。途上国の発展を牽引(けんいん)するのはその国の輸出であり、アメリカは輸入する力が弱っている。TPPで日本が求められる役割は、輸出ではなく輸入のはずだ。
競争力をめぐるこうした「有識者」の発想は、経済学の通念にもとづいている。J・M・ケインズやF・A・ハイエクは1930年代からそうした通念を批判したが、そこで焦点とされたのは「通貨」だった。そして彼らは通貨にかんするラディカルな改革を唱えた。ケインズは金本位制に代わる清算同盟案として、ハイエクは通貨発行の自由化案として。
しかし彼らが問題視した「通貨」の不思議さは、十分には理解されていない。その結果が競争力をめぐる議論の混乱だろう。本書は新書でありながら、実務にまでさかのぼり、曖昧にしか論じられてこなかった通貨用語を丁寧に説明して、もつれた思索の糸を解きほぐす。仮説にもとづく理論が事実のように述べられ、国際金融をめぐる見通しをさらに悪くする類書とは一線を画している。
評者が本書の白眉(はくび)と感じたのは、「基軸通貨とは何か」の説明だ。貿易実務の現場を知らないと、たとえば中国へ輸出する日本企業は人民元を得ると考えてしまう。国を単位としたなら、経常収支の黒字国と赤字国の間で、通貨が直接に交換され決済が行われるかに想定されるだろう(実はケインズの「清算同盟案」は、どの国の通貨でもない中立貨幣「バンコール」によりすべての貨幣間の交換という複雑さを解消しようと目論(もくろ)むものである)。
だが現実には、別のやり方がとられている。中国側は、まず元をドルと交換する。それで日本から物資を買い、日本企業はドルを円に交換する。交換手数料が往復で取れるのだから、濡(ぬ)れ手で粟(あわ)とはこのことだ。これが基軸通貨の「媒介通貨」という特性である。ドルは世界中の無数の企業の間の貿易を、「第三者」として媒介している。支払いと受け取りは銀行預金への振り込みと引き出しで行われるから、決済は米国内の銀行のシステム網で行われる。
便利に見えるかもしれないが、今日の通貨危機はここに由来する。媒介通貨としてドルが散布されねばならず、それは米国の経常収支赤字によっている。IMFの専務理事と議決権は欧米が握っており、通常は経常収支赤字国には介入しつつ融資するのに、世界最大の赤字(もっとも競争力が「低い」ことになる)国である米国には、リーマン・ショックの震源地でありながら構造改革も財政縮小も命じない。自国通貨を基軸通貨に祭り上げたからこそ、赤字まみれの米国は他国に構造改革を命じ、みずからを律しない。それが通貨危機の根本原因ともなっているのだ。
こうした事態を予見したケインズやハイエクは通貨制度の改革案に知恵を絞ったが、本書もまた回答の一例を用意している。それが「日中合成通貨」。最近の領土をめぐる反目を見れば実現は容易ではないだろうが、それでも対外純資産の保有額が世界の第一位・第二位の両国が基軸通貨からもIMFからも外されている現状を思えば、言い分には妥当性がある。金融危機の核心をえぐる力作だ。
ALL REVIEWSをフォローする