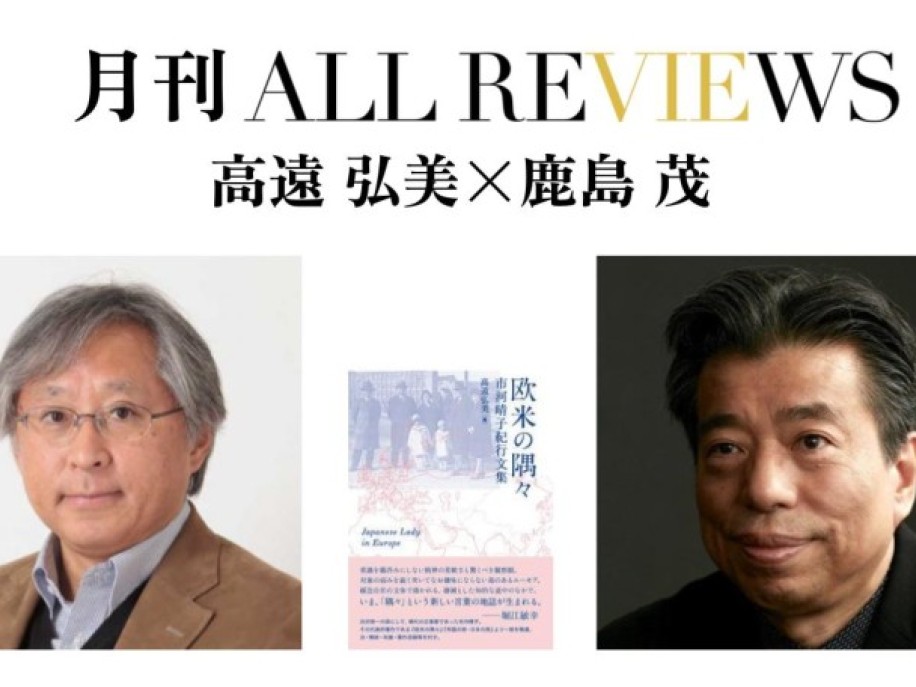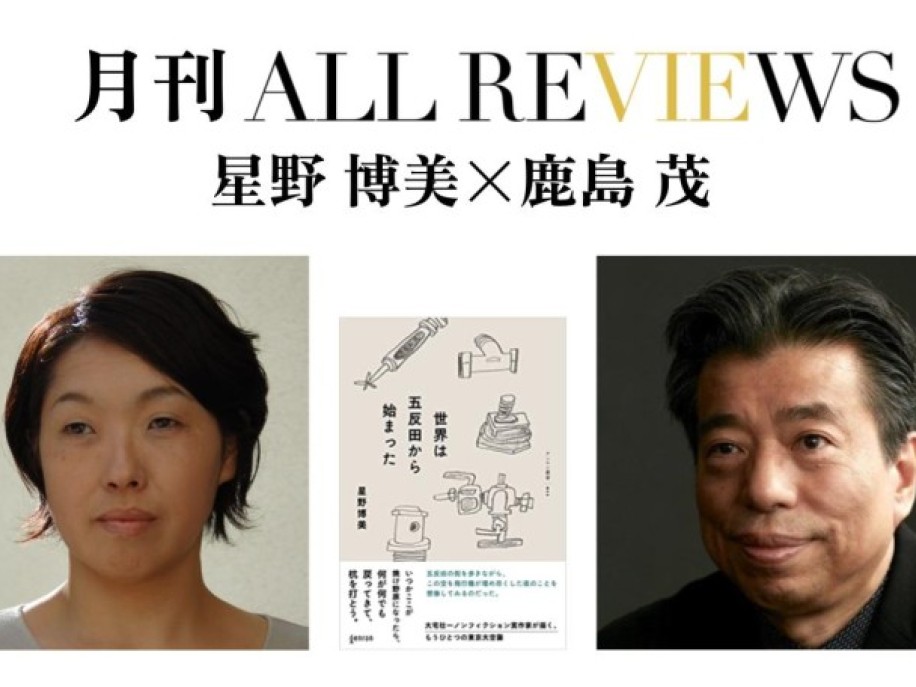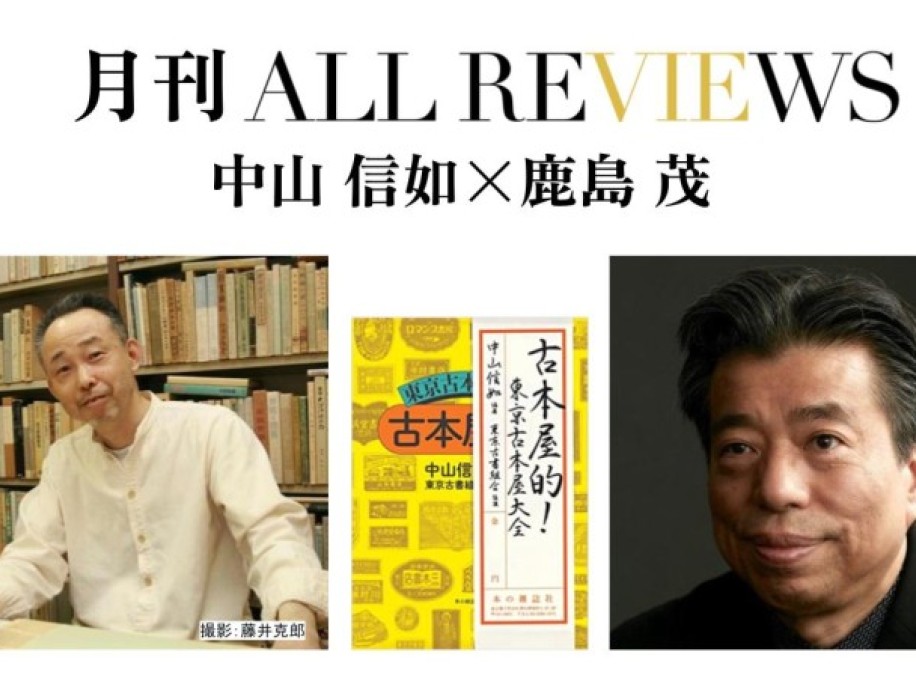後書き
『ドーダの人、西郷隆盛』(中央公論新社)
文庫版あとがき
本書のもとになる『ドーダの近代史』を朝日新聞出版から出したのが二〇〇七年のことだから、もう十一年も前のことになる。「まえがき」でも触れているように、最初は、「東海林さだおさんの『ドーダ学』確立の提唱を馬鹿正直に受け止めて」、ドーダ理論を日本近代史に当てはめてみたらどうなるのかという、軽い疑問から出発した連載だった。
ところが、やっているうちに規模がどんどん拡大し、最後は日本的組織とは何か、あるいは日本人の思考のパターンとは何かというところまで話が広がってしまった。
しかしながら、話は拡大したものの、私の心を占めていた問題は、常にたった一つだけだった。それは、西郷隆盛をどう扱うかという問題である。
なぜなら、表面的なドーダ理解からすると、西郷隆盛をドーダ人間に含めることは難しかったにもかかわらず、西郷隆盛もまたドーダ国の住人に間違いないという確信があったからだ。ラ・ロシュフーコーのいうように、ドーダの国の領土は広大無辺なのである。そこで、なんとかして西郷隆盛的なドーダの本質をつかみ出そうと努めたところ、ついに陰ドーダという概念に辿りついたのである。一見そうは見えないが、その本質においては立派なドーダであるようなドーダを「陰ドーダ」と命名すると、西郷隆盛のすべてが理解できるように思えたのだ。
そして、次にこの西郷隆盛的な「陰ドーダ」の概念を解読格子とすると、なんとしたことか、明治維新から今日に至る日本近代史を裏で駆動させていたメカニズムが鮮明に見えてきたのである。
それと同時に、私が長い間抱えていた疑問、すなわち、日本はなにゆえに、あの負けると分かっている対英米戦争に踏み切ってしまったのかという究極の疑問にもそれは答えてくれるような気がしてきたのである。
つまり、西郷隆盛的ドーダがわかれば、日本近代史最大の謎も解けるというわけだ。
こうして、「ドーダの近代史」と銘打った私の究極の謎解きの旅は始まり、足掛け四年かけて最終的な結論に辿りついたのである。
その結論については、本書で詳述したつもりであるが、結論を先に知りたがるせっかちな読者のために簡単に要約しておくと次のようになる。すなわち、西南戦争は戦争ではなく、西郷隆盛の陰ドーダ公式から演繹された革命の方法論に基づく「西南革命」であったのだが、なぜか、革命の弾圧側だった政府と陸軍は、以後、この西南革命の方法論に幻惑され、ついに自己の論理として取り込むに至ったということである。
私と同じように、対英米戦争開戦という永遠の謎にとりつかれた読者は多いはずだ。多少の参考になるのではないかと期待している。
今回、文庫化に当たって、『ドーダの近代史』を、西郷隆盛がメインのコンセプトであるという観点から『ドーダの人、西郷隆盛』と改めた。とはいえ、ドーダ学というのは、もとはといえば、東海林さだお氏のユーモア・エッセイを出発点としている「学問体系」である。笑いながら楽しんでいただければ幸いである。
文庫化に際しては、中央公論新社編集部の菅龍典さんにお世話になった。この場を借りて感謝の気持ちを捧げたい。
最後に、ドーダ学という得体の知れない「学問体系」にかかわったりしたら学者としての評価が下がるかもしれないという危険をかえりみず、対談相手を引き受けてくださった片山杜秀さんにも深甚なる感謝の気持ちをお伝えしたい。
二〇一八年八月十五日
鹿島 茂
ALL REVIEWSをフォローする